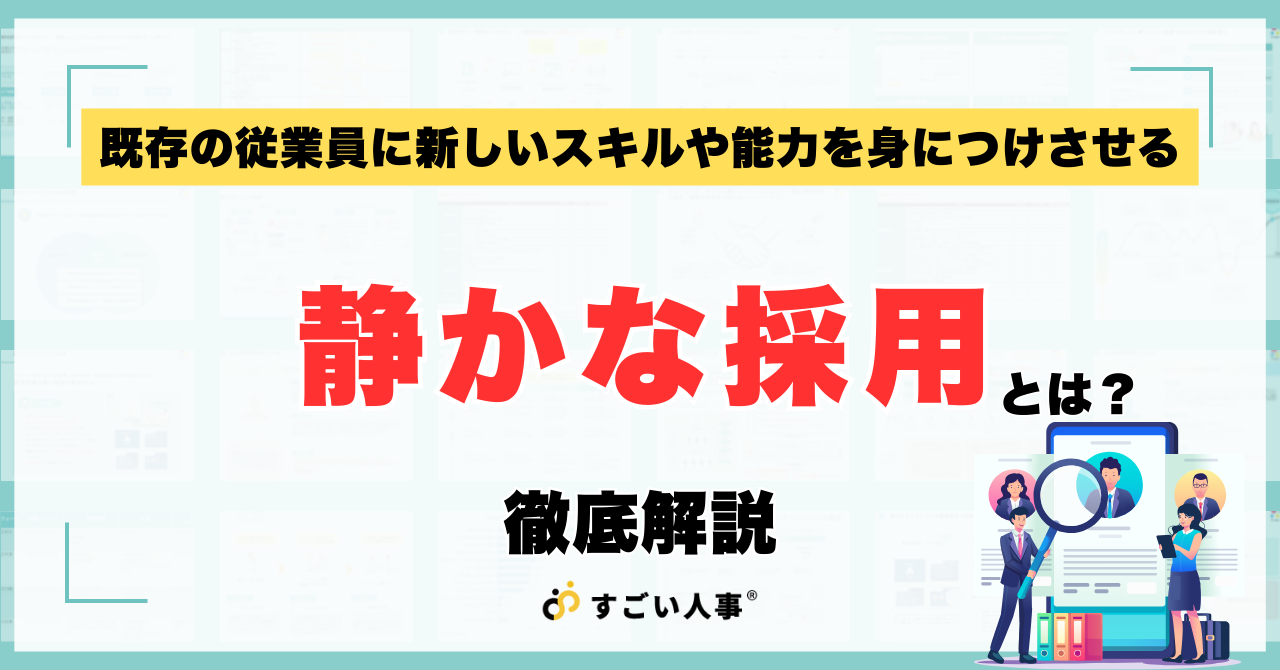
近年、人材獲得競争が激化し、予測不能な経済状況が続く現代において、企業は常に「いかにして優秀な人材を確保し、組織の生産性を高めるか」という命題に直面しています。しかし、外部からの新規採用はコストや時間がかかる上、ミスマッチのリスクも伴います。こうした背景から、今、人事戦略の新たな潮流として「静かな採用(Quiet Hiring)」が注目を集めています。本記事では、この「静かな採用」が具体的に何を意味するのか、企業にどのような導入メリットをもたらすのか、そして「静かな退職」との決定的な違いなどを、人事担当者様に向けて詳しく解説します。
目次
静かな採用とは?
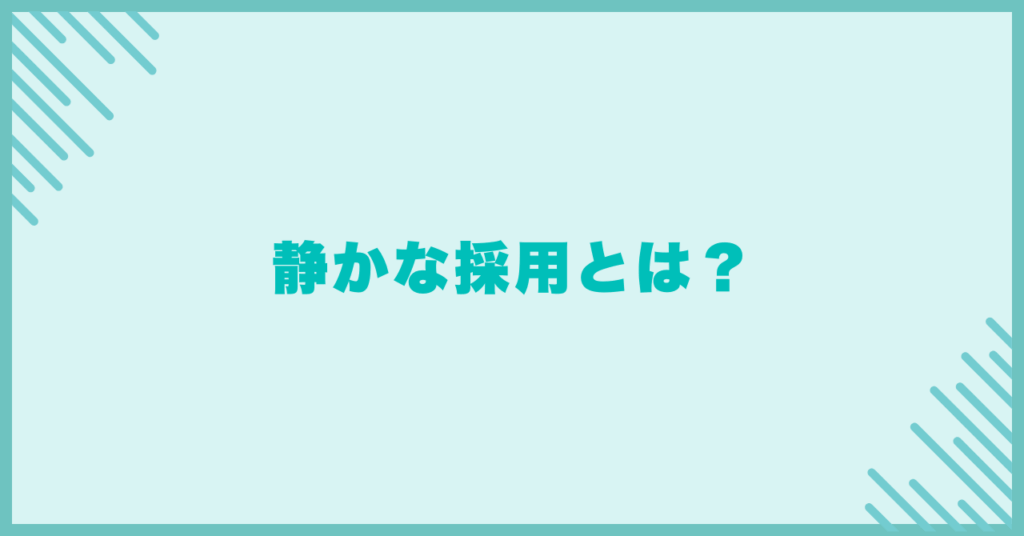
「静かな採用」とは、文字通り「静か」に、つまり外部に公募をかけることなく、組織内で人材ニーズを満たす戦略的アプローチを指します。具体的には、どのような概念なのでしょうか。
静かな採用の定義と具体的な手法
「静かな採用」とは、企業が外部から新たな正社員を雇用することなく、既存の従業員に新しいスキルや能力を身につけさせたり、異なる役割やプロジェクトを付与したりすることで、組織に必要なスキルや人材を確保し、組織力を最大化する戦略です。この概念は、米国の調査会社ガートナーが2023年のワーク・トレンド・レポートで提唱したことで、広く知られるようになりました。
静かな採用には、主に以下の3つの手法が含まれます。
1.社内異動・配置転換
既存の従業員を、現在とは異なる部署やポジションに配置し、新たな役割を担ってもらうことで、必要な人材を社内でまかないます。従業員の潜在能力を引き出し、新たなキャリアパスを提示する機会にもなります。
2.リスキリング・アップスキリング
従業員が新たなスキル(リスキリング)や、現在のスキルをさらに向上させる(アップスキリング)ための教育機会を提供します。これにより、将来的に必要となる業務に対応できる人材を育成します。
3.短期契約社員・フリーランスの活用
正社員の新規雇用ではなく、特定のプロジェクトや期間限定の業務に対して、短期間の契約社員やフリーランスといった外部人材を柔軟に活用するケースも、広義の「静かな採用」に含まれることがあります。
「静かな退職」との違い
「静かな採用」としばしば対比されるのが、「静かな退職」です。この二つの概念は、名称こそ似ていますが、その意味するところは全く異なります。
「静かな退職」とは、従業員が仕事に対する意欲や熱意を失い、契約上定められた最低限の業務だけをこなす働き方を指します。実際に退職するわけではありませんが、精神的には組織から離れている状態と言えるでしょう。
以下の表は、両者の違いをまとめたものです。
| 項目 | 静かな採用 | 静かな退職 |
| 主体 | 企業(経営者・人事) | 従業員 |
| 目的 | 組織力の最大化、人材育成、コスト削減 | ワークライフバランスの維持、精神的負担の軽減 |
| 従業員への影響 | スキルアップ、キャリア開発、エンゲージメント向上(ポジティブ) | スキル停滞、成長機会の損失、エンゲージメント低下(ネガティブ) |
| 組織への影響 | 生産性向上、人材定着、組織の活性化 | 生産性低下、イノベーションの停滞、離職リスクの増大 |
このように、「静かな採用」が従業員の成長を促し、組織を活性化させるポジティブな人材戦略であるのに対し、「静かな退職」は従業員のエンゲージメントが低下し、組織の活力が失われていくネガティブな現象であるという点で、両者は明確に区別されます。
なぜ今、「静かな採用」が注目されるのか?
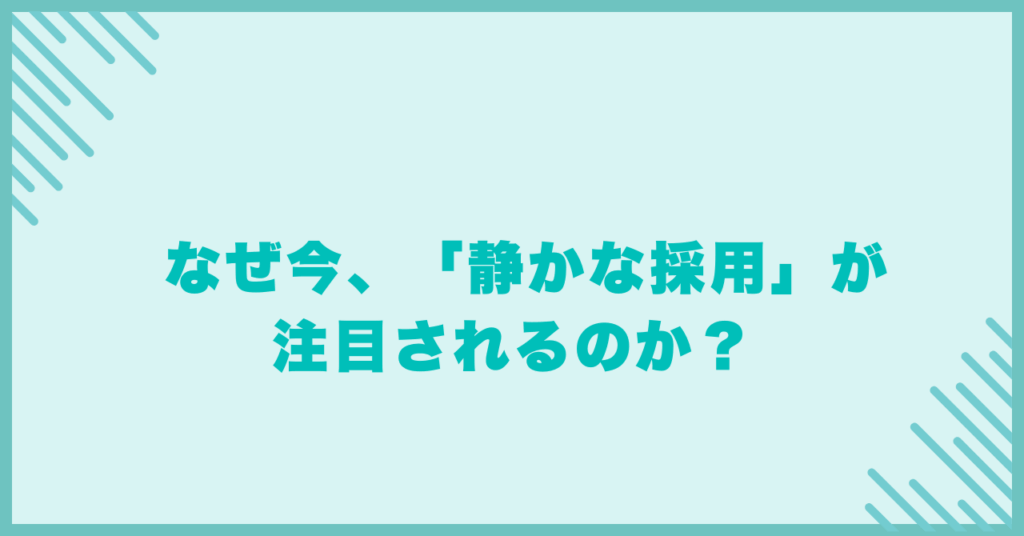
ガートナーが提唱して以降、多くの企業が「静かな採用」に関心を寄せています。その背景には、現代の企業が直面する深刻な課題があります。
採用市場の変化と人材獲得の難化
少子高齢化に伴う労働人口の減少は、多くの先進国で深刻な問題となっています。日本も例外ではなく、有効求人倍率は高止まりし、特に専門的なスキルを持つ人材の獲得競争は激化の一途をたどっています。このような状況下で、従来の新規採用だけに頼った人材戦略は限界を迎えつつあります。採用コストは高騰し、多大な時間と労力をかけても、必ずしも求める人材を確保できるとは限りません。こうした採用市場の変化が、企業に内部人材の活用、すなわち「静かな採用」へと目を向けさせているのです。
ビジネス環境の不確実性と求められるスキルの変化
デジタル化の急速な進展やグローバル化、そして予期せぬパンデミックなど、現代のビジネス環境は「VUCA(Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity)」の時代と言われるように、極めて不確実性が高まっています。このような環境下では、企業に求められるスキルも常に変化し続けます。昨日まで有効だったスキルが、明日には陳腐化してしまう可能性も否定できません。次々と現れる新たなビジネス課題に迅速に対応するためには、その都度外部から人材を採用していては間に合いません。既存の従業員に新たなスキルを習得させ、変化に柔軟に対応できる組織体制を構築する必要があり、その有効な手段として「静かな採用」が注目されています。
従業員エンゲージメントの低下という課題
「静かな退職」という言葉が広まったように、従業員のエンゲージメント(仕事に対する熱意や貢献意欲)の低下も、多くの企業が抱える課題です。単調な業務の繰り返しや、自身の成長が感じられない環境は、従業員のモチベーションを削ぎ、組織全体の生産性を低下させる要因となります。「静かな採用」は、従業員に新たな挑戦の機会やスキルアップの道筋を示すことで、仕事へのやりがいやエンゲージメントを高める効果が期待できます。自身の成長が会社の成長に繋がるという実感は、従業員の定着率向上にも貢献するでしょう。
静かな採用がもたらすメリット
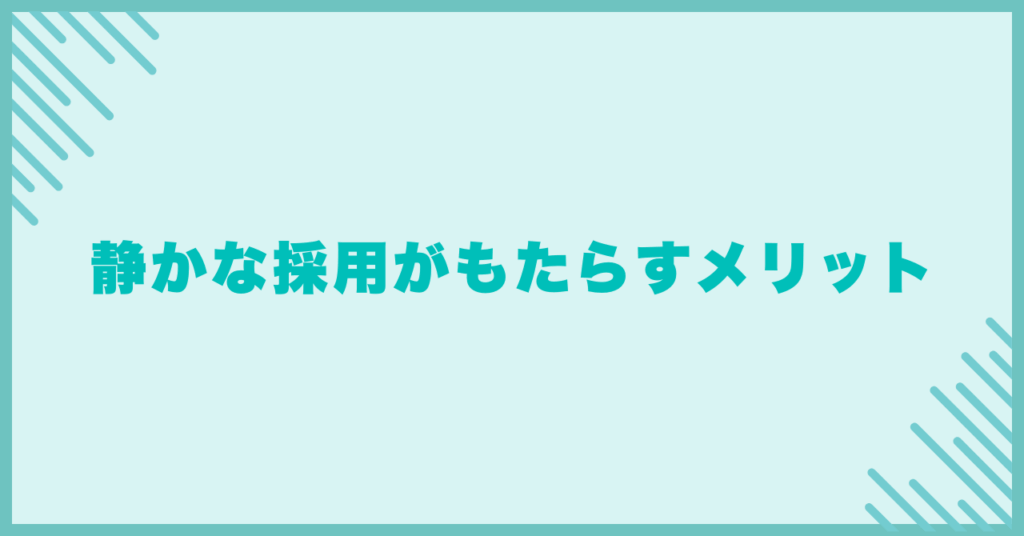
「静かな採用」は、単なる人材不足への対症療法にとどまらず、企業と従業員の双方に多くのメリットをもたらす可能性を秘めています。
企業側のメリット
企業にとって、「静かな採用」はコスト削減や組織の柔軟性向上といった直接的な利益に繋がります。
1. 採用コストと時間の大幅な削減
新規採用には、求人広告費、人材紹介会社への手数料、採用担当者の人件費、そして入社後の研修費用など、多大なコストと時間がかかります。「静かな採用」は、これらの採用プロセスを省略できるため、コストと時間を大幅に削減できます。削減できたリソースを、事業のコア業務や新たな投資に振り分けることで、企業全体の競争力を高めることができます。
2. 組織の柔軟性と迅速なリソース配分
変化の激しいビジネス環境において、必要なスキルを持つ人材を迅速に確保することは極めて重要です。「静かな採用」を活用すれば、外部の採用市場に頼ることなく、社内の人材を新たなプロジェクトや緊急性の高い業務に迅速に配置することが可能になります。これにより、ビジネスチャンスを逃すことなく、柔軟な組織運営が実現します。
3. 人材の定着と生産性の向上
従業員に新たなスキル習得やキャリアアップの機会を提供することは、仕事への満足度やエンゲージメントを高める上で非常に効果的です。自身の成長を実感できる従業員は、組織への帰属意識が高まり、定着率の向上が期待できます。また、スキルアップした従業員一人ひとりの生産性が向上することは、組織全体の生産性向上に直結します。
従業員側のメリット
「静かな採用」は、従業員にとっても自身のキャリアを豊かにする多くの機会を提供します。
1. スキルアップとキャリア開発の機会
新しい役割や責任ある立場を任されることは、従業員にとって自身の潜在能力を試し、新たなスキルを習得する絶好の機会となります。特に、若手従業員にとっては、実務を通じて成長できる貴重な経験となるでしょう。会社からの期待を感じながら挑戦することで、従業員のキャリアはより豊かなものになります。
2. 仕事へのモチベーション向上
「静かな退職」に見られるように、仕事へのマンネリ感はモチベーション低下の大きな原因です。「静かな採用」によって、これまでとは異なる新鮮な業務や、より難易度の高い仕事に挑戦する機会が与えられると、従業員の仕事に対するモチベーションは大きく向上する可能性があります。新たな目標に向かって主体的に取り組む姿勢は、職場全体にも良い影響を与えるでしょう。
3. 安定した環境でのキャリアチェンジ
転職には、新しい環境への適応や人間関係の構築など、多くの精神的負担が伴います。「静かな採用」による社内での役割変更は、慣れ親しんだ企業文化や人間関係の中で、比較的低いリスクで新たなキャリアに挑戦できるというメリットがあります。これにより、従業員は安心して自身のキャリアの可能性を追求することができます。
静かな採用を成功させるための注意点
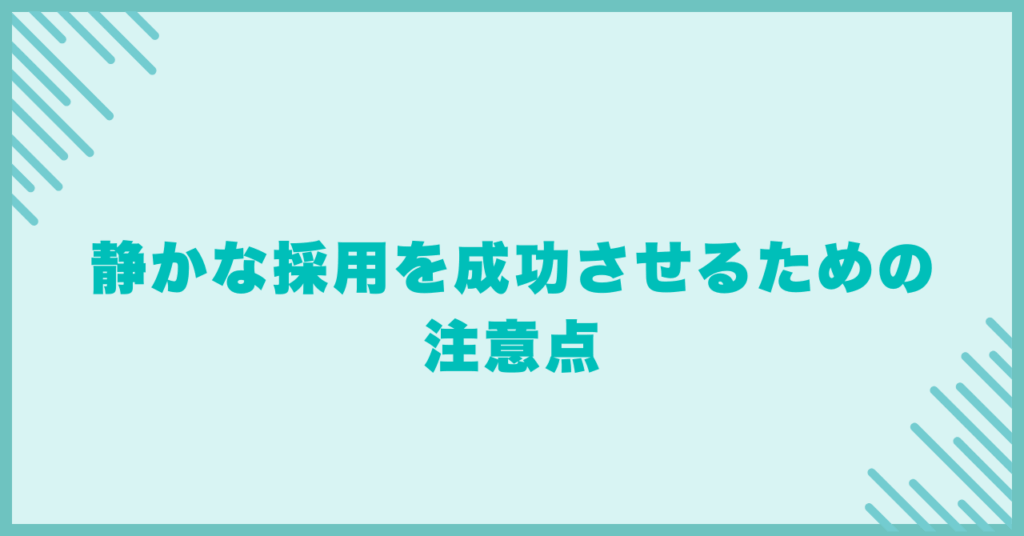
多くのメリットを持つ「静かな採用」ですが、その運用を誤ると、かえって従業員の不満を高め、逆効果となりかねません。成功のためには、いくつかの重要な点に注意する必要があります。
従業員への過度な負担と燃え尽き症候群のリスク
「静かな採用」で最も注意すべきは、従業員への過度な負担です。特に、既存の業務に加えて新たな役割を付与する場合、業務量が個人のキャパシティを超えてしまう危険性があります。このような状態が続くと、従業員は心身ともに疲弊し、燃え尽き症候群(バーンアウト)に陥ってしまう可能性があります。これは、「静かな退職」を引き起こす大きな要因の一つでもあります。企業は、新たな役割を与える際には、既存の業務内容や業務量を見直し、適切なサポート体制を整えることが不可欠です。
公平な評価と適切な報酬の重要性
新たな役割や責任が付与されたにもかかわらず、それに見合った評価や報酬が伴わなければ、従業員の不満は増大します。「頑張っても報われない」という感情は、モチベーションを著しく低下させ、エンゲージメントの喪失に繋がります。企業は、「静かな採用」を導入するにあたり、人事評価制度を見直し、付与された役割や責任、そして成果が、昇進や昇給、ボーナスといった形で適切に報われる仕組みを構築する必要があります。
従業員との対話と役割の明確化
「静かな採用」は、トップダウンで一方的に進めるべきではありません。企業は、対象となる従業員と十分にコミュニケーションを取り、新たな役割を付与する背景や期待する成果を丁寧に説明する必要があります。その上で、従業員自身のキャリアプランや意向を尊重し、双方にとって納得のいく形で進めることが重要です。役割の定義が曖昧なままでは、従業員は何をすべきか分からず、混乱や不安を招くだけです。具体的な役割と期待値を明確に言語化し、共有することが成功の鍵となります。
まとめ
本記事では、新たな人事戦略の潮流である「静かな採用」について、その定義からメリット、そして成功のための注意点までを詳しく解説しました。
「静かな採用」は、採用コストの削減や組織の柔軟性向上といった企業側のメリットだけでなく、従業員のスキルアップやモチベーション向上にも繋がる、Win-Winの可能性を秘めた戦略です。しかし、その運用には、従業員への過度な負担や不公平感といったリスクも伴います。
「静かな採用」を成功に導くためには、従業員一人ひとりと向き合い、その成長を支援するという真摯な姿勢が不可欠です。公平な評価制度と適切な報酬、そして丁寧なコミュニケーションを通じて、従業員のエンゲージメントを高め、変化に強いしなやかな組織を構築していくこと。それこそが、これからの時代に求められる人事戦略と言えるのではないでしょうか。

「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe
Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界1300名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス
⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス
⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス
などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。
