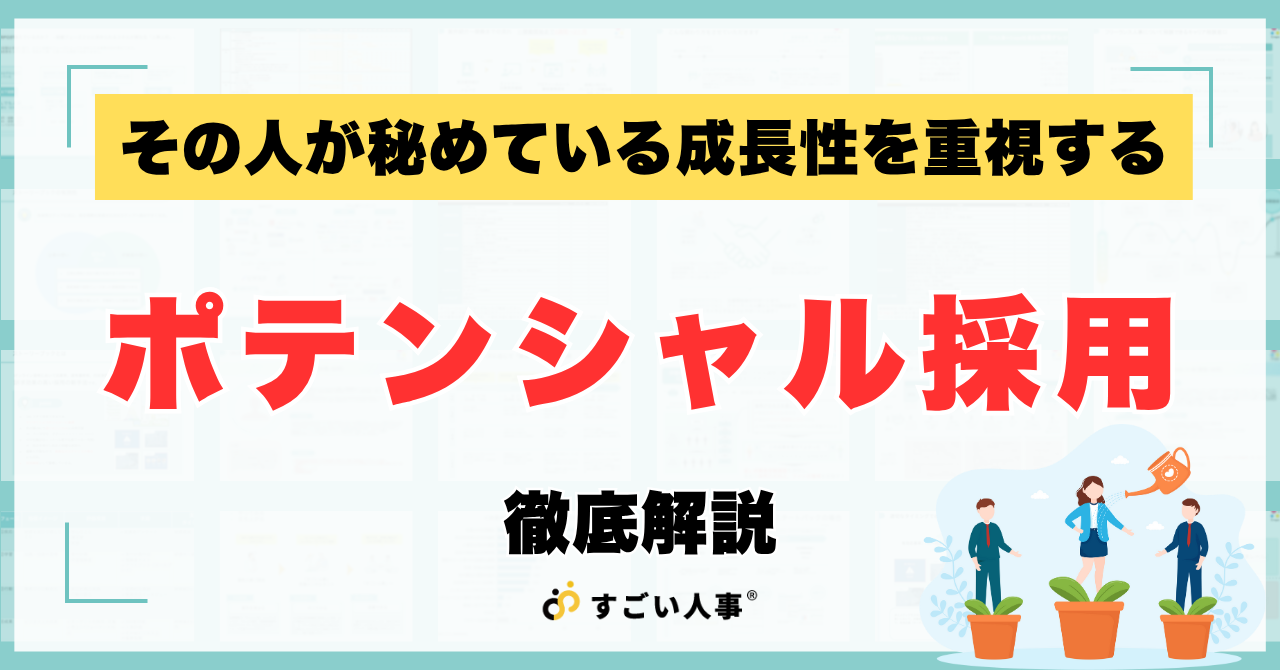
【経営者・人事必見】ポテンシャル採用完全ガイド|メリット・デメリットから成功の秘訣まで徹底解説
現代のビジネス環境は、少子高齢化に伴う労働人口の減少という構造的な課題に直面しています。多くの企業が、必要な人材を確保することに困難を感じており、特に即戦力となる優秀な人材の獲得競争は激化の一途をたどっています。このような状況下で、従来通りの採用手法だけでは、企業の持続的な成長は望めません。
そこで今、新たな採用戦略として注目を集めているのが「ポテンシャル採用」です。これは、応募者の現在のスキルや経験のみに固執するのではなく、その人が秘める「潜在能力(ポテンシャル)」、すなわち将来性や成長可能性を重視して採用するアプローチを指します。
本記事では、企業の経営者や人事担当者の皆様に向けて、ポテンシャル採用について徹底的に解説します。
目次
- ポテンシャル採用とは?
- なぜ今、ポテンシャル採用が注目されるのか?
- 企業が享受するポテンシャル採用の4つのメリット
- 押さえておくべきポテンシャル採用のデメリットと3つの注意点
- ポテンシャル採用を成功に導くための4つの重要ポイント
- まとめ
ポテンシャル採用とは?
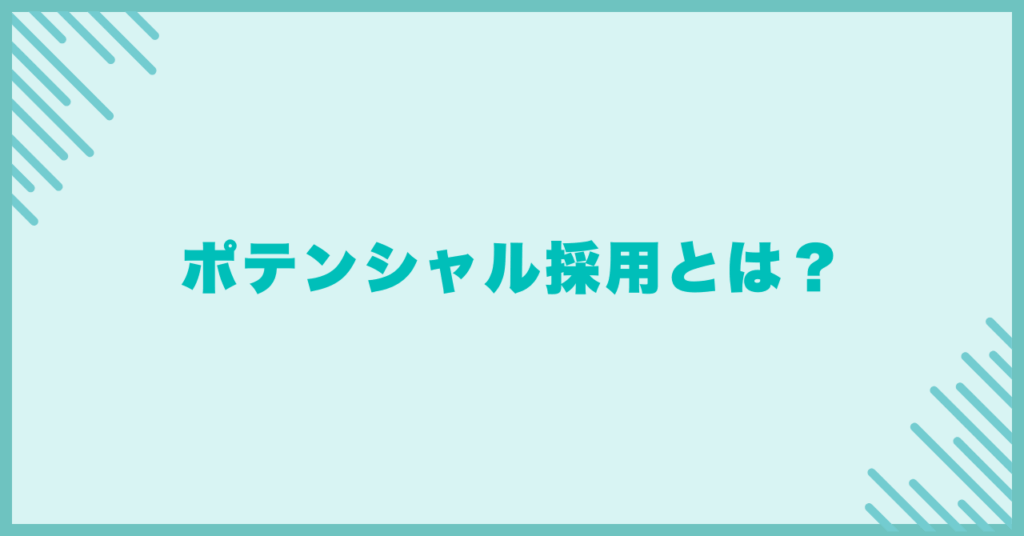
ポテンシャル採用とは、応募者が現時点で保有しているスキルや職務経験といった顕在的な能力だけでなく、その人物が内に秘める「潜在能力(ポテンシャル)」、すなわち将来性、学習意欲、人柄、企業文化への適応性などを重視して人材を選考する採用手法です。即戦力採用が中心となる従来の中途採用とは一線を画し、中長期的な視点で企業に貢献し、成長していく可能性のある人材を発掘・育成することを目的としています。
ポテンシャル採用の基本的な定義
ポテンシャル採用の核心は、「将来の活躍を見据えた投資」という考え方にあります。企業は、応募者が現時点で完璧なスキルセットを持っていなくても、自社の教育・研修プログラムを通じて成長し、将来的に重要な役割を担う人材になることを見込んで採用を決定します。
主な対象は新卒学生や第二新卒、社会人経験の浅い20代の若手層ですが、特定の年齢制限が設けられているわけではありません。30代であっても、異業種へのチャレンジ意欲が高く、新たな環境への適応能力や高い学習意欲が認められれば、ポテンシャル採用の対象となるケースは十分にあり得ます。
ポテンシャル採用は、候補者の現在のスキルや経験ではなく、成長意欲や学習能力、適応力、リーダーシップなどの潜在的な能力を重視する採用手法です。中途採用、キャリア採用のように即戦力を求めるのではなく、将来的な活躍や自社のカルチャーとの適性を見込み、長期的な視点で人材を採用します。
中途採用(キャリア採用)・新卒採用との決定的な違い
ポテンシャル採用の理解を深めるために、従来からある「中途採用(キャリア採用)」および「新卒採用」との違いを明確にしておきましょう。これらの採用手法は、ターゲットとなる人材層や選考で重視するポイントが異なります。
| 採用手法 | 主なターゲット層 | 選考で重視するポイント |
| ポテンシャル採用 | 新卒、第二新卒、若手社会人(主に20代) | 将来性、学習意欲、人柄、企業文化への適応性 |
| 中途採用(キャリア採用) | 特定のスキル・経験を持つ社会人 | 即戦力となる専門スキル、実績、マネジメント経験 |
| 新卒採用 | 大学・大学院・専門学校などを卒業予定の学生 | ポテンシャル、学習意欲、基礎的な能力、人柄 |
中途採用(キャリア採用)との違いは、求める能力の時間軸にあります。中途採用が「現在」の高い専門性や即戦力を求めるのに対し、ポテンシャル採用は「未来」の成長可能性に投資します。欠員補充や事業拡大に伴う専門職の確保など、特定のポジションで直ちに成果を出す人材が必要な場合は中途採用が適しています。
一方、新卒採用との違いは、対象となる層の広さにあります。新卒採用が社会人経験のない学生に限定されるのに対し、ポテンシャル採用は、社会人経験が数年ある第二新卒や、キャリアチェンジを目指す若手社会人も対象に含みます。これにより、新卒採用の枠組みだけでは出会えなかった、多様なバックグラウンドを持つ人材にアプローチすることが可能になります。
なぜ今、ポテンシャル採用が注目されるのか?
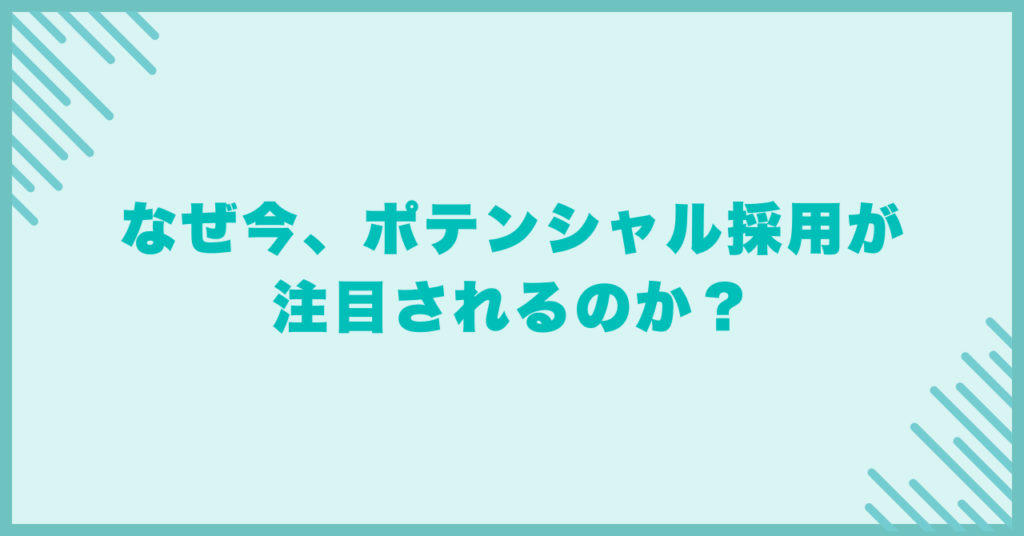
近年、多くの企業がポテンシャル採用に注目し、導入を進めています。その背景には、現代の日本が抱える労働市場の構造的な変化と、それに伴う企業経営の課題があります。ここでは、ポテンシャル採用が重要視される3つの主要な理由を掘り下げて解説します。
深刻化する労働人口の減少と採用競争の激化
第一に、少子高齢化による生産年齢人口の減少が深刻な問題となっています。厚生労働省の調査によると、日本の生産年齢人口(15~64歳)は1995年をピークに減少し続けており、今後もこの傾向は続くと予測されています。労働力の絶対数が減少する中で、企業は限られた人材を奪い合う状況に置かれています。
特に、高い専門性を持つ即戦力人材の採用は極めて困難になっており、有効求人倍率は高止まりしています。リクルートワークス研究所の調査では、2025年卒の大卒求人倍率は1.75倍と、依然として高い水準で推移しており、企業が求める人材を十分に確保できていない実態が浮き彫りになっています。このような売り手市場において、従来の即戦力採用だけに固執していては、事業に必要な人材を確保すること自体が困難になるのです。
高騰し続ける採用コストと、その解決策として
採用競争の激化は、必然的に採用コストの高騰を招きます。求人広告費や人材紹介会社への成功報酬は年々上昇傾向にあり、企業の財政的な負担は増大しています。特に、希少なスキルを持つエンジニアなどの専門職を中途採用する場合、一人当たり数百万円のコストがかかることも珍しくありません。
ポテンシャル採用は、この課題に対する有効な解決策となり得ます。未経験者や経験の浅い若手層を対象とすることで、即戦力採用に比べて一人当たりの採用単価を抑制することが可能です。もちろん、入社後の教育・研修にコストはかかりますが、長期的な視点で見れば、採用コストと育成コストのトータル費用を最適化できる可能性があります。
組織の持続的成長に不可欠な、多様な人材の確保
変化の激しい現代のビジネス環境において、企業が持続的に成長するためには、組織の多様性(ダイバーシティ)を確保し、イノベーションを創出し続けることが不可欠です。しかし、同質的な経験やスキルを持つ人材ばかりを集めていては、組織は硬直化し、新たな発想は生まれにくくなります。
ポテンシャル採用は、この課題を解決する上でも重要な役割を果たします。採用の門戸を広げることで、異業種での経験を持つ人材や、海外留学、ワーキングホリデーといった多様なバックグラウンドを持つ人材を獲得する機会が生まれます。こうした多様な視点や価値観が組織に新しい風を吹き込み、既存の枠組みにとらわれないイノベーションの創出や、組織全体の活性化につながることが期待されるのです。
企業が享受するポテンシャル採用の4つのメリット
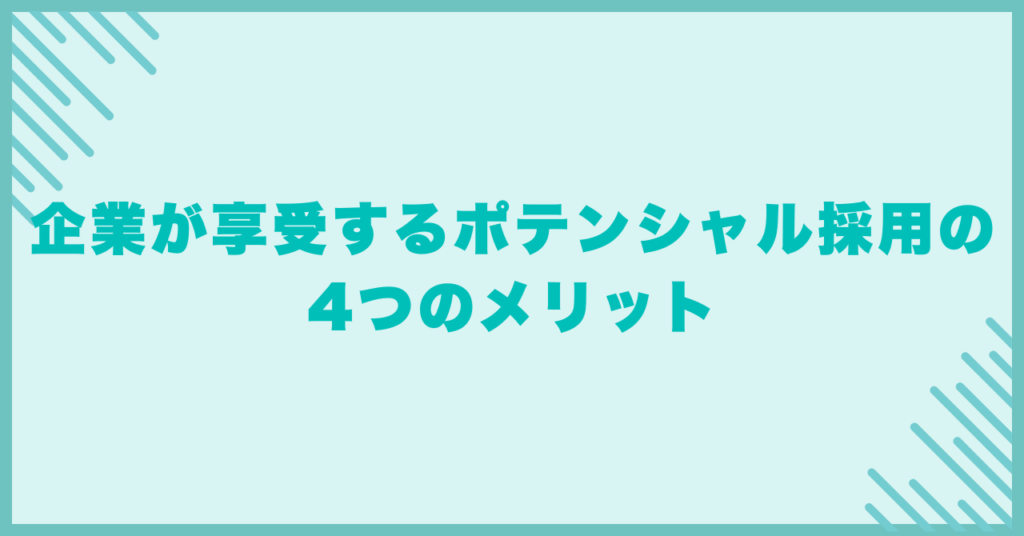
ポテンシャル採用は、単に採用難を乗り越えるためだけの守りの戦略ではありません。企業の未来を創るための、攻めの戦略として多くのメリットをもたらします。ここでは、企業が享受できる4つの主要なメリットについて具体的に解説します。
メリット1:将来のリーダー候補となる優秀な若手人材の獲得
最大のメリットは、将来的に企業の中核を担う可能性を秘めた、優秀な若手人材を獲得できることです。近年の若手層は、自身のキャリア形成に対する意識が高く、必ずしも一つの企業に長く勤めることを前提としていません。「今後のキャリアや自身の適性を見極め、チャンスがあればマッチする企業に転職したい」と考える優秀な人材は、大手企業や有名企業だけでなく、自身の成長機会を求めて中小企業やベンチャー企業にも目を向けています。
ポテンシャル採用を導入することで、こうした成長意欲の高い若手層に対して、自社の魅力や成長環境をアピールし、従来の採用チャネルでは出会えなかった優秀な人材を獲得する新たな道が開かれます。
メリット2:新卒採用と比較した際の教育コスト削減効果
ポテンシャル採用の対象となる第二新卒や若手社会人は、既に社会人としての基本的なマナーやビジネススキルを身につけている場合がほとんどです。そのため、ビジネスマナー研修やPCスキルの基礎研修といった、新卒社員に必要となる導入教育を大幅に簡略化、あるいは省略することが可能です。
もちろん、業界知識や専門スキルに関する研修は別途必要ですが、社会人としての基礎教育にかかるコストと時間を削減できる点は、大きなメリットと言えるでしょう。これにより、企業はより専門的なスキルの習得や、早期の戦力化に向けたOJT(On-the-Job Training)にリソースを集中させることができます。
メリット3:組織の活性化とイノベーションを促進するダイバーシティ
異なる業界や職種での経験を持つ人材を採用することは、組織に多様性(ダイバーシティ)をもたらし、新たなイノベーションの起爆剤となり得ます。同じようなバックグラウンドを持つ人材ばかりが集まった組織は、思考の同質化が進み、環境変化への対応力が低下するリスクがあります。
ポテンシャル採用を通じて、多様な価値観や経験を持つ人材を組織に迎え入れることで、既存の常識にとらわれない新しいアイデアや視点が生まれる土壌が育まれます。これは、新たな商品やサービスの開発、業務プロセスの改善など、企業の競争力を高める上で非常に重要な要素です。
メリット4:企業文化への高いフィットと定着率の向上
ポテンシャル採用では、スキルや経験以上に、候補者の価値観や人柄が自社の企業文化(カルチャー)に合致するかどうかを重視します。カルチャーフィットを重視した採用は、入社後のミスマッチを防ぎ、社員のエンゲージメントと定着率を高める効果が期待できます。
自社のビジョンや価値観に共感して入社した人材は、仕事へのモチベーションが高く、組織への貢献意欲も強い傾向にあります。また、既存のやり方に染まっていないため、企業文化を素直に受け入れ、組織にスムーズに溶け込みやすいという利点もあります。これは、長期的な視点で見た場合、組織の一体感を醸成し、企業全体の生産性を向上させる上で大きなプラスとなります。
押さえておくべきポテンシャル採用のデメリットと3つの注意点
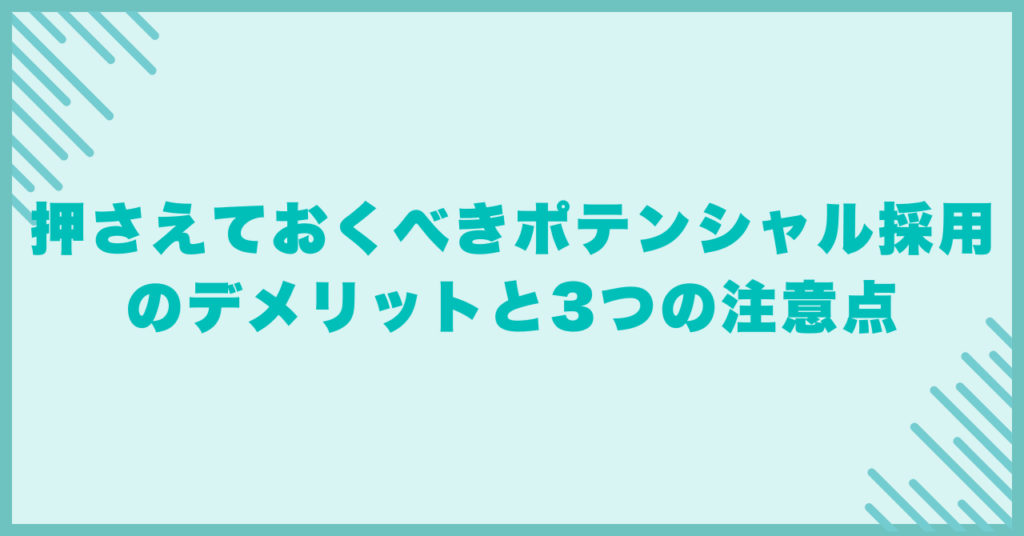
多くのメリットがある一方で、ポテンシャル採用には見過ごすことのできないデメリットや注意点も存在します。これらのリスクを事前に理解し、対策を講じることが、採用活動を成功させる上で不可欠です。ここでは、特に注意すべき3つのデメリットとその対策について解説します。
デメリット1:即戦力化までの育成コストと時間的投資
ポテンシャル採用で獲得した人材は、あくまで「将来の成長が期待される人材」であり、即戦力ではありません。特に業務未経験の分野に挑戦する場合、専門知識やスキルを習得し、一人前に業務をこなせるようになるまでには、相応の教育・研修コストと時間的な投資が必要です。
また、新卒社員向けの画一的な研修プログラムをそのまま適用できないケースも多く、個々のスキルレベルやキャリアに合わせた育成プランを別途設計する必要があります。この育成体制の構築が不十分な場合、せっかく採用した人材が期待通りに成長せず、結果的にコストだけがかさんでしまうという事態に陥りかねません。
デメリット2:活躍までのタイムラグと周囲のサポート体制の必要性
育成に時間がかかるということは、採用した人材が本格的に戦力として活躍し始めるまでにタイムラグが生じることを意味します。この期間、現場の既存社員は、自身の業務に加えて新人教育の負担を担うことになります。特に、人員に余裕のない中小企業や、繁忙な部署においては、この教育負担が現場の疲弊を招き、全体の生産性を一時的に低下させるリスクも考慮しなければなりません。
採用担当者や経営層だけでなく、配属先の部署全体で「ポテンシャル人材を育てる」という共通認識を持ち、メンター制度の導入や定期的な面談の実施など、組織的なサポート体制を構築することが極めて重要です。
デメリット3:ミスマッチが引き起こす早期離職のリスクと、その対策
ポテンシャル採用の対象となる若手層は、自身のキャリアに対して柔軟な考えを持っているがゆえに、転職に対する心理的なハードルが低い傾向にあります。入社前に抱いていた業務内容や企業文化に対するイメージと、入社後の現実にギャップを感じた場合、早期離職に至ってしまう可能性は、経験者採用に比べて高いと言えるでしょう。
このミスマッチを防ぐためには、選考段階で候補者に対して「良いこと」ばかりを伝えるのではなく、仕事の厳しさや困難な側面も含めて、ありのままの情報を正直に伝えることが求められます。また、入社後も定期的に1on1ミーティングなどを実施し、本人が抱える不安や悩みを早期にキャッチアップし、解消していくためのフォロー体制が不可欠です。
ポテンシャル採用を成功に導くための4つの重要ポイント
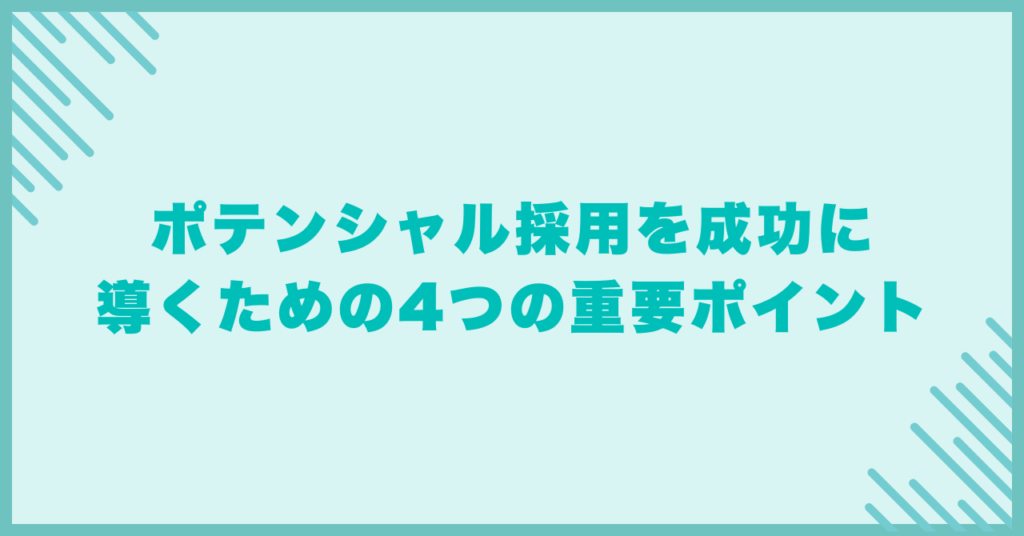
ポテンシャル採用は、単に未経験者を採用することではありません。企業の未来を託す人材を見極め、育てるという戦略的な活動です。ここでは、その成功確率を飛躍的に高めるための4つの重要なポイントを解説します。
ポイント1:自社に最適な「求める人材像」の明確な定義
成功の第一歩は、「自社にとってのポテンシャル人材とは何か」を具体的に定義することから始まります。漠然と「意欲のある若手」を求めるだけでは、選考基準が曖昧になり、ミスマッチの原因となります。
コンピテンシーの明確化
自社で高いパフォーマンスを発揮している社員(ハイパフォーマー)に共通する行動特性(コンピテンシー)を分析し、それを採用基準に落とし込みます。「主体性」「学習意欲」「論理的思考力」「チームワーク」など、具体的な言葉で定義することが重要です。
カルチャーフィットの見極め
自社のビジョン、ミッション、バリューを明確にし、それに共感し、体現してくれる人材かどうかを見極める基準を設定します。
これらの「求める人材像」を、経営層、人事、現場の各部門が一体となって議論し、共通認識を持つことが、採用活動の軸をブラさずに進める上で不可欠です。
ポイント2:潜在能力を見抜くための選考プロセスの設計と面接術
潜在能力は、職務経歴書や短い面接だけでは簡単に見抜けません。候補者の本質的な資質や思考の特性を多角的に評価するための、工夫された選考プロセスが必要です。
構造化面接の導入
あらかじめ評価基準と質問項目を具体的に定めておき、全ての候補者に同じ質問をすることで、評価の客観性を担保する手法です。「過去の経験で、最も困難だった課題をどのように乗り越えましたか?」といった行動ベースの質問(STARメソッドなど)は、候補者のポテンシャルを測る上で非常に有効です。
適性検査やワークサンプルの活用
候補者の性格特性やストレス耐性、論理的思考力などを客観的に測定する適性検査や、実際の業務に近い課題に取り組んでもらうワークサンプル(例:営業職ならロールプレイング、企画職なら企画立案)を取り入れることで、面接だけでは分からない側面を評価できます。
現場社員との面談機会
最終的な配属先となる部署の社員とカジュアルな面談の場を設けることも有効です。候補者は現場のリアルな声を聞くことができ、企業側も現場視点でのカルチャーフィットを見極めることができます。
ポイント3:入社後の成長を加速させる育成・フォローアップ体制の構築
ポテンシャル採用は、「採用して終わり」ではありません。むしろ、入社後こそが本番です。原石である人材をいかに磨き、輝かせるかが成功の鍵を握ります。
体系的な研修プログラム
業界知識や専門スキルを習得するためのOff-JT(Off-the-Job Training)と、実際の業務を通じて学ぶOJTを組み合わせた、体系的な育成プログラムを設計します。
メンター制度の導入
年齢の近い先輩社員をメンターとして任命し、業務上の指導だけでなく、精神的なサポートも行う体制を整えることで、新入社員の不安を和らげ、早期の立ち上がりを支援します。
定期的な1on1ミーティング
上司と部下が定期的に1対1で対話する機会を設け、キャリアプランや業務上の課題について話し合います。これにより、エンゲージメントを高め、離職の兆候を早期に察知することが可能になります。
ポイント4:ターゲット層に響く、効果的な求人媒体の選定と活用
求める人材像が明確になったら、その人材がどこにいるのかを考え、最適なアプローチ方法を選択する必要があります。
若手向け求人サイト・転職エージェント
第二新卒や20代をメインターゲットとする求人媒体や、若手層のキャリア支援に強みを持つ転職エージェントを活用します。
ダイレクトリクルーティング
企業側から候補者に直接アプローチできるダイレクトリクルーティングサービスを活用し、潜在的な転職希望者にも積極的に働きかけます。
リファラル採用
自社の社員から友人や知人を紹介してもらうリファラル採用は、カルチャーフィットした人材を獲得する上で非常に効果的です。
求人情報を作成する際は、単に業務内容を羅列するだけでなく、「どのような経験が積めるのか」「どのようなキャリアパスが描けるのか」といった、候補者の成長意欲に訴えかけるメッセージを明確に打ち出すことが重要です。
まとめ
本記事では、ポテンシャル採用の基本的な概念から、そのメリット・デメリット、そして成功に導くための具体的なポイントまでを網羅的に解説しました。
労働人口の減少と採用競争の激化という、避けては通れない課題に直面する現代において、ポテンシャル採用はもはや単なる選択肢の一つではありません。企業の持続的な成長を実現するために不可欠な、「未来への戦略的投資」と言えるでしょう。
確かに、ポテンシャル採用には育成の時間やコスト、ミスマッチのリスクといった側面も存在します。しかし、これらの課題は、本記事でご紹介したような、明確な人材要件の定義、戦略的な選考プロセスの設計、そして入社後の手厚い育成・フォローアップ体制を構築することで、十分に乗り越えることが可能です。
目先のスキルや経験にとらわれず、個人の持つ無限の可能性に目を向け、共に成長していく。その姿勢こそが、変化の激しい時代を勝ち抜くための強固な組織基盤を築き、企業の未来を切り拓く原動力となるはずです。
「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe
Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界1300名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス
⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス
⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス
などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。
