
note採用広報とは?メリット・デメリットと成功事例5選を徹底解説
現代の採用市場は、売り手市場が続くとともに、求職者の価値観も大きく変化しています。単なる労働条件だけでなく、企業のビジョンやカルチャーへの共感を重視する傾向が強まっています。このような状況下で、従来の一方的な求人広告だけでは、自社の魅力を十分に伝えきれず、理想の人材と出会うことが難しくなっています。
そこで注目されているのが、企業の「物語(ストーリー)」を伝えることの重要性です。創業の想い、事業にかける情熱、働く社員のリアルな姿といったストーリーは、求職者の感情に訴えかけ、深い共感を生み出します。このストーリーテリングを実践する上で、非常に親和性が高いプラットフォームが「note」です。
なぜnoteなのか?
自由な表現形式:長文のテキスト、画像、動画などを組み合わせ、企業の魅力を多角的に表現できます。
共感を呼ぶ文化:ユーザーが良質なコンテンツを評価し、共有する文化が根付いています。
潜在層へのリーチ:今すぐの転職を考えていない優秀な人材にも、企業の魅力を届けることができます。
本記事では、noteを活用した採用広報(以下、note採用広報)のメリット・デメリットから、具体的な成功事例、そして明日から実践できるステップまで、人事・経営者の皆様に向けて徹底的に解説します。企業の未来を担う理想の人材と出会うための、新たな一手として、ぜひ最後までご覧ください。
目次
noteを活用した採用広報のメリット・デメリット
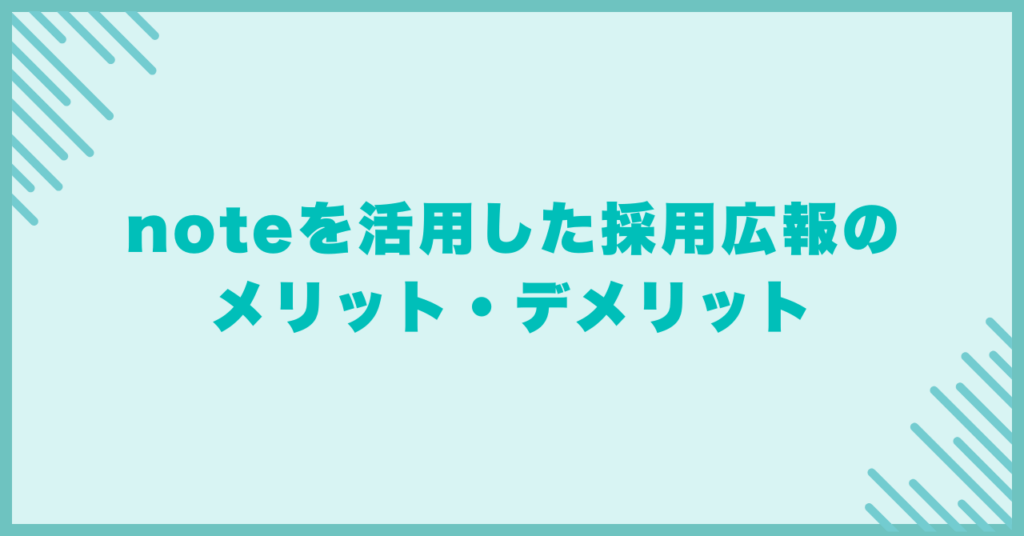
noteを採用広報に活用することは、多くの企業にとって大きな武器となり得ますが、その一方で注意すべき点も存在します。ここでは、具体的なメリットとデメリットを詳しく見ていきましょう。
採用活動に革命を。noteがもたらす4つのメリット
noteを戦略的に活用することで、採用活動は新たなステージへと進化します。企業と求職者の間に、より深く、強固な結びつきを生み出す4つの主要なメリットを解説します。
メリット1:採用ミスマッチの防止
採用における最大の課題の一つが、入社後のミスマッチです。求人票の限られた情報だけでは、企業の文化や働き方の実態を正確に伝えることは困難です。noteでは、社員インタビューや一日の仕事の流れ、プロジェクトの裏側、時には失敗談まで、リアルな情報を包み隠さず発信できます。これにより、求職者は企業をより深く、多角的に理解することができ、入社後のギャップを大幅に減らすことが可能です。「こんなはずではなかった」という早期離職を防ぎ、定着率の向上に繋がります [1]。
メリット2:採用コストの削減
noteは、長期的な視点で見ると採用コストの削減に大きく貢献します。企業の魅力やストーリーが詰まった質の高いコンテンツが蓄積されていくと、それが企業の資産となります。求職者が自社のnoteを読んで深く共感し、高い意欲を持って応募してくれるようになれば、高額な求人広告への依存度を下げることができます。また、note経由の応募者は、企業理解度が高く、志望動機も明確であるため、選考プロセスがスムーズに進み、内定承諾率の向上も期待できます。結果として、一人当たりの採用単価を抑制することに繋がるのです [2]。
メリット3:潜在層への効果的なアプローチ
「今すぐ転職したい」と考えている顕在層だけでなく、まだ転職を具体的に考えていない「潜在層」にアプローチできる点も、noteの大きな強みです。業界の動向解説や、専門的な技術知見、キャリアに関する考察など、採用とは直接関係のない有益な情報を発信することで、多くのビジネスパーソンとの接点を持つことができます。日常的にnoteで情報収集をしている優秀な人材が、あなたの会社に興味を持つきっかけとなり、将来的な採用候補者の母集団形成に繋がります。
メリット4:社員のエンゲージメント向上
note採用広報は、社外だけでなく社内にもポジティブな影響をもたらします。社員が自らの仕事や会社について語る記事を作成する過程で、自身の業務の意義や会社への貢献を再認識することができます。また、他部署の取り組みや仲間の活躍を知ることで、社内コミュニケーションが活性化し、組織としての一体感が醸成されます。社員が自社に誇りを持ち、エンゲージメントが高まることは、採用力強化だけでなく、企業全体の成長にとっても不可欠な要素と言えるでしょう。
始める前に知っておきたい2つのデメリットと対策
多くのメリットがある一方で、note採用広報にはいくつかの注意点もあります。事前にデメリットを理解し、対策を講じることで、失敗のリスクを最小限に抑えることができます。
デメリット1:運用コスト(リソース)がかかる
noteのコンテンツは、誰かが企画し、執筆し、公開するというプロセスを踏む必要があり、相応の人的リソースがかかります。特に、質の高い記事を定期的に更新し続けるには、専任の担当者を置くか、チームで分担するなどの体制構築が不可欠です。現場の社員に執筆を依頼する場合も、通常業務との兼ね合いや、文章を書くことへの心理的なハードルを考慮する必要があります。
【対策】
スモールスタートを心がける:まずは月1〜2本の更新から始め、無理のない範囲で継続することを目指しましょう。
運用体制を明確にする:編集長や担当者を決め、企画、執筆、編集の役割分担を明確にします。
外部リソースの活用:社内での運用が難しい場合は、採用広報支援サービスなどを利用し、プロの力を借りることも有効な選択肢です 。
デメリット2:成果がすぐに見えにくい
note採用広報は、すぐに採用数に直結するような即効性のある施策ではありません。企業のブランディングやファン作りと同様に、長期的な視点でコツコツとコンテンツを積み重ねていく必要があります。そのため、短期的な成果を求められると、途中で挫折してしまう可能性があります。
【対策】
長期的な視点を持つ:最低でも半年から1年は継続する覚悟で臨みましょう。
KPIを適切に設定する:応募数だけでなく、記事のPV数、読了率、スキの数、SNSでのシェア数など、中間的な指標(KPI)を設定し、活動の進捗を可視化します。
社内の理解を得る:経営層や関連部署に、note採用広報の目的と長期的な視点の重要性を事前に説明し、理解を得ておくことが成功の鍵となります。
【事例で学ぶ】note採用広報・成功企業5社の戦略
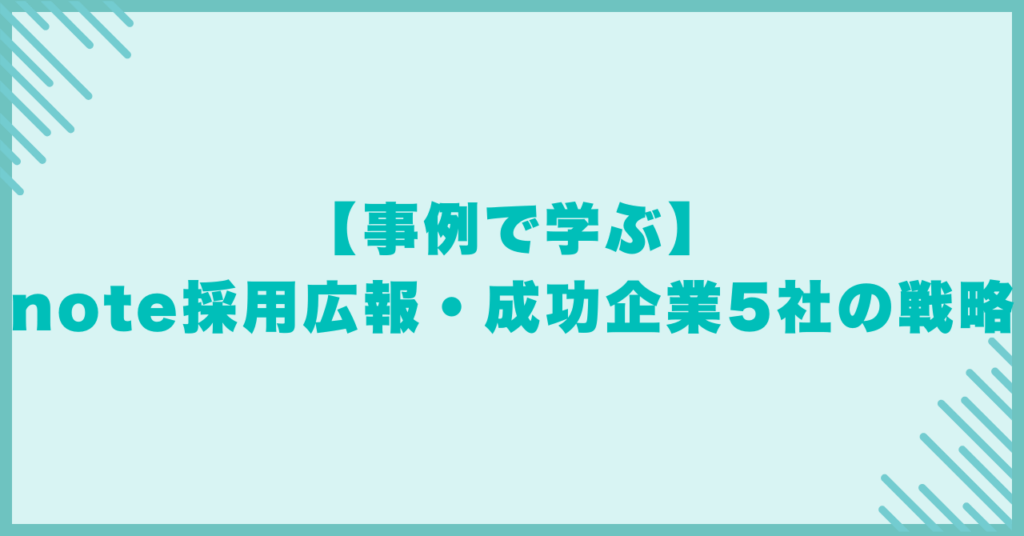
note採用広報を成功させている企業は、どのような戦略を描き、コンテンツを発信しているのでしょうか。ここでは、特徴的な取り組みで成果を上げている5社の事例を分析し、その成功の秘訣を探ります。
キリンビール:従業員の「想い」を伝えて潜在層にアプローチ
大手飲料メーカーのキリンビール株式会社は、従業員一人ひとりの「想い」や「価値観」に焦点を当てたコンテンツで、多くの読者の共感を呼んでいます。「仕事で大事にしている価値観」や「自分らしい仕事の作り方」といったテーマは、求職者が自身のキャリアを考える上で示唆に富んでおり、採用という枠を超えて多くの読者を惹きつけています。
また、商品開発の裏側やお客様とのエピソードを織り交ぜることで、企業の誠実な姿勢や社会との関わりを伝えています。これにより、直接的な求職者だけでなく、将来的に転職を考える可能性のある潜在層に対しても、ポジティブな企業イメージを醸成することに成功しています [2]。
カルビー:商品への「こだわり」を発信し、ステークホルダーを魅了
大手菓子メーカーのカルビー株式会社は、特に新卒採用を意識し、「カルビーで働くこと」を具体的にイメージさせるコンテンツを連載しています。特徴的なのは、商品づくりの現場を支えるプロフェッショナルや、プレスリリースだけでは伝えきれない商品への熱い「こだわり」にスポットを当てている点です。
これにより、単なる食品メーカーというだけでなく、「食」を通じて社会に価値を提供しようとする企業の情熱が伝わってきます。その結果、求職者はもちろん、株主や顧客といった、あらゆるステークホルダーに対して企業の魅力を効果的にアピールできています。
シチズン時計:「新卒向け」に特化し、求人サイトと差別化
精密・電子機器メーカーのシチズン時計株式会社は、ターゲットを「新卒」に明確に定め、情報発信を行っています。企業の誕生秘話や技術的な強みといった硬派な内容から、教育制度や福利厚生、さらには社員食堂のランチメニューといった、学生がリアルな会社生活を想像できるような柔らかい情報まで、幅広く網羅しています。
特に、実際の研修風景などを写真付きで紹介することで、求人サイトの画一的な情報とは一線を画す、独自のコンテンツを提供。他の採用メディアとの明確な差別化を図り、自社に興味を持つ学生を効果的に惹きつけています。
株式会社ベーシック:「リアルな企業文化」を伝えるため全社を巻き込む
BtoBマーケティング支援を行う株式会社ベーシックは、人事部だけでなく、様々な部署の社員がクリエイターとして情報発信に参加する「全社一丸」の運用スタイルが特徴です。エンジニア、デザイナー、営業など、多様な職種の社員がそれぞれの視点から会社の日常や仕事のやりがいを語ることで、多角的で「リアルな企業文化」が浮かび上がります。
AI研究開発の裏側や、顧客への提案内容といった専門的な情報から、就職活動の軸を整理するノウハウまで、コンテンツは多岐にわたります。これにより、求職者と採用担当者の両方にとって価値のある情報を提供し、魅力的なアカウントを構築しています。
MNTSQ株式会社:「専門性」と「人」を掛け合わせ、入社後の活躍をイメージさせる
契約業務のDXを支援するSaaS企業、MNTSQ(モンテスキュー)株式会社は、自社の強みである「AI」や「DX」といった専門領域に関する情報を積極的に発信しています。これにより、同分野に興味を持つ優秀な人材に対して、企業の技術力を強くアピールしています。
さらに、実際に活躍している社員のインタビュー記事を豊富に掲載。「どのような専門性を持つ人材が、どのようにチームに貢献し、成長しているのか」を具体的に示すことで、求職者が入社後の自身の姿を明確にイメージできるように工夫されています。専門性と人の魅力を掛け合わせることで、採用ブランディングを成功させている好例です。
成功事例から学ぶ共通点
これら5社の事例から、note採用広報を成功に導くためのいくつかの共通点が見えてきます。
| 共通点 | 具体的なアクション | 目的・効果 |
| ターゲットの明確化 | 新卒、専門職など、誰に届けたいかを具体的に設定する。 | コンテンツの方向性が定まり、メッセージが響きやすくなる。 |
| 独自性の発信 | 他のメディアでは伝えきれない、自社ならではの情報を発信する。 | 競合他社との差別化を図り、企業の魅力を際立たせる。 |
| 「人」にフォーカス | 経営者や社員の想い、価値観、働き方に焦点を当てる。 | 共感を呼び、企業文化への理解を深める。 |
| リアルな情報提供 | 成功体験だけでなく、日々の業務や時には苦労話も交える。 | 信頼感を醸成し、入社後のミスマッチを防ぐ。 |
| 継続的な発信 | 定期的にコンテンツを更新し、読者との接点を持ち続ける。 | 企業のファンを育成し、潜在層へのアプローチを強化する。 |
これらのポイントを意識することが、単なる情報発信に留まらない、戦略的なnote採用広報への第一歩と言えるでしょう。
【実践編】明日から始める!note採用広報5つのステップ
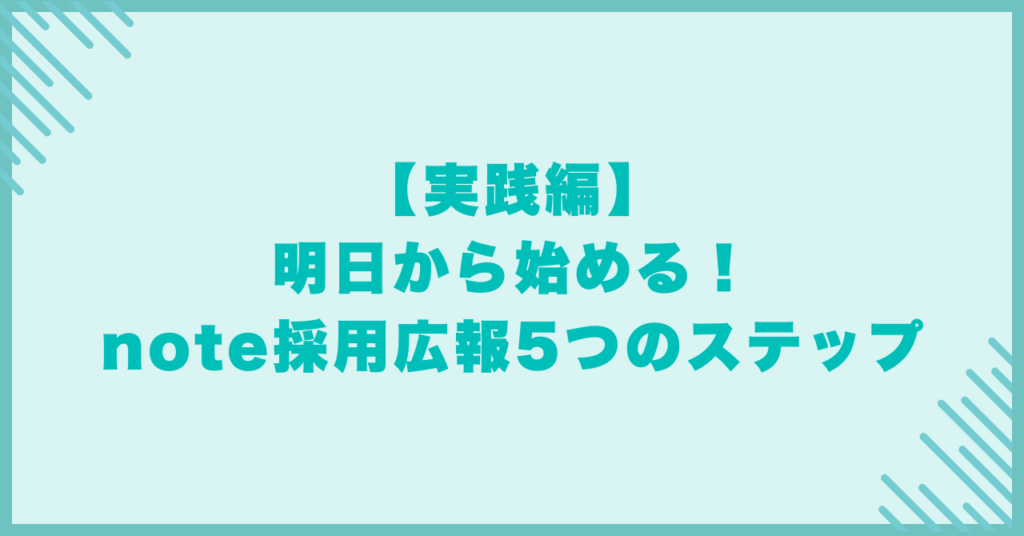
ここからは、実際にnote採用広報を始めるための具体的な5つのステップを解説します。このステップに沿って進めることで、戦略的かつ効果的な運用が可能になります。
STEP1: 目的とターゲット(ペルソナ)を明確にする
何よりもまず、「何のためにnoteをやるのか」「誰に届けたいのか」を明確にすることがスタート地点です。ここが曖昧なままでは、コンテンツの方向性がぶれてしまい、誰にも響かない情報発信になってしまいます。
1. 目的(KGI)の設定
最終的に達成したい目標(KGI: Key Goal Indicator)を設定します。採用広報におけるKGIは、単に「採用成功」とするだけでなく、より具体的に設定することが重要です。
KGIの設定例
•2026年度の新卒採用において、エンジニア職の応募者のうち30%をnote経由にする。
•半年以内に、採用ミスマッチによる早期離職率を10%改善する。
•採用ブランディングを強化し、指名応募(「貴社で働きたい」という応募)の割合を前年比20%増加させる。
2. ターゲット(ペルソナ)の設定
次に、KGIを達成するために、どのような人材に情報を届けたいのか、具体的な人物像(ペルソナ)を描きます。ペルソナを詳細に設定することで、その人物が「何に悩み、何を求めているのか」「どのような情報に興味を持つのか」が明確になり、コンテンツの企画が立てやすくなります。
ペルソナ設定の項目例
基本情報:年齢、性別、居住地、最終学歴
現在の状況:現在の職種、役職、企業規模、年収
価値観・志向:仕事に求めること、キャリアプラン、情報収集の方法
課題・悩み:現在の仕事やキャリアに対する不満、転職を考えるきっかけ
STEP2: 自社の魅力を棚卸しする
ターゲットに何を伝えるべきか、コンテンツの「素材」となる自社の魅力を洗い出します。この時、自社にとっては「当たり前」のことも、他社から見れば大きな魅力である可能性があります。様々な角度から、客観的に自社を見つめ直すことが重要です。
魅力の洗い出しと整理
以下の4つのPの観点から、自社の魅力を整理してみましょう。
| 観点 | 内容 | 具体例 |
| Philosophy(理念・目的) | 企業のビジョン、ミッション、バリュー、存在意義 | 「テクノロジーで世界をより良くする」という創業以来の理念 |
| Profession(仕事・事業) | 事業内容、仕事のやりがい、社会貢献性、成長性 | 急成長中のSaaS市場で、業界トップシェアを誇るプロダクト |
| People(人・文化) | 社員の人柄、チームワーク、社風、多様性 | 経歴多様なメンバーが、互いを尊重し合うフラットな組織文化 |
| Privilege(特権・待遇) | 制度、福利厚生、働き方、給与、キャリアパス | フルリモート・フルフレックス、書籍購入補助、資格取得支援制度 |
これらの要素を具体的なエピソードや客観的なデータと共にリストアップし、コンテンツの素材としてストックしておきましょう。
STEP3: コンテンツ戦略とKPIを設定する
目的、ターゲット、そして自社の魅力が明確になったら、それらをどのようにコンテンツに落とし込み、届けていくかの戦略を立てます。行き当たりばったりの運用ではなく、計画的に進めることが継続の鍵です。
1. コンテンツカレンダーの作成
「いつ」「誰が」「どのようなテーマで」記事を公開するのかを計画するコンテンツカレンダーを作成します。これにより、計画的な運用が可能になり、ネタ切れを防ぐことができます。
コンテンツカレンダーの項目例
・公開予定日
・記事タイトル(仮)
・担当者(企画・執筆・編集)
・ターゲットペルソナ
・伝えたい魅力(4つのP)
・想定キーワード(SEO対策)
・進捗状況
2. 中間目標(KPI)の設定
最終目標であるKGIに対して、その達成度を測るための中間指標(KPI: Key Performance Indicator)を設定します。KPIを定期的に観測することで、施策が順調に進んでいるか、改善すべき点はどこかを判断することができます。
KPIの例
認知度:記事のPV(ページビュー)数、UU(ユニークユーザー)数、SNSでのインプレッション数
興味・関心:記事の読了率、スキの数、コメント数、SNSでのエンゲージメント率
行動:採用サイトへの遷移数、カジュアル面談への応募数、note経由の応募数
STEP4: 心を動かす記事を作成・投稿する
いよいよ記事の作成です。ターゲットの心に響き、行動を促すような記事を作成するためのポイントをいくつか紹介します。
読まれる記事のポイント
タイトルで惹きつける
ターゲットが思わずクリックしたくなるような、具体的で魅力的なタイトルをつけましょう。
冒頭で心を掴む
読者が「自分ごと」として捉えられるような問いかけや、結論を先に示すことで、続きを読む動機を与えます。
ストーリーを語る
単なる事実の羅列ではなく、背景にある想いや苦労、成功体験などを交え、物語として語りましょう。
読みやすい構成
見出し(H2, H3)を適切に使い、段落を短く区切ることで、スマートフォンでも読みやすい文章を心がけます。
視覚的要素を活用する
写真や図表、動画などを効果的に挿入し、読者の理解を助け、飽きさせない工夫をしましょう。
CTAを設置する
記事の最後には、読者に次にとってほしい行動(Call To Action)を明確に示します。採用サイトへのリンクや、カジュアル面談の案内などを忘れずに設置しましょう [3]。
STEP5: 効果測定と改善を繰り返す
noteは公開して終わりではありません。定期的に成果を振り返り、改善を続けるPDCAサイクルを回すことが最も重要です。
1. 効果測定
STEP3で設定したKPIを基に、データを分析します。法人向けの有料プラン「note pro」を利用すれば、記事ごとの詳細なアナリティクス(PV数、読了率、流入経路など)を確認することができます。
・どの記事がよく読まれているか?
・読者はどこから来ているのか?(SNS、検索エンジンなど)
・どの記事が採用サイトへの遷移に繋がっているか?
これらのデータを分析し、成功・失敗の要因を仮説立てします。
2. 改善
分析結果と仮説に基づき、次回のコンテンツ企画や記事の書き方を改善します。例えば、「社員インタビュー記事の読了率が高い」のであれば、同様の企画を増やす。「特定のキーワードでの検索流入が多い」のであれば、そのキーワードを意識した記事を作成する、といった具合です。
このPDCAサイクルを粘り強く回し続けることで、note採用広報は着実に成果へと繋がっていきます。
まとめ
本記事では、noteを活用した採用広報のメリット・デメリットから、具体的な成功事例、そして実践的なステップまでを解説してきました。
note採用広報は、単なる流行りの手法ではありません。企業の「物語」を通じて、求職者との間に深い共感と信頼を築き、ミスマッチのない採用を実現するための、極めて戦略的なアプローチです。それは、短期的な応募者数を増やすための「コスト」ではなく、企業の未来を共に創る仲間と出会うための「投資」と言えるでしょう。
運用にはリソースが必要であり、成果が出るまでには時間がかかります。しかし、Helpfeel社や多くの成功企業が証明しているように、粘り強くPDCAを回し続けることで、採用活動に大きな変革をもたらすポテンシャルを秘めています。
この記事を参考に、まずは自社の魅力を洗い出し、小さな一歩から始めてみてはいかがでしょうか。あなたの会社の物語が、未来の優秀な仲間を惹きつける、最高の採用ツールになるはずです。
「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe
Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界1300名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス
⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス
⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス
などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。
