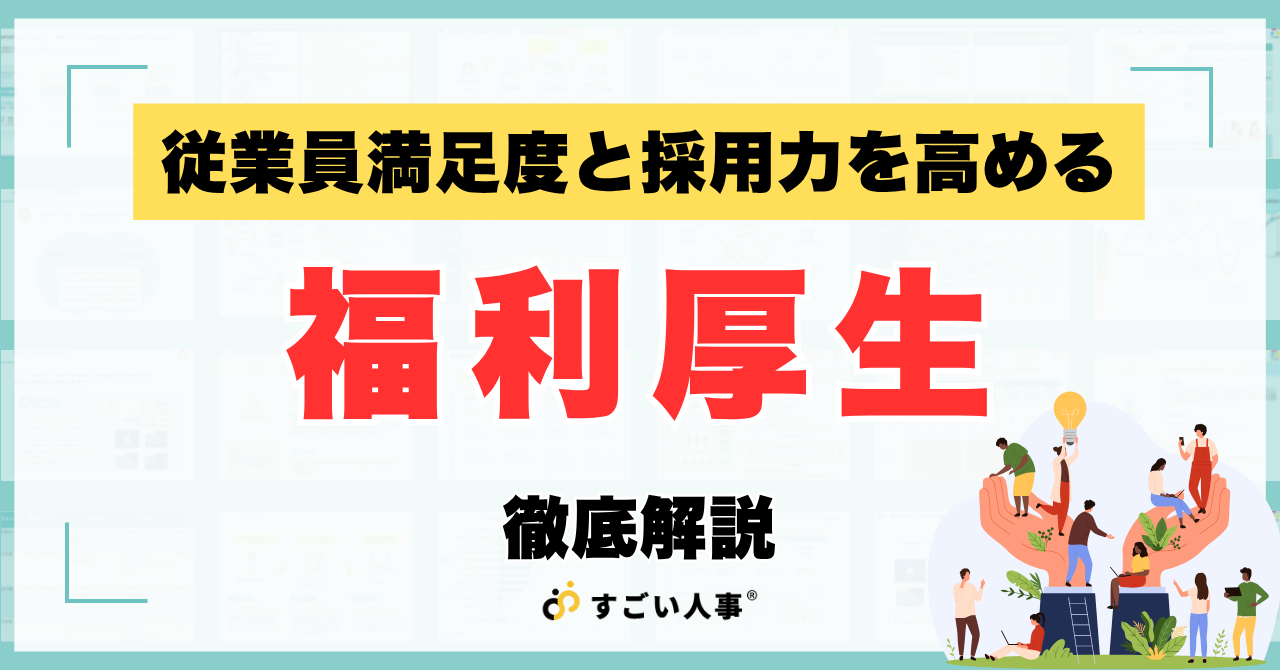
福利厚生で採用力が変わる!大企業の事例から学ぶ制度設計と組織改革の進め方
現代のビジネス環境は、働き方の多様化と、それに伴う人材獲得競争の激化という大きな変化の渦中にあります。特に、優秀な人材を確保し、その定着を図ることは、企業が持続的に成長するための最重要課題の一つと言えるでしょう。このような状況下で、従業員のエンゲージメント、すなわち「企業への貢献意欲」を高める施策として、福利厚生の重要性が再認識されています。
かつての福利厚生は、給与以外の報酬という側面が強いものでした。しかし現在では、従業員の働きがいや生活の質(QOL)を向上させ、企業理念やビジョンを体現するための戦略的なツールとして位置づけられています。魅力的な福利厚生は、従業員の満足度を高めるだけでなく、企業のブランドイメージを向上させ、採用市場における競争優位性を確立する上でも不可欠です。
本記事では、人事・経営者の皆様を対象に、大企業で導入されている福利厚生の最新トレンドや具体的な事例を詳しく解説します。さらに、福利厚生を導入・見直しする際のメリットや注意点を整理し、単なる制度導入に留まらない、戦略的な組織改革へと繋げるためのヒントを提供します。自社の組織改革を検討するきっかけとして、ぜひご一読ください。
目次
- 大企業で導入されている人気の福利厚生一覧
- 【事例紹介】先進的な福利厚生を導入する大企業
- 福利厚生を充実させるメリットと導入のポイント
- 福利厚生は組織改革の第一歩。しかし、制度だけでは不十分
- 貴社の組織改革を加速させる「すごい人事コンサルティング」
- まとめ
大企業で導入されている人気の福利厚生一覧
福利厚生には、法律で義務付けられている「法定福利厚生」(健康保険、厚生年金保険など)と、企業が任意で設ける「法定外福利厚生」の2種類があります。従業員の満足度やエンゲージメントに大きく影響し、企業の個性を打ち出すことができるのは、後者の法定外福利厚生です。
ここでは、多くの大企業で導入され、従業員からの人気も高い福利厚生を「定番」と「トレンド」に分けてご紹介します。
定番で人気の福利厚生
長年にわたり多くの企業で提供され、従業員の生活を支える基盤として定着している福利厚生です。
| 種類 | 内容 | 具体例 |
| 住宅手当・家賃補助 | 従業員の住居に関する費用を補助する制度。生活コストの大きな部分を占める家賃負担を軽減することで、従業員の経済的な安定に貢献します。 | 家賃の一部補助、社宅・寮の提供、住宅ローン補助など |
| 食事補助 | 従業員の食事にかかる費用を補助する制度。健康的な食生活をサポートし、従業員の健康維持・増進を図ります。 | 社員食堂の運営、食事券やチケットの配布、オフィスへの弁当配達サービスなど |
| 健康支援 | 従業員の心身の健康を維持・増進するための制度。健康経営の観点からも重要視されています。 | 人間ドック・健康診断の費用補助、フィットネスクラブの利用割引、ストレスチェック、産業医による面談など |
| 育児・介護支援 | 仕事と育児・介護の両立を支援する制度。多様なライフステージにある従業員が安心して働き続けられる環境を整備します。 | 育児・介護休業の延長、時短勤務制度、社内託児所の設置、ベビーシッター利用補助など |
| 特別休暇 | 法律で定められた休暇以外に、企業が独自に設ける休暇制度。従業員のリフレッシュや自己実現を促進します。 | リフレッシュ休暇、アニバーサリー休暇、ボランティア休暇、自己啓発休暇など |
| 財産形成支援 | 従業員の長期的な資産形成をサポートする制度。将来への経済的な不安を軽減し、安心して働ける環境を提供します。 | 財形貯蓄制度、従業員持株会、確定拠出年金(DC)のマッチング拠出など |
近年のトレンドを反映した福利厚生
働き方の多様化や価値観の変化に対応し、近年注目を集めている福利厚生です。
| 種類 | 内容 | 具体例 |
| 多様な働き方支援 | 時間や場所にとらわれない柔軟な働き方を可能にする制度。ワークライフバランスの実現に直結します。 | リモートワーク制度、フレックスタイム制度、ワーケーション制度、時短勤務制度など |
| 自己啓発・スキルアップ支援 | 従業員の学びや成長を後押しする制度。個人のキャリア開発を支援し、組織全体の能力向上に繋げます。 | 資格取得費用の補助、外部研修・セミナーへの参加費補助、書籍購入費補助、e-ラーニングの提供など |
| ウェルビーイング向上支援 | 従業員の身体的、精神的、社会的に良好な状態(ウェルビーイング)を支援する制度。より広範な視点から従業員の幸福を追求します。 | メンタルヘルスケア(カウンセリングサービス)、マインドフルネス研修、社内コミュニケーション活性化施策(部活動支援など) |
【事例紹介】先進的な福利厚生を導入する大企業
ここでは、独自のユニークな福利厚生を導入し、従業員のエンゲージメント向上や企業文化の醸成に成功している大企業の事例をご紹介します。
ソニー株式会社:個人の成長を支える制度
ソニーは、社員一人ひとりの成長意欲に応え、キャリアの可能性を広げるための制度を充実させています 1。
公募留学制度 会社から社費で留学派遣する候補者を年に一度公募。行き先・テーマ・留学後のプランを考え、上司の推薦を得て自ら手を挙げる仕組み。海外大学の研究室を中心に1年間、最先端技術・知識に触れ、高い専門性と人間力に磨きをかけるチャレンジ。ソニーは早くから留学生派遣を始めており、これまでに400名以上の社員が留学している。
フレキシブルキャリア休職制度 ソニーでのキャリア展開を豊かにするため、配偶者の海外赴任や留学への同行で知見や語学・コミュニケーション能力の向上により、キャリアの継続を図る休職 (最長5年) や、ご自身の専門性を深化・拡大させるための私費就学のための休職 (最長2年) ができるようになっている。
これらの制度は、会社が社員の長期的なキャリア形成を支援し、挑戦を奨励する文化の表れと言えるでしょう。
サイボウズ株式会社:多様な働き方を実現する制度
「100人100通りの働き方」を掲げるサイボウズは、社員が自身のライフスタイルに合わせて働き方を選択できる制度を導入しています。
•選べる働き方: 「ライフ重視型」「ワーク重視型」「ワークライフバランス型」など、個人の希望に応じて働き方のスタイルを選択・変更できます。結婚や出産、介護といったライフイベントにも柔軟に対応可能です。
•ウルトラワーク: 時間や場所の制約なく、会社に出社しなくても自宅やカフェなどで作業できる制度。生産性を最大限に高めるための働き方を社員自らがデザインできます。
株式会社サイバーエージェント:女性活躍を推進する制度
サイバーエージェントでは、女性社員が長期的に活躍できる環境を整備するため、「macalon(マカロン)パッケージ」という独自の制度を設けています。
「ママ(mama)がサイバーエージェント(CA)で長く(long)働く」という意味を込めて 「macalon(マカロン)パッケージ」と名付けられたとのこと。 女性特有の体調不良の際に、月1回休暇を取得できる「エフ休」・子どもの急な発熱など看護が必要な場合に在宅勤務できる「キッズ在宅」・妊活に興味がある社員や不妊治療中の社員向けの「妊活コンシェル」「妊活休暇」など、充実した内容の制度で、女性社員が十分に力を発揮できるようにこの社内制度が強力にサポート。
その他ユニークな事例
ロート製薬株式会社:「社外チャレンジワーク」
本業に支障のない範囲で兼業を認め、社員が社外で新たなスキルや知見を得ることを奨励しています。
大和ハウス工業株式会社:「親孝行支援制度」
両親が要介護認定されている場合に、帰省費用を補助する制度。社員の介護と仕事の両立を支援します。
これらの事例から、福利厚生が単なるコストではなく、企業の価値観を伝え、組織文化を形成するための重要な投資であることがわかります。
福利厚生の人気ランキング(従業員視点)
従業員が実際に求めている福利厚生を理解することは、効果的な制度設計の第一歩です。Wantedlyの調査によると、従業員に人気の福利厚生は以下のようにランキングされています。
| 順位 | 福利厚生 | 人気の理由 |
| 1位 | 特別休暇 | ワークライフバランスの実現に直結し、リフレッシュや自己実現の機会を提供するため |
| 2位 | 住宅支援制度 | 生活費の大きな部分を占める住居費の負担軽減は、経済的な安心感に直結するため |
| 3位 | 健康管理制度 | 自身の健康への関心の高まりと、将来への不安を軽減する効果があるため |
| 4位 | 慶弔見舞制度 | ライフイベントにおける企業からのサポートは、帰属意識を高める効果があるため |
| 5位 | 家族支援制度 | 家族との時間を大切にしたいという価値観の広がりを反映しているため |
このランキングから見えてくるのは、従業員が「金銭的な支援」と「時間的な余裕」の両方を求めているという事実です。単に給与を上げるだけでなく、生活の質を総合的に向上させる施策が求められています。
福利厚生を充実させるメリットと導入のポイント
魅力的な福利厚生制度は、企業に多くのメリットをもたらします。しかし、その効果を最大化するためには、いくつかの注意点を押さえておく必要があります。
企業側が得られる5つのメリット
1.採用力の強化
魅力的な福利厚生は、求職者に対する強力なアピールポイントとなり、優秀な人材の獲得に繋がります。
2.従業員満足度と定着率の向上
働きやすい環境は従業員の満足度を高め、エンゲージメントを向上させます。結果として、離職率の低下が期待できます。
3.生産性の向上
ワークライフバランスの実現や健康増進支援は、従業員の心身のコンディションを整え、業務への集中力を高めることで生産性向上に寄与します。
4.企業のブランドイメージ向上
「従業員を大切にする企業」という社会的評価は、企業の信頼性を高め、ブランドイメージの向上に貢献します。
5.節税効果
一定の要件を満たす福利厚生費は、法人税法上の損金として算入できるため、節税効果が期待できます。
導入・見直しを成功させるための3つの注意点
1.コストと管理負担の把握
新たな制度の導入には、当然ながらコストがかかります。また、申請受付や管理といった運用面の負担も考慮し、持続可能な制度設計を心掛ける必要があります。
2.従業員ニーズの的確な把握
従業員の年齢構成やライフスタイルによって、求められる福利厚生は異なります。アンケート調査などを実施し、従業員の真のニーズを把握することが、利用率の高い制度を作るための鍵となります。
3.公平性と利用しやすさの担保
一部の従業員しか利用できない制度は、かえって不公平感を生む可能性があります。全従業員が公平に利用できる機会を提供し、制度の利用方法を分かりやすく周知することが重要です。
福利厚生の導入プロセス
福利厚生を効果的に導入するためには、計画的なプロセスを踏むことが重要です。以下のステップを参考に、自社に最適な制度を構築しましょう。
ステップ1:現状分析と課題の明確化
まず、自社の現状を客観的に把握することから始めます。既存の福利厚生の利用状況を分析し、従業員からのフィードバックを収集します。離職率や採用における課題、従業員エンゲージメントのスコアなども参考にしながら、何が問題なのかを明確にします。
ステップ2:従業員ニーズの調査
アンケートやヒアリングを通じて、従業員が本当に求めている福利厚生を把握します。年齢層、家族構成、ライフステージなど、従業員の属性によってニーズは大きく異なるため、できるだけ多様な声を集めることが重要です。
ステップ3:予算の設定と優先順位の決定
福利厚生にかけられる予算を明確にし、調査結果をもとに導入する制度の優先順位を決定します。すべてのニーズに応えることは現実的ではないため、費用対効果や企業の戦略との整合性を考慮しながら、実現可能な範囲で最大の効果を狙います。
ステップ4:制度設計と運用ルールの策定
具体的な制度の内容を設計し、利用条件や申請方法、管理体制などの運用ルールを明確にします。この段階で、法的な要件を満たしているか、税務上の問題はないかなども確認しておく必要があります。
ステップ5:周知と浸透
制度を導入しても、従業員に知られていなければ意味がありません。社内報やイントラネット、説明会などを活用して、新しい制度の内容や利用方法を丁寧に周知します。また、利用を促進するための工夫(申請手続きの簡素化、上司からの推奨など)も重要です。
ステップ6:効果測定と改善
制度導入後は、定期的に利用状況や従業員の満足度を測定し、効果を検証します。期待した効果が得られていない場合は、原因を分析し、制度の見直しや改善を行います。福利厚生は一度導入したら終わりではなく、継続的に改善していくものです。
福利厚生は組織改革の第一歩。しかし、制度だけでは不十分
ここまで見てきたように、福利厚生の充実は、従業員エンゲージメントの向上や人材の定着に大きな効果を発揮します。それは間違いなく、ポジティブな組織改革への重要な第一歩です。
しかし、注意しなければならないのは、制度を導入しただけで組織が自動的に変わるわけではないということです。どんなに素晴らしい制度も、従業員に利用されなければ意味がありません。「制度はあるが、忙しくて使えない」「上司や同僚の目が気になって申請しづらい」といった状況では、福利厚生は「絵に描いた餅」となり、形骸化してしまいます。
福利厚生を真に機能させるためには、制度設計と同時に、それを利用しやすい組織風土を醸成することが不可欠です。休暇を取得すること、個々の事情に合わせて柔軟な働き方を選択することが、当たり前の文化として根付いていなければなりません。
そして、そのためには、福利厚生制度が経営戦略や人事戦略全体の中に明確に位置づけられている必要があります。「なぜこの制度を導入するのか」「それによってどのような組織を目指すのか」という目的が全社で共有されていて初めて、福利厚生は組織変革の強力なエンジンとなるのです。
福利厚生と企業文化の関係性
福利厚生は、企業文化を形成し、強化する重要な役割を担っています。例えば、サイボウズの「選べる働き方」は、個人の多様性を尊重する企業文化を体現しています。ロート製薬の「社外チャレンジワーク」は、社員の挑戦を応援し、成長を促す文化を象徴しています。
このように、福利厚生は単なる「制度」ではなく、「企業が何を大切にしているか」を従業員や社会に伝えるメッセージでもあります。だからこそ、自社の理念やビジョンと整合性のとれた福利厚生を設計することが、組織の一体感を高め、強い企業文化を築くことに繋がるのです。
逆に言えば、企業文化と乖離した福利厚生は、従業員に混乱を招き、かえって組織の求心力を弱める可能性があります。福利厚生の見直しは、自社の企業文化を見つめ直す絶好の機会でもあるのです。
貴社の組織改革を加速させる「すごい人事コンサルティング」
福利厚生の見直しをきっかけに、より本質的な組織改革へと踏み出したい。そうお考えの経営者・人事担当者の方も多いのではないでしょうか。
こんな課題はありませんか?
•「福利厚生を見直したいが、何から手をつければいいかわからない」
•「制度は導入したが、従業員に利用されず形骸化している」
•「採用競争が激化し、優秀な人材を確保できない」
•「中期的な経営計画と連動した人事戦略を描けていない」
これらの課題は、多くの企業が直面する根深い問題です。そして、その解決には、人事領域における高度な専門知識と豊富な経験が求められます。
「すごい人事コンサルティング」が提供するソリューション
私たち「すごい人事コンサルティング」は、採用課題から人事組織・制度設計、人材育成、組織成長まで、人事に関するあらゆる課題を解決する戦略的パートナーです 3。
急成長ベンチャーから大手企業まで、200社以上の支援実績とリピート率98%という高い評価が、私たちのサービスの質を証明しています。私たちは、単に制度のテンプレートを提供するのではありません。各企業の成長フェーズや経営課題に深く寄り添い、組織図の作成からMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)の策定、そしてそれに基づいた人事制度の設計・運用まで、一気通貫で伴走支援します。
福利厚生の見直しは、貴社の組織が抱える課題を可視化し、理想の組織へと変革していく絶好の機会です。
まずは無料相談から
「何から相談すればいいかわからない」という方も、ご安心ください。まずは貴社の現状やお悩みをお聞かせいただくことから始めます。経験豊富なコンサルタントが、貴社の組織改革の第一歩をサポートします。
まとめ
本記事では、大企業の福利厚生制度に焦点を当て、その種類や具体的な事例、導入のメリット・注意点について解説しました。現代において、福利厚生は単なるコストではなく、企業の成長を支える重要な戦略的投資です。
魅力的な福利厚生は、採用力の強化や従業員エンゲージメントの向上に繋がり、ひいては企業全体の生産性を高めます。しかし、その効果を最大限に引き出すためには、制度の導入と並行して、それを利用しやすい組織風土を醸成し、経営戦略と連動した人事戦略を構築することが不可欠です。
この記事が、皆様の会社における福利厚生制度を見直し、より良い組織づくりへの一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。
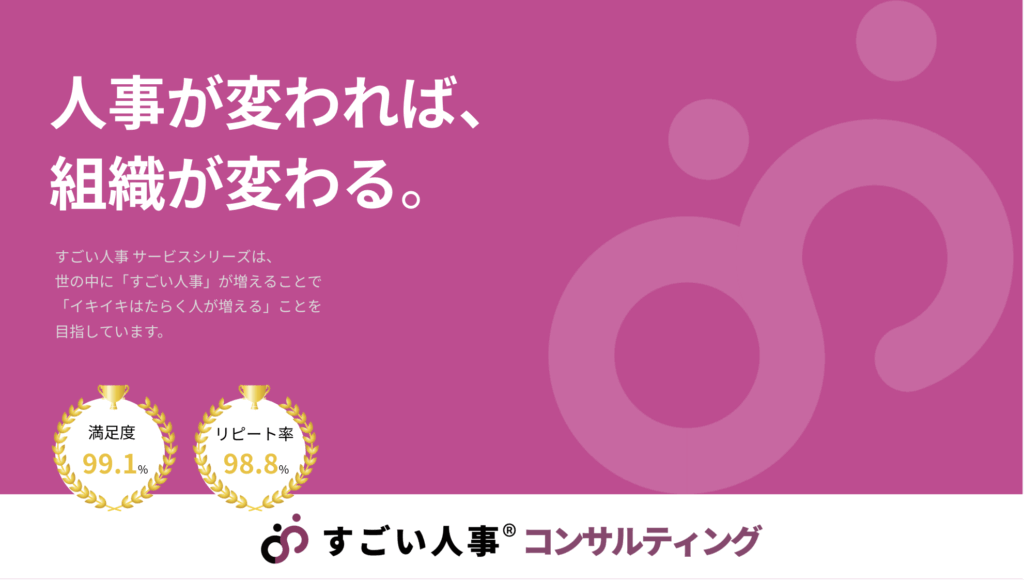
「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe
Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界1300名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス
⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス
⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス
などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。
