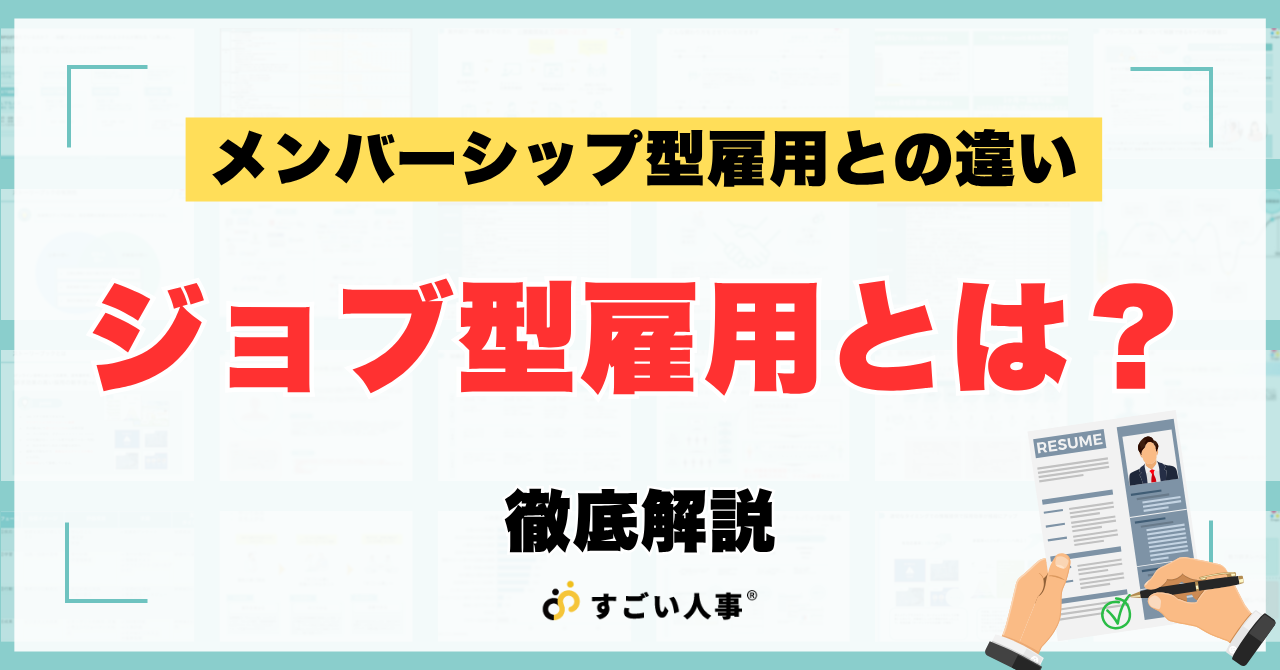
ジョブ型雇用とは?メンバーシップ型との違いを徹底解説
近年、働き方の多様化や専門性の高い人材獲得の必要性から、「ジョブ型雇用」という言葉を耳にする機会が増えました。従来の日本企業で主流であった「メンバーシップ型雇用」とは異なるこの雇用形態は、企業と従業員の双方にとって大きな変化をもたらす可能性を秘めています。本記事では、ジョブ型雇用の基本的な概念から、メンバーシップ型雇用との違い、注目される背景、そして企業側・従業員側それぞれのメリット・デメリット、さらには導入手順に至るまで、専門的な知見を交えつつ、分かりやすく解説していきます。人事責任者や経営者の方々が、自社の人事戦略を検討する上での一助となれば幸いです。
目次
ジョブ型雇用とは?
ジョブ型雇用とは、企業が必要とする職務(ジョブ)を明確に定義し、その職務を遂行できるスキルや経験を持つ人材を採用する雇用形態を指します。具体的には、職務記述書(ジョブディスクリプション)によって、担当する業務内容、責任範囲、必要なスキル、経験、資格などが詳細に定められます。この職務記述書に基づいて人材の募集、選考、配置が行われ、報酬もその職務の価値や難易度、市場価値などに応じて決定されるのが一般的です。
ジョブ型雇用の特徴
欧米企業では古くから主流となっている雇用システムであり、専門性の高い人材を確保しやすいという特徴があります。個人のキャリア形成においては、自身の専門性を深め、市場価値を高めていくことが重視されます。企業と個人は、職務を介して対等な関係で結ばれ、双方が選び選ばれるという考え方が根底にあります。 ジョブ型雇用と対比される概念として、日本企業で伝統的に採用されてきた「メンバーシップ型雇用」があります。この二つの雇用形態は、人材に対する考え方や処遇において根本的な違いが存在します。
ジョブ型雇用とメンバーシップ型との違い
メンバーシップ型雇用は、企業がまず人材を「メンバー」として採用し、その後、社内の様々な部署や職務を経験させながら育成していくスタイルです。採用時点では特定の職務を限定せず、個人の適性や企業の状況に応じて柔軟に配置転換が行われます。新卒一括採用や終身雇用、年功序列といった日本的経営の特徴と深く結びついており、「就社」という言葉で表現されることもあります。企業への帰属意識が高まりやすく、ゼネラリスト育成に適しているとされる一方、専門性が育ちにくい、評価基準が曖昧になりやすいといった側面も指摘されています。
両者の主な違いを整理すると、以下のようになります。
| 項目 | ジョブ型雇用 | メンバーシップ型雇用 |
|---|---|---|
| 業務範囲 | 明確(職務記述書で規定) | 総合的かつ流動的 |
| 採用 | 職務に適したスキル・経験を持つ人材を随時採用 | 新卒一括採用が中心、ポテンシャル重視 |
| 配置・異動 | 原則として職務記述書にない異動はなし、公募が基本 | 企業主導による配置転換・異動あり |
| 評価・報酬 | 職務の価値・成果に基づいて決定 | 年齢・勤続年数・能力などを総合的に評価、職能給が中心 |
| 人材育成 | OJT中心、自己研鑽による専門性向上が求められる | 企業主導の研修制度、ジョブローテーションによる育成 |
| キャリア形成 | 個人主導で専門性を追求 | 企業主導で多様な経験を積む |
| 雇用の安定性 | 職務がなくなれば雇用の継続が困難になる可能性あり | 長期雇用が前提とされる傾向が強い |
このように、ジョブ型雇用は「仕事に人を合わせる」考え方であるのに対し、メンバーシップ型雇用は「人に仕事を合わせる」という側面が強いと言えます。どちらの雇用形態が優れているというわけではなく、企業の事業戦略や組織文化、そして時代の変化に応じて、最適な形を模索していくことが重要です。 近年、日本においてもジョブ型雇用への関心が高まり、導入を検討・推進する企業が増加傾向にあります。この背景には、社会経済環境の大きな変化や、企業が直面する新たな課題が複雑に絡み合っています。主な要因として、以下の点が挙げられます。
経団連の提言と政府の方針転換
2018年頃から、経団連の会長(当時)が従来のメンバーシップ型雇用の限界に言及し、ジョブ型雇用への移行の必要性を訴え始めました。これに呼応するように、政府も働き方改革の一環として、専門性を重視した流動性の高い労働市場の実現を目指す方針を示し、「ジョブ型人事指針」を発表するなど、ジョブ型雇用導入を後押しする動きが活発化しています。こうしたトップダウンの動きが、企業の人事戦略に大きな影響を与えています。
デジタルトランスフォーメーション(DX)の進展と専門人材の需要増大
AI、IoT、ビッグデータといったデジタル技術の急速な発展は、あらゆる産業においてビジネスモデルの変革、すなわちDXを不可避なものとしています。DX推進には、データサイエンティスト、AIエンジニア、サイバーセキュリティ専門家など、高度な専門知識やスキルを持つ人材の獲得が不可欠です。しかし、これらの専門人材は国内で不足しており、従来のメンバーシップ型雇用では育成や確保が追いつかないケースが増えています。特定の職務内容と必要なスキルを明確にし、市場から即戦力となる専門人材を迅速に採用できるジョブ型雇用は、この課題への有効な解決策として注目されています。
グローバル化と競争激化
企業のグローバル展開が進む中で、海外の拠点ではジョブ型雇用が一般的であるため、国内外で一貫した人事制度を構築する必要性が高まっています。また、国際競争が激化する中、専門性を武器に高い生産性を発揮できる人材の重要性が増しており、職務ベースで評価・処遇を行うジョブ型雇用が、グローバルスタンダードに合わせた人材マネジメント手法として認識されつつあります。
働き方の多様化と個人のキャリア意識の変化
終身雇用や年功序列といった従来の日本的雇用慣行が揺らぐ中で、個人のキャリアに対する意識も変化しています。自身の専門性を高め、市場価値を意識しながらキャリアを自律的に形成していきたいと考える人が増えています。職務内容が明確で、自身のスキルや経験を活かせるジョブ型雇用は、こうした個人のキャリア志向と合致しやすく、魅力的な働き方として捉えられています。特に、専門性を活かして複数の企業で活躍したいと考える人材や、特定の分野でプロフェッショナルを目指す若手層にとって、ジョブ型雇用はキャリアパスの選択肢を広げるものとなります。
新型コロナウイルス感染症拡大に伴うテレワークの普及
2020年以降の新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、テレワークという働き方を急速に普及させました。オフィスから離れて業務を行う環境では、プロセスよりも成果が重視される傾向が強まります。ジョブ型雇用は、職務内容と期待される成果が明確であるため、テレワーク環境下での業務管理や評価と親和性が高いとされています。時間や場所にとらわれない柔軟な働き方を実現する上で、ジョブ型雇用の考え方が有効であるとの認識が広がりました。
大手企業による導入事例の増加
日立製作所、富士通、KDDI、資生堂といった日本を代表する大手企業が、相次いでジョブ型雇用の導入や拡大を発表したことも、社会的な注目度を高める一因となりました。これらの企業の動向は、他の企業の人事戦略にも影響を与え、ジョブ型雇用への関心を一層高める結果となっています。
これらの背景が複合的に作用し、日本企業におけるジョブ型雇用の導入機運はかつてないほど高まっています。ただし、単に流行として捉えるのではなく、自社の経営戦略や組織文化、従業員の意識などを踏まえ、慎重に検討を進めることが肝要です。 ジョブ型雇用を導入することは、企業にとって多くのメリットをもたらす一方で、いくつかのデメリットや課題も存在します。導入を検討する際には、これらの両側面を十分に理解し、自社の状況と照らし合わせて慎重に判断することが求められます。
企業側のメリット
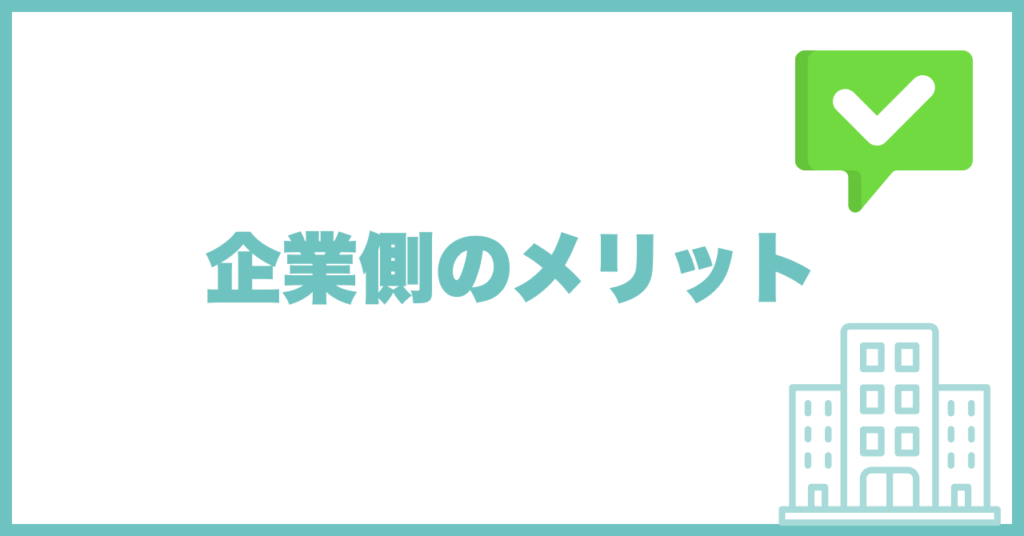
専門性の高い即戦力人材の確保
ジョブ型雇用の最大のメリットの一つは、特定の職務に必要なスキルや経験を持つ人材を、市場から迅速かつ的確に獲得できる点です。職務記述書によって求める人物像が明確になっているため、採用のミスマッチを減らし、事業戦略上不可欠な専門人材を効率的に確保できます。特に、変化の速い現代においては、新規事業の立ち上げやDX推進など、特定の専門知識が急遽必要となる場面で大きな力を発揮します。
職務に応じた公正な評価と処遇の実現
職務内容と責任範囲、期待される成果が明確であるため、従業員の評価を客観的かつ公正に行いやすくなります。成果に基づいて報酬を決定する仕組みを導入しやすく、従業員の納得感を高めることができます。これにより、高いパフォーマンスを発揮した従業員が正当に報われる組織風土を醸成し、モチベーション向上にも繋がります。
生産性の向上
各従業員が自身の専門分野に特化して業務に取り組むため、スキルアップのスピードが速く、業務効率の向上が期待できます。また、職務範囲が明確であるため、従業員は自身の役割に集中しやすく、無駄な業務の削減や意思決定の迅速化にも貢献します。結果として、組織全体の生産性向上に繋がる可能性があります。
人件費の最適化
職務の価値に基づいて報酬が決定されるため、必ずしも年功序列で人件費が上昇し続けるわけではありません。必要な職務に対して適切なコストで人材を確保できるため、人件費の最適化が期待できます。ただし、高度な専門人材に対しては市場価値に見合う高い報酬が必要となる場合もあります。
組織の活性化とイノベーション促進
外部から多様なスキルや経験を持つ人材が流入することで、組織内に新たな視点や知識がもたらされ、イノベーションが促進される可能性があります。また、職務ベースでのキャリアアップを目指す従業員の意欲が刺激され、組織全体の活性化に繋がることも期待できます。
企業側のデメリット
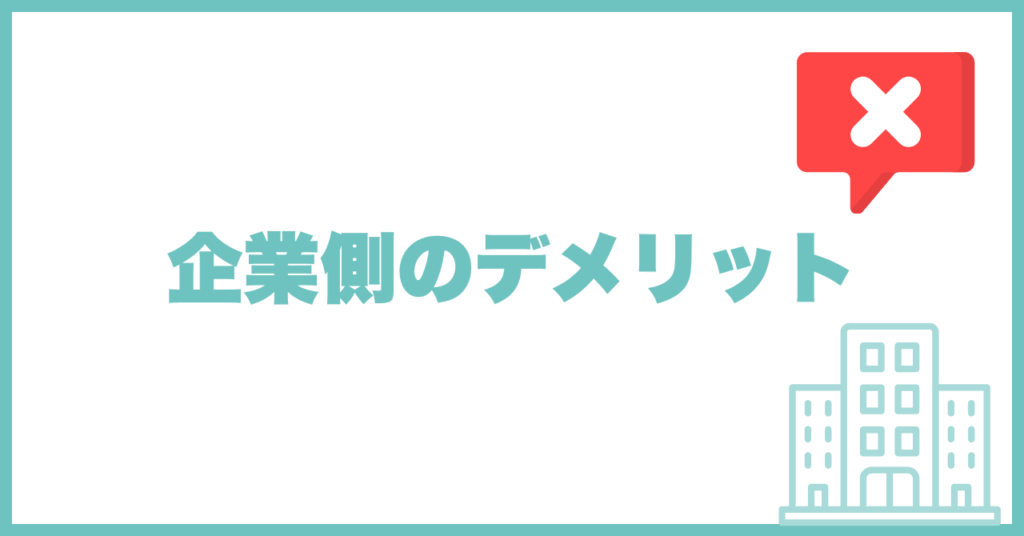
人材の流動性が高まり、流出リスクが増加
ジョブ型雇用では、従業員は特定の職務を遂行するために雇用されるため、より良い条件やキャリアアップの機会を求めて他社へ転職するハードルが低くなる傾向があります。特に優秀な専門人材は常に市場からの引き合いが強く、魅力的な労働条件やキャリアパスを提示できなければ、人材流出のリスクが高まります。リテンション戦略の重要性が増すと言えるでしょう。
ゼネラリストの育成が困難
従業員が特定の専門分野に特化するため、幅広い知識や経験を持つゼネラリストが育ちにくいという側面があります。将来の経営幹部候補など、多角的な視点を持つ人材を育成するためには、ジョブローテーションのような仕組みを別途検討する必要があります。
柔軟な人事異動の制約
職務内容が契約で明確に定められているため、企業側の都合で安易に配置転換や職務変更を行うことが難しくなります。事業環境の変化に迅速に対応するために人員配置を柔軟に変更したい場合でも、従業員の合意なしには進められないケースが多く、組織運営の柔軟性が低下する可能性があります。
職務記述書の作成・維持管理の負担
社内のあらゆる職務について、職務内容、責任範囲、必要なスキルなどを詳細に記述した職務記述書を作成し、常に最新の状態に維持・管理する必要があります。これには多大な時間と労力が必要となり、人事部門の負担が増加します。また、職務評価の基準を策定し、公平性を保つことも重要な課題となります。
既存従業員からの反発や制度移行の困難さ
長年メンバーシップ型雇用に慣れ親しんできた従業員にとって、ジョブ型雇用への移行は大きな変化であり、評価制度やキャリアパスの変更に対して不安や抵抗を感じる可能性があります。丁寧な説明とコミュニケーションを通じて理解を求め、段階的な移行や経過措置を設けるなどの配慮が必要です。
帰属意識の低下の可能性
職務を基盤とした関係性が強まることで、企業全体への帰属意識や一体感が希薄になる可能性があります。企業文化の醸成やチームワークの維持に向けた取り組みが、より一層重要になります。
ジョブ型雇用の導入は、企業にとって大きな変革を伴います。メリットを最大限に活かし、デメリットを最小限に抑えるためには、自社の経営戦略や組織文化、従業員の特性などを総合的に考慮し、周到な準備と丁寧なコミュニケーションを重ねながら進めていくことが不可欠です。 ジョブ型雇用は、企業だけでなく、働く個人にとってもキャリア形成や働き方に大きな影響を与えます。従業員側から見たメリットとデメリットを理解することは、自身のキャリアプランを考える上で非常に重要です。
従業員側のメリット
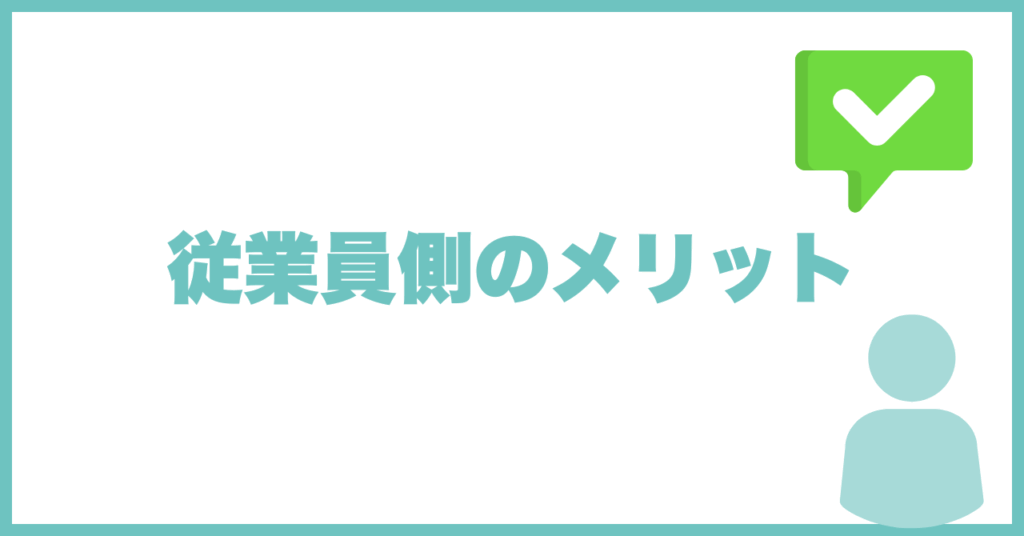
専門性やスキルを活かし、高めやすい
自身の持つ専門知識やスキルを明確に活かせる職務に就くことができるため、仕事への満足感を得やすくなります。また、特定の分野で継続的に業務に取り組むことで、より高度な専門性を追求し、スキルを深めていくことが可能です。これは、自身の市場価値を高める上で大きな利点となります。
職務内容や期待される成果が明確
職務記述書によって、担当する業務の範囲、責任、権限、そして期待される成果が明確に示されます。これにより、「何をすべきか」「何が評価されるのか」が分かりやすくなり、業務に集中しやすくなります。評価基準が明確であるため、自身の貢献が正当に評価されることへの期待も高まります。
主体的なキャリア形成が可能
企業主導の異動や配置転換が少ないため、自身のキャリアパスを主体的に設計しやすくなります。興味のある分野や得意なスキルを軸に、専門性を高めていくキャリアを築くことができます。また、職務経歴が明確になるため、転職を通じてキャリアアップを目指す際にも有利に働くことがあります。
成果に応じた公正な評価と報酬への期待
年齢や勤続年数ではなく、職務の価値や成果に基づいて評価・処遇されるため、若手であっても高い成果を上げれば、それに見合った報酬やポジションを得られる可能性があります。自身の努力や貢献が直接的に評価に結びつくことは、大きなモチベーションとなるでしょう。
ワークライフバランスの実現可能性
職務範囲が明確であるため、時間外労働が発生しにくい、あるいはコントロールしやすい環境が期待できます。自身の専門性を活かして効率的に業務を遂行することで、プライベートの時間を確保しやすくなる可能性があります。ただし、これは職務内容や企業の文化にも左右されます。
従業員側のデメリット
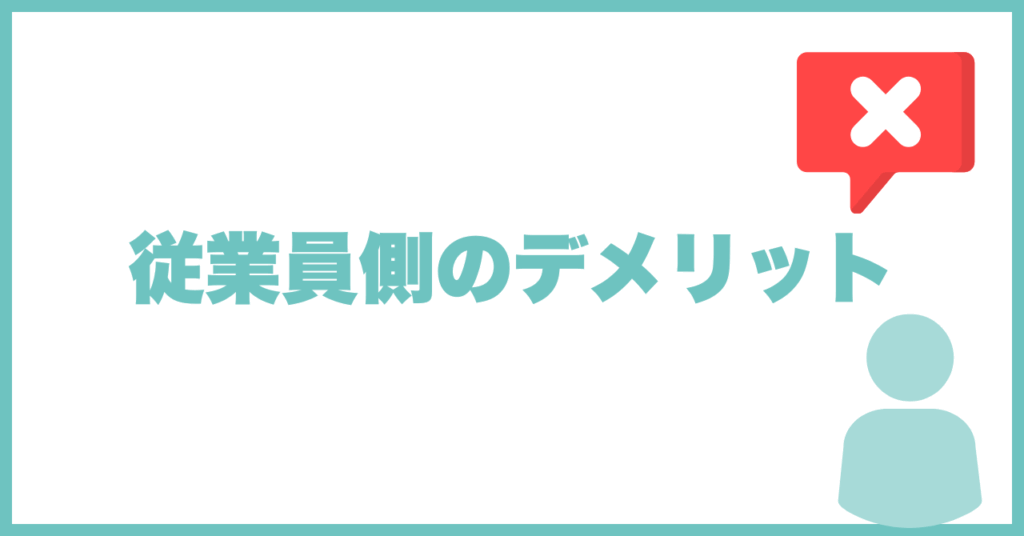
自己研鑽・自学自習の継続的な必要性
専門性を維持・向上させるためには、常に新しい知識や技術を学び続ける自己研鑽が不可欠です。企業が手厚い研修制度を提供してくれるとは限らず、自ら積極的にスキルアップに取り組む姿勢が求められます。これを怠ると、自身の市場価値が低下し、キャリアアップが難しくなる可能性があります。
会社都合でジョブがなくなるリスク
担当していた職務が、企業の事業再編や外部環境の変化などによって廃止された場合、雇用契約が終了したり、別の職務への転換を余儀なくされたりするリスクがあります。メンバーシップ型雇用のような手厚い雇用保障は期待しにくく、常に自身の市場価値を意識し、キャリアの選択肢を複数持っておく必要があります。
ゼネラリストとしてのキャリア形成の難しさ
特定の専門分野に特化する反面、幅広い業務経験を積む機会が減少し、ゼネラリストとしてのキャリアを築きにくくなる可能性があります。将来的にマネジメント層を目指す場合など、多角的な視点や経験が求められる際には、意識的に視野を広げる努力が必要となるかもしれません。
企業文化への適応や人間関係構築の難しさ
職務ベースでの採用となるため、メンバーシップ型雇用のように同期入社や長期間の共働を通じて自然と企業文化に馴染んだり、社内の人間関係を構築したりする機会が少なくなる可能性があります。自ら積極的にコミュニケーションを取り、組織に溶け込む努力が求められる場面もあるでしょう。
雇用の不安定さへの懸念
職務がなくなれば解雇される可能性があるという点は、従業員にとって大きな不安材料となり得ます。特に、景気変動の影響を受けやすい業界や職種の場合、雇用の不安定さを常に意識する必要があるかもしれません。
ジョブ型雇用は、個人の専門性を最大限に活かし、自律的なキャリア形成を促す一方で、常に自己成長を続け、市場の変化に対応していく柔軟性が求められる働き方と言えます。自身のキャリアプランや価値観と照らし合わせ、メリットとデメリットを総合的に理解することが重要です。 ジョブ型雇用を企業に導入する際には、単に制度を変更するだけでなく、組織文化や従業員の意識改革も含めた慎重かつ計画的なアプローチが不可欠です。ここでは、一般的な導入手順と成功させるためのポイントを解説します。
ジョブ型雇用の導入手順
導入目的の明確化と経営層のコミットメント
まず、なぜジョブ型雇用を導入するのか、その目的(例:専門人材の獲得、生産性向上、グローバル競争力の強化など)を明確にし、経営層がその目的達成に向けて強くコミットすることが不可欠です。導入目的が曖昧なままでは、制度設計や運用で迷走し、従業員の理解も得られません。経営トップからのメッセージ発信も重要となります。
現状分析と課題の洗い出し
現在の雇用形態、人事制度、組織文化、従業員のスキル構成などを分析し、ジョブ型雇用導入にあたっての課題を洗い出します。例えば、既存の職務内容が曖昧である、評価制度が年功序列的である、従業員の専門性が不足している、といった課題が考えられます。この現状認識が、具体的な制度設計の土台となります。
ジョブの定義と職務記述書(ジョブディスクリプション)の作成
社内に存在する各職務について、その内容、責任範囲、必要なスキル・経験・資格、期待される成果などを具体的に定義し、職務記述書として文書化します。これはジョブ型雇用の根幹となる作業であり、客観的かつ網羅的に行う必要があります。既存の職務を見直すだけでなく、将来的に必要となる新たな職務を定義することも重要です。このプロセスには、現場の管理職や従業員の意見を聴取することも有効です。
職務評価の実施と等級制度の設計
作成した職務記述書に基づいて、各職務の価値や難易度を客観的に評価し、等級制度を設計します。職務評価の手法には、要素比較法、ポイント法など様々なものがありますので、自社に適した方法を選択します。この等級が、報酬や処遇の基準となります。
報酬制度の設計
職務等級に基づいて、報酬レンジ(給与の範囲)を設定します。市場の報酬水準も参考にしながら、内部的な公平性と外部的な競争力を両立できるような報酬制度を設計することが重要です。成果に応じたインセンティブ制度の導入も検討します。
人事評価制度の再構築
職務記述書に定められた目標の達成度や、職務遂行における行動などを評価する新たな人事評価制度を構築します。評価基準や評価プロセスを明確にし、評価者研修を実施するなどして、評価の公平性と納得性を高める努力が必要です。定期的なフィードバックの仕組みも重要となります。
採用・育成・配置転換の仕組みの整備
職務記述書に基づいた採用プロセスの確立、専門性を高めるための研修制度やキャリア開発支援策の導入、公募制を中心とした配置転換の仕組みなどを整備します。従業員のキャリア自律を支援する視点が求められます。
就業規則・関連規程の改定
ジョブ型雇用の導入に伴い、就業規則や賃金規程、退職金規程など、関連する諸規程を見直し、改定する必要があります。法的な整合性を確保するため、専門家のアドバイスも活用しましょう。
従業員への説明とコミュニケーション
新しい人事制度の目的、内容、変更点、従業員への影響などを、丁寧かつ具体的に説明し、理解と協力を得ることが不可欠です。説明会や質疑応答の機会を設け、双方向のコミュニケーションを重視します。不安や疑問を解消し、納得感を醸成することが、制度のスムーズな移行に繋がります。
段階的な導入とモニタリング・改善
全社一斉導入が難しい場合は、特定の部門や職種から段階的に導入することを検討します。導入後は、制度の運用状況を定期的にモニタリングし、従業員からのフィードバックも収集しながら、必要に応じて改善を加えていくことが重要です。ジョブ型雇用は一度導入したら終わりではなく、常に最適化を図っていく必要があります。
ジョブ型雇用を成功させるポイント
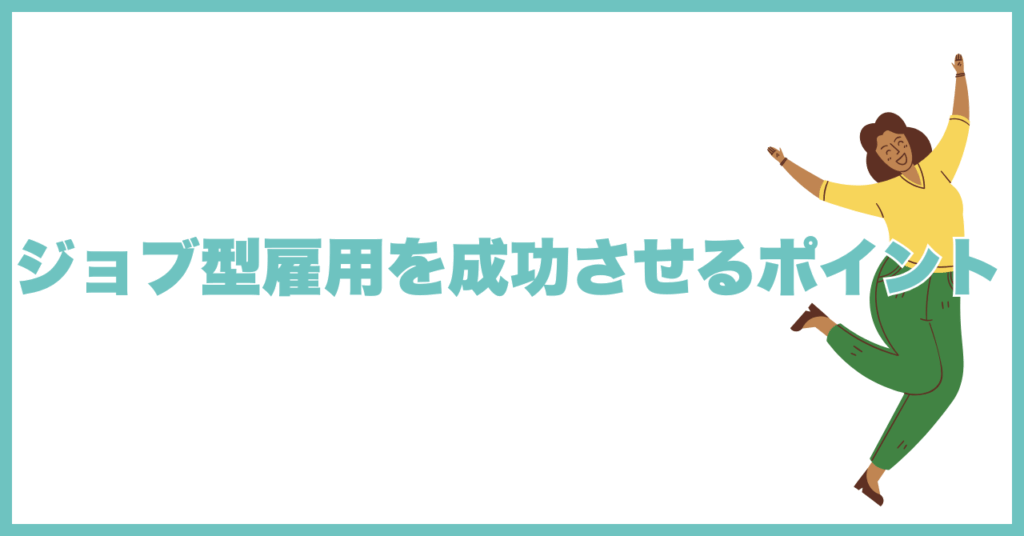
自社の方針を明確にし、社内のコンセンサスを得る
他社の事例を鵜呑みにするのではなく、自社の経営戦略や文化に合ったジョブ型雇用のあり方を追求し、従業員の理解と共感を得ることが成功の鍵です。
メンバーシップ型雇用との併用も検討する
全ての職種や階層にジョブ型雇用を適用するのではなく、職務特性や育成方針に応じて、メンバーシップ型雇用の良い点を残したり、両者を組み合わせたりするハイブリッド型も有効な選択肢です。
長期的な視点で取り組む
ジョブ型雇用の導入と定着には時間がかかります。短期的な成果を求めすぎず、継続的な改善を重ねながら、自社に合った形を作り上げていく姿勢が重要です。
経営戦略との連動を常に意識する
人事制度は経営戦略を実現するための手段です。事業環境の変化や経営戦略の見直しに合わせて、ジョブ型雇用のあり方も柔軟に見直していく必要があります。
まとめ
ジョブ型雇用の導入は、企業にとって大きな挑戦ですが、適切に設計・運用されれば、企業の競争力強化と持続的成長、そして従業員のキャリア自律支援に大きく貢献する可能性を秘めています。 本記事では、「ジョブ型雇用」について、その基本的な概念からメンバーシップ型雇用との違い、注目される背景、企業側・従業員側双方のメリット・デメリット、そして具体的な導入手順と成功のポイントに至るまで、多角的に解説してまいりました。
ジョブ型雇用は、専門性の高い人材を確保し、成果に基づいた公正な評価を実現することで企業の競争力強化に貢献する可能性を秘めている一方で、人材の流動化やゼネラリスト育成の課題、制度移行の難しさといった側面も持ち合わせています。従業員にとっては、専門性を活かして主体的なキャリアを築けるメリットがある反面、常に自己研鑽を続け、雇用の不安定さに備える必要性も生じます。
重要なのは、ジョブ型雇用を万能な解決策として捉えるのではなく、自社の経営戦略、事業特性、組織文化、そして従業員の価値観などを総合的に勘案し、その導入の是非や最適な形を慎重に検討することです。場合によっては、メンバーシップ型雇用の長所を活かしつつ、ジョブ型雇用の要素を取り入れるハイブリッド型のアプローチも有効でしょう。
いずれの雇用形態を選択するにしても、企業と従業員が互いに信頼し合い、共に成長していける関係性を構築することが、変化の激しい時代を乗り越え、持続的な発展を遂げるための鍵となります。本記事が、人事責任者や経営者の皆様にとって、今後の人事戦略を考える上での一助となれば幸いです。
「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe
Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界1300名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス
⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス
⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス
などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。
