
【採用担当者向け】カジュアル面談とは?目的、メリットから失敗例と対策まで徹底解説
近年、労働市場の変化と採用競争の激化を背景に、新たな採用手法を取り入れる企業が増えつつあります。その中で、候補者と企業が対等な立場で相互理解を深める「カジュアル面談」を導入する企業も少なくありません。選考とは異なるリラックスした雰囲気で行われるカジュアル面談は、候補者の本音や潜在的なニーズを引き出せることから、入社後のミスマッチ防止や志望意欲の向上に効果を発揮するといわれています。
本記事では、カジュアル面談の基本的な定義から、注目される背景、企業側が得られるメリット、そして多くの企業が陥りがちな失敗例とその対策までを網羅的に解説します。さらに、効果的な進め方や具体的な質問例、先進企業の成功事例も交えながら、採用担当者が明日から実践できるノウハウを提供します。
目次
- カジュアル面談とは?
- なぜ今、カジュアル面談が注目されるのか?
- 企業がカジュアル面談を実施する3つのメリット
- 【失敗から学ぶ】カジュアル面談で陥りがちな10の失敗例と具体的な対策
- カジュアル面談を成功に導く!効果的な進め方と質問例
- まとめ
カジュアル面談とは?
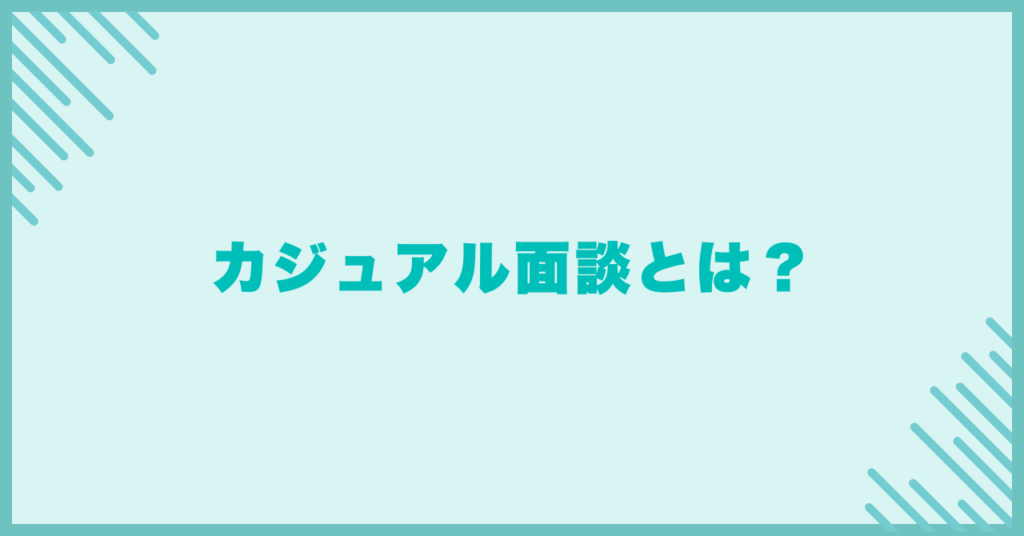
カジュアル面談は、採用活動における初期段階で、企業と候補者が互いをより深く知るために設けられるコミュニケーションの場です。従来の面接とは一線を画し、その目的や進め方には独自の特徴があります。
カジュアル面談の定義と目的
カジュアル面談とは、候補者の採否を決めることを目的とした「面接」とは異なり、企業と候補者が相互理解を深めるための情報交換の場です。多くの場合、選考要素は含まれず、リラックスした雰囲気の中で、お互いが対等な立場で対話することが重視されます。企業側は自社のビジョンや文化、働きがいなどを伝え、候補者は自身のキャリアプランや価値観、疑問点などを率直に話すことができます。
この面談の主な目的は、本格的な選考に進む前に、候補者との間に良好な関係を築き、自社への興味・関心を高めてもらうことにあります。また、企業側にとっても、候補者の潜在的な能力や人柄、自社とのカルチャーフィットを見極める貴重な機会となります。
従来の面接との違い
カジュアル面談と従来の面接の最も大きな違いは、その「目的」にあります。面接が「評価・選考」を主眼に置くのに対し、カジュアル面談は「相互理解・魅力づけ」に重点を置きます。この目的の違いが、雰囲気やコミュニケーションのあり方に大きな差を生み出します。
| 項目 | カジュアル面談 | 従来の面接 |
| 目的 | 相互理解、情報交換、魅力づけ | 候補者の評価、採否判断 |
| 立場 | 対等な関係 | 評価する側とされる側 |
| 雰囲気 | リラックス、フランク | フォーマル、緊張感がある |
| 内容 | 自由な対話、キャリア相談、情報提供 | 経歴やスキルの確認、志望動機 |
| 選考要素 | 基本的に含まない | 採否に直結する |
なぜ今、カジュアル面談が注目されるのか?
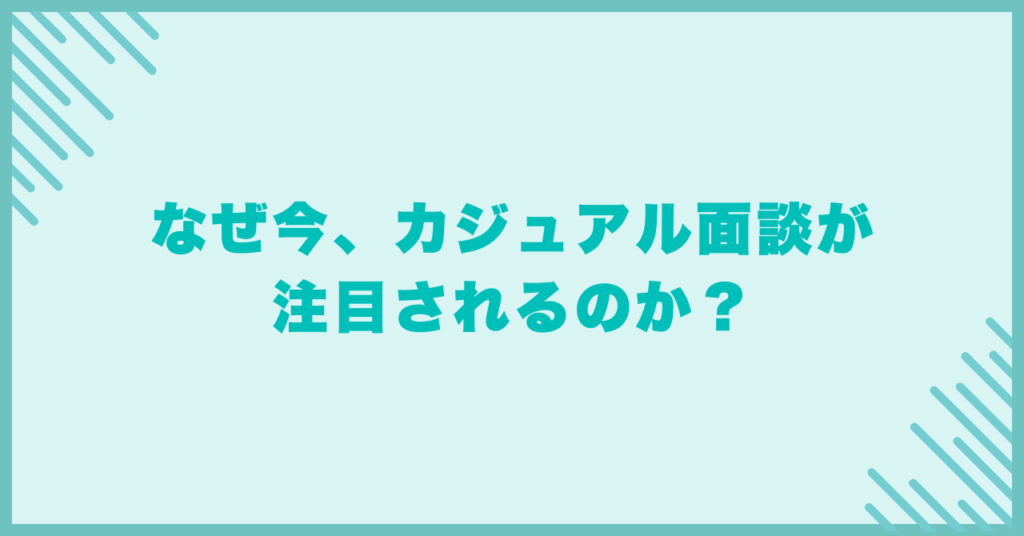
近年、多くの企業がカジュアル面談を導入する背景には、現代の労働市場が抱える構造的な変化があります。採用競争の激化と、働くことに対する価値観の多様化が、企業に新たな採用アプローチを求めているのです。
採用競争の激化と売り手市場
少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少により、多くの業界で人材獲得競争が激化しています。いわゆる「売り手市場」が続く中、企業はもはや応募者を待つだけの「待ちの姿勢」では、優秀な人材を確保することが困難になりました。企業側から積極的に候補者にアプローチし、自社の魅力を能動的に伝えていく「攻めの採用」が不可欠となっています。
実際に、株式会社学情が2025年に行った調査によると、キャリア採用において「カジュアル面談を実施している」と回答した企業は36.7%に上り、3社に1社以上が導入していることが明らかになりました。さらに「実施を検討している」と回答した企業も30.1%に達しており、カジュアル面談が企業の採用戦略において、有力な手法として定着しつつあることがうかがえます。
出典:株式会社学情, https://umai-jinji.jp/column/interview-52/
働き方の多様化と求職者の価値観の変化
終身雇用の概念が薄れ、転職が当たり前になった現代において、求職者の企業選びの軸も大きく変化しています。給与や福利厚生といった条件面だけでなく、企業のビジョンやパーパスへの共感、組織文化とのフィット感、自己成長の機会、ワークライフバランスといった、より本質的な要素を重視する傾向が強まっています。
求職者は、入社後の「働きがい」や「自分らしさの発揮」を求め、企業の表面的な情報だけでは意思決定をしなくなりました。カジュアル面談は、こうした求職者のニーズに応え、企業のリアルな情報を伝え、候補者が抱く疑問や不安を解消するための効果的な手段として、その重要性を増しているのです。
企業がカジュアル面談を実施する3つのメリット
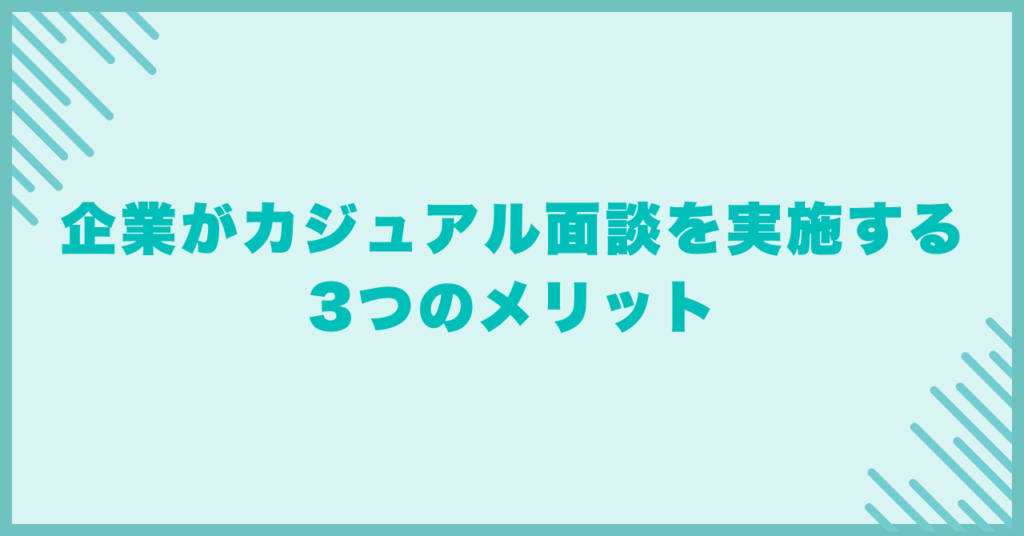
カジュアル面談を戦略的に活用することで、企業は採用活動において大きなメリットを得ることができます。ここでは、代表的な3つのメリットについて詳しく解説します。
1. 候補者とのミスマッチを防ぎ、定着率向上へ
入社後のミスマッチは、早期離職の大きな原因となり、採用コストの増大や組織力の低下を招きます。限られた時間で行われる選考面接だけでは、企業の文化や働く環境、人間関係といった「リアルな情報」を候補者に十分に伝えることは困難です。
カジュアル面談を通じて、候補者はリラックスした状態で現場社員などから具体的な話を聞くことができます。これにより、入社後の働き方をより鮮明にイメージできるようになり、「思っていたのと違った」というギャップを最小限に抑えることが可能です。企業側もまた、対話を通じて候補者の価値観やキャリア志向が自社のカルチャーに本当にフィットするかどうかを慎重に見極めることができ、結果として入社後の定着率向上に大きく貢献します。
2. 候補者の入社意欲を高め、惹きつけを強化
選考という評価のプレッシャーがないカジュアル面談は、候補者一人ひとりのキャリアプランや価値観に寄り添った対話を可能にします。候補者の話に真摯に耳を傾け、その関心やニーズに合わせた情報を提供することで、「自分のことを理解してくれている」という信頼感を醸成することができます。
このようなパーソナライズされたコミュニケーションは、候補者の企業に対するエンゲージメントを高め、「この会社で働きたい」という入社意欲を強力に喚起します。特に、複数の企業から内定を得ているような優秀な人材に対しては、最終的な意思決定を促す上で非常に効果的なアプローチとなります。
3. 潜在層へアプローチし、質の高い母集団を形成
カジュアル面談は、今すぐの転職を考えている「転職顕在層」だけでなく、良い機会があれば転職したいと考えている「転職潜在層」にアプローチする上でも極めて有効です。本格的な選考ではないため、候補者も気軽に参加しやすく、企業は早い段階から有望な人材との接点を持つことができます。
ダイレクトリクルーティングやリファラル(社員紹介)などを通じてコンタクトした候補者に対し、まずはカジュアル面談を提案することで、自社の魅力を伝え、関係性を構築しておく。そうすることで、その候補者が本格的に転職活動を開始した際に、自社を第一想起してもらえる可能性が飛躍的に高まります。これにより、競争が激化する前に優秀な人材を確保し、質の高い母集団を形成することが可能になるのです。
【失敗から学ぶ】カジュアル面談で陥りがちな10の失敗例と具体的な対策
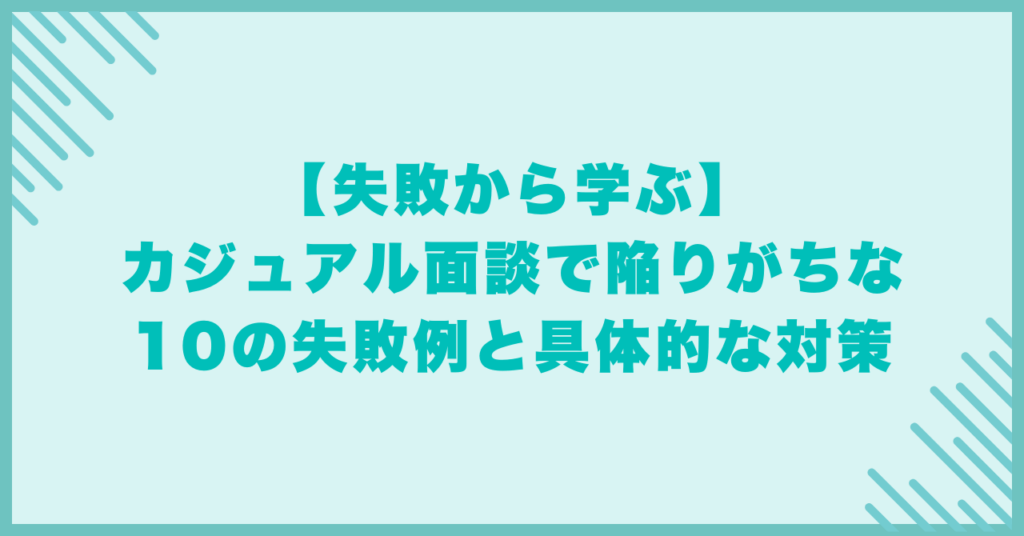
カジュアル面談は多くのメリットをもたらす一方で、その運用方法を誤ると、かえって企業の評判を落としたり、採用機会を損失したりするリスクも伴います。ここでは、多くの採用担当者が陥りがちな10の失敗例と、それを未然に防ぐための具体的な対策を解説します。
失敗例1:目的が曖昧なまま始めてしまう
ありがちな失敗
「他社もやっているから」「流行っているから」といった曖昧な動機でカジュアル面談を導入し、具体的な目的やゴール設定がないまま運用してしまうケースです。結果として、面談が単なる雑談で終わってしまい、候補者の惹きつけや次の選考への接続といった成果に結びつきません。
対策
カジュアル面談を導入する前に、「誰に(ターゲット層)」「何のために(企業認知向上、特定ポジションの魅力づけ、潜在層のタレントプール化など)」「面談後にどうなってほしいか(選考応募、定期的な情報提供の承諾など)」を具体的に定義し、採用チーム全体でその目的を共有することが不可欠です。目的が明確になることで、面談の構成や担当者の選定、話すべき内容も自ずと定まり、効果を最大化できます。
失敗例2:企業と候補者間で認識がズレている
ありがちな失敗
企業側は「選考とは無関係の情報交換の場」と位置づけていても、候補者は「実質的な一次面接ではないか」と身構えてしまうケースです。この認識のズレは、候補者の過度な緊張を招き、本音の対話を妨げる大きな要因となります。
対策
候補者への案内メールの段階から、「今回の面談は選考ではございません」「リラックスして、相互理解を深めるための時間にできれば幸いです」といった文言を明確に記載し、選考ではない旨を繰り返し伝えることが重要です。さらに、面談の冒頭でも改めてその点を口頭で伝え、候補者の心理的な安全性を確保する配慮が求められます。
失敗例3:気づけば「面接」になっている
ありがちな失敗
面談担当者が普段の面接の癖で、「あなたの強み・弱みは?」「なぜ当社を志望するのですか?」といった評価的な質問を繰り返してしまうパターンです。これにより、雰囲気は一気に緊張感のあるものに変わり、カジュアル面談本来の目的である「リラックスした対話」が失われてしまいます。
対策
面談を担当する社員(特に現場社員)に対して、カジュアル面談の目的と面接との違いを明確にレクチャーする事前研修を実施しましょう。「評価」ではなく「対話」に徹すること、一方的な質問攻めではなく、会話のキャッチボールを意識することを徹底させることが重要です。
失敗例4:一方的な自社アピールに終始する
ありがちな失敗
候補者に自社を魅力的に感じてもらいたいという思いが先行するあまり、企業側が一方的に会社説明や事業内容を話し続けてしまうケースです。候補者は受け身の姿勢になり、知りたい情報を得る機会を失い、「自分の話を聞いてもらえなかった」という不満を抱くことになります。
対策
面談の主役はあくまで候補者です。序盤は候補者のキャリア観や興味関心について丁寧にヒアリングすることに時間を使い、候補者のニーズに合わせて情報を提供するというスタンスを徹底しましょう。「話す」よりも「聞く」姿勢が、結果的に候補者の満足度と信頼感を高めます。
失敗例5:候補者が本当に知りたい情報を提供できていない
ありがちな失敗
企業のウェブサイトや求人票に書かれているような一般的な情報提供に終始し、候補者が本当に知りたい「リアルな情報」を提供できていないケースです。例えば、具体的な業務内容、チームの雰囲気、キャリアパス、残業の実態など、候補者が抱える疑問や不安に応えられていないと、面談の価値は半減してしまいます。
対策
事前に候補者の経歴やスキルシートを読み込み、「この人は何に興味を持ち、どんな情報を求めているだろうか」と仮説を立てて準備しておくことが有効です。また、面談中も「何か具体的に聞いておきたい業務はありますか?」などと問いかけ、候補者の知りたい情報を引き出す工夫をしましょう。必要に応じて、写真や動画、実際の成果物などを見せることも理解を深める上で効果的です。
失敗例6:リラックスした雰囲気を作れていない
ありがちな失敗
面談の冒頭、アイスブレイクなしにいきなり本題に入ってしまい、終始堅苦しい雰囲気で進んでしまうケースです。物理的な環境(会議室など)も相まって、候補者は最後まで緊張が解けず、表面的な会話に終わってしまいます。
対策
面談の冒頭で、担当者の簡単な自己紹介(業務内容だけでなく、趣味なども交えると効果的)や、当日の天気や交通手段といった軽い雑談から入ることを意識しましょう。オンラインの場合は、背景について触れてみるのも良いでしょう。こうした小さな工夫が、場の空気を和ませ、対話しやすい雰囲気を作り出します。
失敗例7:候補者を質問攻めにしてしまう
ありがちな失敗
会話の沈黙を恐れるあまり、用意してきた質問リストを上から順番に消化するように、次々と質問を投げかけてしまうパターンです。これは候補者にとって尋問のように感じられ、大きな心理的負担となります。
対策
質問はあくまで会話のきっかけと捉え、一つの回答に対してさらに深掘りすることを意識しましょう。「そうなんですね。もう少し詳しく教えていただけますか?」といった形で、候補者の話に興味を示す姿勢が、自然で深みのある対話を生み出します。
失敗例8:面談後のフォローアップを怠る
ありがちな失敗
面談で良い感触を得たにもかかわらず、その後のフォローアップが遅れたり、あるいは全く行われなかったりするケースです。候補者は「自分に興味がなかったのかもしれない」「あの面談は何だったのだろう」と感じ、せっかく高まった志望度が時間とともに低下してしまいます。
対策
面談終了後、当日中(遅くとも24時間以内)に、担当者個人の言葉でお礼のメールを送るのが理想です。メールには、面談で印象に残ったことや、話に出てきた内容に関する補足情報などを添えると、よりパーソナルな印象を与え、好感度を高めることができます。
失敗例9:クロージングが曖昧で次のステップにつながらない
ありがちな失敗
面談の最後に「また何かあればご連絡ください」「ぜひご検討ください」といった受け身の言葉で締めくくり、具体的な次のアクションを示さないケースです。これにより、候補者は次にどう動けば良いか分からず、選考に進む意欲があっても、そのままフェードアウトしてしまうことがあります。
対策
候補者の感触が良いと判断した場合、「もしご興味をお持ちいただけましたら、ぜひ次の選考ステップに進んでいただきたいのですが、いかがでしょうか?」と、企業側から明確に次のステップを提示しましょう。その場で結論が出なくても、「それでは、来週の月曜日までに、改めて今後のご意向についてメールでご連絡いただけますでしょうか」など、具体的なアクションと期限をセットで伝えることが重要です。
失敗例10:「お祈りメール」を送ってしまう
ありがちな失敗
カジュアル面談は選考ではないと伝えていたにもかかわらず、面談後に「慎重に検討を重ねた結果、今回はご期待に沿いかねる結果となりました」といった、いわゆる「お祈りメール」を送ってしまう最悪のパターンです。これは候補者との信頼関係を著しく損ない、企業の評判を落とす行為に他なりません。
対策
カジュアル面談は、あくまで相互理解の場です。企業側が「自社とは合わない」と感じたとしても、合否の連絡は決して行ってはいけません。面談に参加してくれたことへの感謝を伝え、今後の選考への案内は行わない、という形でコミュニケーションを完結させましょう。将来的に別のポジションで縁がある可能性も踏まえ、良好な関係を維持することが賢明です。
カジュアル面談を成功に導く!効果的な進め方と質問例
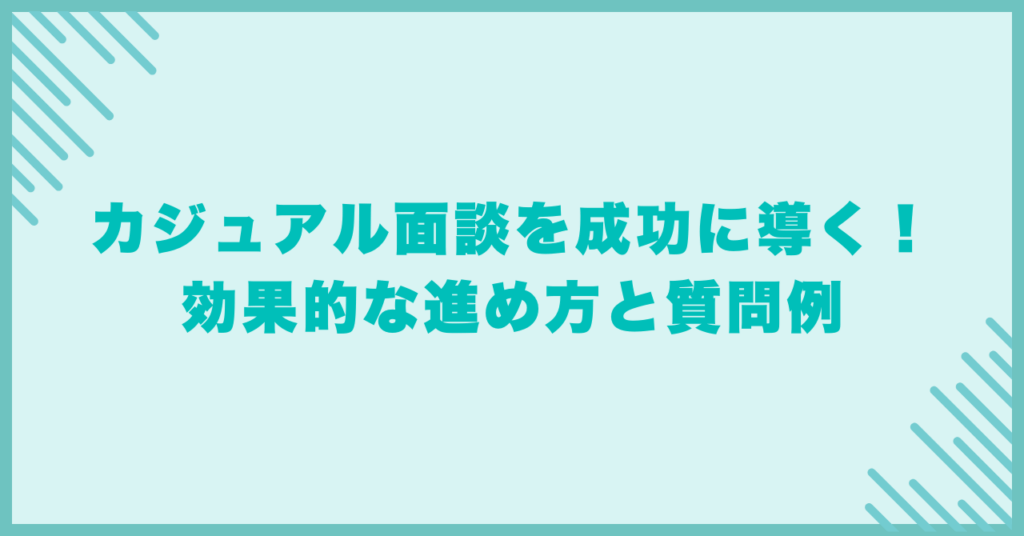
カジュアル面談の成否は、事前の準備と当日の進め方にかかっています。ここでは、面談の効果を最大化するための具体的なステップと、対話を深めるための質問例を紹介します。
カジュアル面談の進め方(7つのステップ)
効果的なカジュアル面談は、以下の7つのステップで構成されます。この流れを意識することで、候補者との間に信頼関係を築き、有意義な対話を実現できます。
1. 事前準備
目的の明確化と候補者理解 面談の成功は準備で8割決まります。まず、今回の面談の目的(魅力づけ、カルチャーフィットの確認など)を再確認します。次に、候補者の職務経歴書やSNSなどを読み込み、その人の経験、スキル、興味関心、価値観について仮説を立てます。「どんな話に興味を持ちそうか」「どんな情報を伝えれば魅力に感じてもらえそうか」を事前にシミュレーションしておきましょう。
2. アイスブレイク
緊張をほぐす自己紹介と雑談 面談は、担当者の自己紹介と軽い雑談から始めます。業務内容だけでなく、自身の経歴や趣味、入社理由などを交えて自己開示することで、候補者も心を開きやすくなります。5分程度の時間を使い、和やかな雰囲気を作り出すことを最優先します。
3. 目的の共有
「選考ではない」ことを明確に アイスブレイクが終わったら、改めて本日の面談の目的を伝えます。「本日は選考ではございませんので、リラックスしてお話しください。弊社について理解を深めていただくとともに、〇〇様(候補者)のキャリアについてもぜひお聞かせいただければと思います」といった形で、あくまで相互理解の場であることを明確に伝え、心理的な安全性を確保します。
4. ヒアリング
候補者の状況とニーズを深く知る 一方的に会社説明を始めるのではなく、まずは候補者の話を聞くことからスタートします。「現在、どのような軸でキャリアを考えていらっしゃいますか?」「転職活動では、どのような情報を重視されていますか?」といった質問を通じて、候補者の現状、価値観、ニーズを深く理解します。このヒアリングが、後の情報提供の質を左右します。
5. 情報提供
候補者の関心に合わせた魅力づけ ヒアリングで得た情報をもとに、候補者の興味関心に沿った形で、自社の情報を伝えます。例えば、成長機会を重視する候補者には具体的なキャリアパスや研修制度の話を、ワークライフバランスを気にする候補者には柔軟な働き方や福利厚生の話を手厚くするなど、パーソナライズされた情報提供を心がけます。企業の魅力が最も効果的に伝わる瞬間です。
6. 質疑応答
双方向のコミュニケーションを意識 面談の後半では、候補者からの質問に答える時間を十分に確保します。どんな質問にも誠実に、そして具体的に答える姿勢が信頼関係を深めます。また、企業側からも「弊社の話を聞いて、何か気になった点や、もっと知りたいことはありますか?」と問いかけ、双方向のコミュニケーションを促しましょう。
7. クロージング
次のアクションを具体的に提示 面談の最後には、必ず次のステップを明確に伝えます。候補者の感触が良ければ、「ぜひ次の選考に進んでいただきたいのですが、ご意向はいかがでしょうか?」と企業側から積極的に働きかけます。その場で結論が出ない場合でも、「それでは、来週〇曜日までに、今後のご意向についてメールでご連絡いただけますでしょうか」など、具体的なアクションと期限を設定することで、採用機会の損失を防ぎます。
【状況別】企業側から使える質問例集
カジュアル面談では、評価につながる質問は避けつつも、候補者のことを深く知るための工夫が必要です。以下に、状況別に使える質問例を挙げます。
候補者のキャリア観・価値観を知る質問
•「これまでのお仕事で、特にやりがいを感じたのはどのような瞬間でしたか?」
•「今後、どのようなスキルや経験を身につけていきたいとお考えですか?」
•「仕事を選ぶ上で、これだけは譲れないという軸があれば教えてください。」
•「どのようなチームや環境で働いているときに、ご自身の力が最も発揮されると感じますか?」
候補者の興味・関心を探る質問
•「最近、何か注目している技術やサービスはありますか?」
•「情報収集は、普段どのようなメディアや方法で行っていますか?」
•「弊社の事業内容について、現時点でどのような印象をお持ちですか?」
自社への関心度を測る質問
•「本日の話の中で、特に興味を持たれた部分はどこでしたか?」
•「もし弊社で働くとしたら、どのようなことにチャレンジしてみたいですか?」
•「現時点で、何か懸念されている点や不安な点はありますか?」
候補者からの逆質問に備えるべきポイント
候補者からの逆質問は、彼らの関心度や企業理解度を知る絶好の機会であると同時に、企業が誠実さを示す重要な場面でもあります。特に、給与、残業、福利厚生といった待遇面や、具体的なキャリアパス、社内の人間関係など、求人票だけでは分からない「リアルな情報」に関する質問が来ることを見越して、誠実に回答できる準備をしておくことが重要です。答えにくい質問に対しても、曖昧に濁すのではなく、可能な範囲でオープンに情報開示する姿勢が、候補者の信頼を獲得します。
まとめ
本記事では、採用担当者に向けて、カジュアル面談の目的やメリット、そして成功に導くための具体的な方法論を、失敗例や成功事例を交えながら包括的に解説しました。
採用競争が激化し、求職者の価値観が多様化する現代において、カジュアル面談はもはや単なる流行りの手法ではありません。候補者と真摯に向き合い、対等な立場で相互理解を深めるこの取り組みは、企業と候補者のミスマッチをなくし、採用活動を成功させるための不可欠な戦略となっています。
重要なのは、カジュアル面談を「選考の入り口」として形式的に行うのではなく、「企業と個人の対話の場」として捉え、その目的を明確にし、誠実なコミュニケーションを徹底することです。今回ご紹介した進め方や質問例、そして失敗例への対策を参考に、ぜひ自社の採用戦略に合った、効果的なカジュアル面談を設計・実践してみてください。それが、未来の優秀な仲間と出会うための、確かな一歩となるはずです。

「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe
Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界1300名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス
⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス
⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス
などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。
