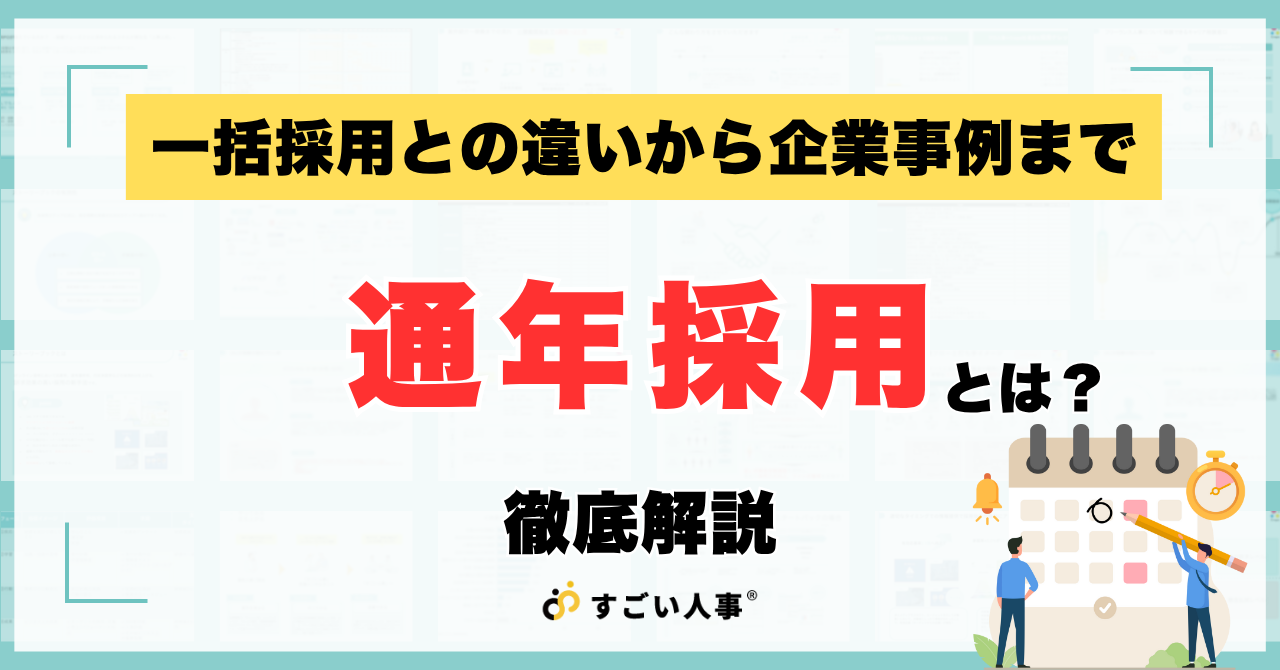
通年採用とは?一括採用との違いとメリット・導入方法を徹底解説
近年、日本の採用市場は大きな転換期を迎えています。少子高齢化に伴う労働人口の減少、働き方の多様化、そしてグローバル化の進展は、従来の新卒一括採用という画一的な採用モデルだけでは、企業が求める人材を確保することが困難になりつつある状況を生み出しています。こうした背景から、年間を通じて柔軟な採用活動を行う「通年採用」に注目が集まっています。
かつては外資系企業や一部のIT企業が中心だった通年採用ですが、現在では業界や規模を問わず多くの企業が導入を検討、あるいはすでに実施しています。本記事では、人事担当者や経営者の皆様に向けて、通年採用の基本的な概念から、従来の一括採用との違い、導入のメリット・デメリット、そして具体的な導入方法と成功のポイントまで解説します。
目次
通年採用とは
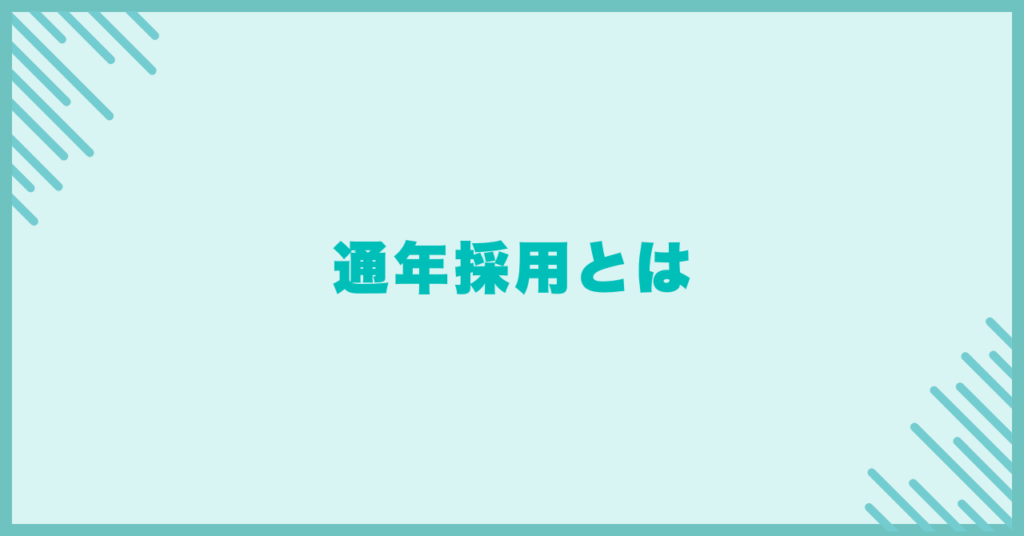
通年採用の定義
通年採用とは、その名の通り、企業が年間を通じて採用活動を行う手法を指します。特定の時期に限定せず、企業のニーズや求職者の状況に応じて、新卒・既卒・中途を問わず、柔軟に人材を募集・選考・採用するのが特徴です。これにより、企業は多様なバックグラウンドを持つ人材にアプローチすることが可能になります。
一括採用との違い
日本の伝統的な採用モデルである「新卒一括採用」と「通年採用」は、その目的と仕組みにおいて大きく異なります。以下の表で、両者の主な違いを比較してみましょう。
| 項目 | 通年採用 | 新卒一括採用 |
| 採用時期 | 年間を通じて随時 | 特定の期間に集中(主に春) |
| 対象者 | 新卒、既卒、第二新卒、中途など | 主に翌年春に卒業予定の学生 |
| 選考スケジュール | 企業が自由に設定 | 政府や経済団体が示す指針に準拠 |
| 採用計画 | 欠員補充や事業拡大など、必要に応じて柔軟に対応 | 年度ごとの事業計画に基づく計画的な大量採用 |
| 内定者フォロー | 個別の状況に合わせた対応が必要 | 集団での研修やフォローが中心 |
一括採用が、限られた期間で多くの学生を効率的に採用し、同期入社による一体感の醸成や計画的な人材育成を目的としているのに対し、通年採用は、より多様な人材プールから、企業の即戦力となる人材や、特定のスキルを持つ人材を、必要なタイミングで確保することに主眼を置いています。
通年採用が注目される背景
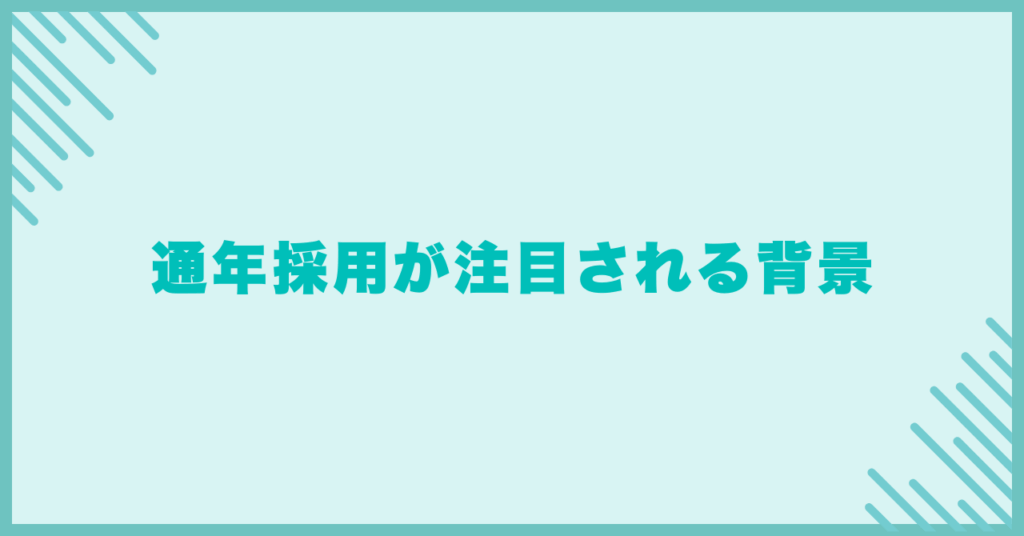
近年、多くの企業が通年採用に注目し、導入を進めている背景には、社会構造や労働市場の大きな変化があります。ここでは、その主な理由を3つの側面から解説します。
労働人口の減少と採用競争の激化
日本の生産年齢人口(15~64歳)は1995年をピークに減少を続けており、今後もこの傾向は続くと予測されています。この労働力不足は、企業にとって深刻な課題であり、優秀な人材の獲得競争はますます激化しています。従来の一括採用だけでは、限られた期間での競争が激しくなり、必要な人材を確保できないケースが増えています。そのため、年間を通じて採用の門戸を開き、より多くの候補者と接点を持つことができる通年採用が、有効な対策として注目されているのです。
働き方の多様化とグローバル化
留学経験者や海外の大学を卒業した学生、あるいは国内でも秋に卒業する学生など、学生のキャリアパスは多様化しています。また、第二新卒や既卒者、あるいは専門的なスキルを持つ中途採用者など、新卒の学生以外にも優秀な人材は数多く存在します。こうした多様なバックグラウンドを持つ人材は、従来の一括採用のスケジュールに合わないことが多く、企業がアプローチする機会を逃す一因となっていました。通年採用は、こうした多様な人材に対して、時期を問わずアプローチすることを可能にし、企業のダイバーシティ推進にも貢献します。
政府の採用方針の変更
かつて経団連が定めていた「採用選考に関する指針」が2021年卒採用から廃止され、政府主導のルールへと移行したことも、通年採用への移行を後押しする一因となりました。虽然政府は依然として一定の採用スケジュールを要請していますが、その拘束力は以前よりも弱まり、企業の採用活動の自由度は高まっています。特に、専門性の高い人材については採用日程の前倒しが検討されるなど、より柔軟な採用活動が推奨される傾向にあり、これが通年採用の導入を検討する企業にとって追い風となっています。
通年採用のメリット
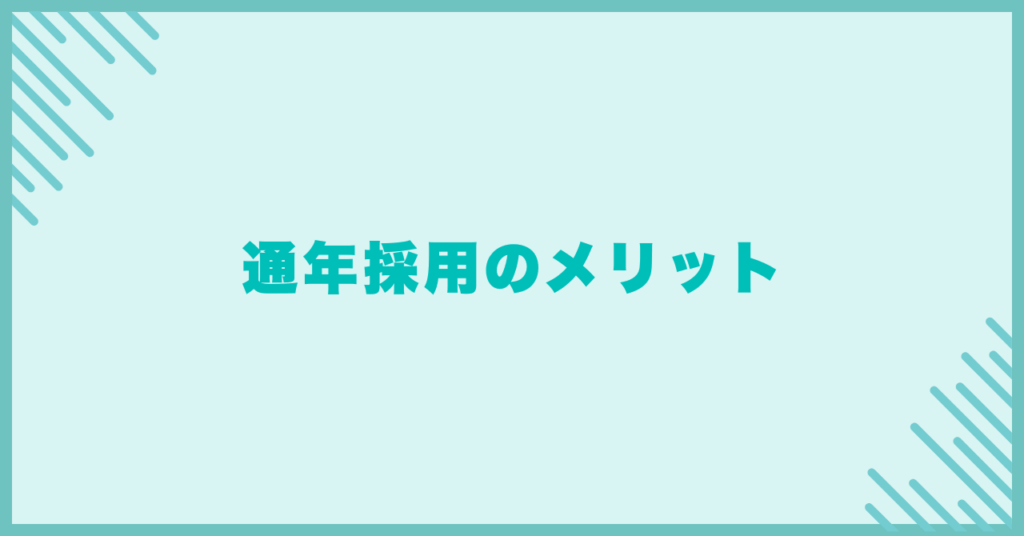
通年採用は、企業と求職者の双方にとって多くのメリットをもたらします。ここでは、それぞれの視点から主な利点を詳しく見ていきましょう。
企業側のメリット
◾️多様な人材との出会い
通年採用を導入する最大のメリットの一つは、従来の一括採用では出会うことが難しかった多様な人材にアプローチできる点です。一括採用の画一的なスケジュールでは、以下のような人材との接点を持つ機会が限られていました。
留学生・帰国子女
海外の大学の卒業時期は日本の大学とは異なることが多く、一括採用のタイミングに合わせることが困難です。
第二新卒・既卒者
卒業後に改めてキャリアを考える人材や、早期離職した若手人材も、通年採用であれば積極的に採用対象とすることができます。
特定の分野に打ち込んでいた学生
学業や研究、部活動、あるいは起業など、学生時代に特定の活動に打ち込み、一般的な就職活動の時期を逃してしまった優秀な学生にも門戸を開くことができます。
年間を通じて採用活動を行うことで、こうした多様な経験や視点を持つ人材を獲得し、組織の活性化やイノベーションの創出につなげることが期待できます。
◾️ミスマッチの防止
一括採用では、限られた期間内に多数の応募者を選考する必要があるため、一人ひとりの候補者とじっくり向き合う時間を確保することが難しいという課題がありました。その結果、企業と候補者の相互理解が不十分なまま採用に至り、入社後のミスマッチが発生するリスクが高まります。
一方、通年採用では、選考スケジュールに余裕が生まれるため、面接回数を増やしたり、インターンシップや職場見学の機会を設けたりと、候補者を多角的に評価し、深く理解するための時間を十分に確保できます。候補者側も、企業文化や仕事内容への理解を深めることができるため、結果として入社後の定着率向上にもつながります。
◾️欠員補充のしやすさ
事業計画の変更や急な退職者などにより、年度の途中で人員補充が必要になるケースは少なくありません。一括採用の場合、次の採用シーズンまで待たなければならず、事業運営に支障をきたす可能性がありました。
通年採用であれば、年間を通じて採用活動を行っているため、内定辞退や急な欠員が発生した場合でも、迅速に新たな候補者の募集・選考を開始することができます。これにより、企業は常に最適な人員体制を維持し、ビジネス機会の損失を防ぐことが可能になります。
求職者側のメリット
◾️柔軟な就職活動
求職者にとっての大きなメリットは、自身の都合やペースに合わせて就職活動を進められる点です。留学や学業、個人的な事情などで一括採用のスケジュールに乗れなかった場合でも、通年採用を実施している企業であれば、焦ることなく挑戦の機会を得ることができます。
◾️企業理解の深化
通年採用は、求職者が企業をじっくりと研究し、理解を深めるための時間的な余裕も与えてくれます。複数の企業の選考を並行して受けるのではなく、一つの企業に集中して情報収集や自己分析を行うことで、より納得感のあるキャリア選択が可能になります。
通年採用のデメリットと注意点
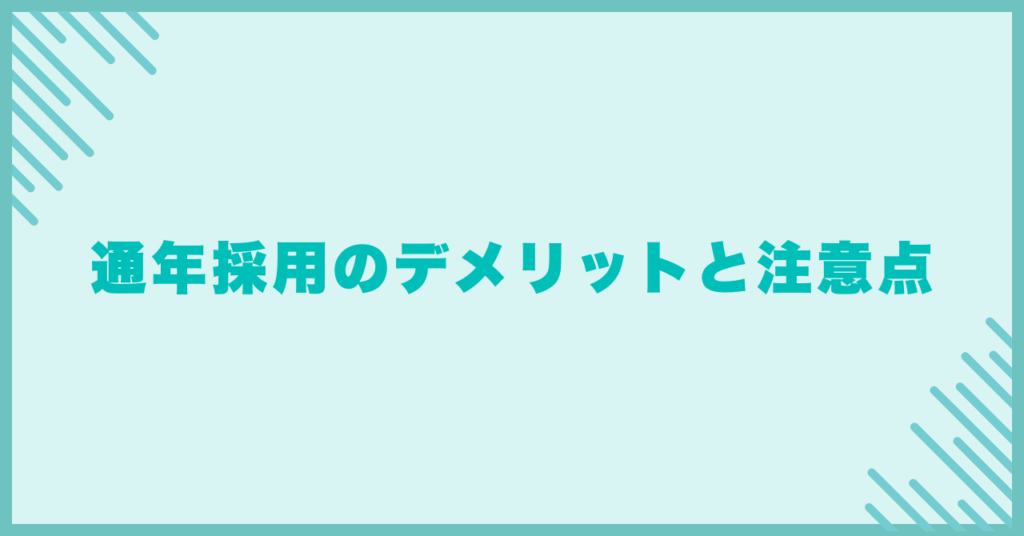
多くのメリットがある一方で、通年採用の導入にはいくつかのデメリットや注意すべき点も存在します。ここでは、企業側が直面しうる課題と、導入にあたっての注意点を解説します。
企業側のデメリット
◾️採用コスト・工数の増加
年間を通じて採用活動を行うことは、採用に関連するコストや工数が継続的に発生することを意味します。一括採用のように特定の期間に集中して活動を行う場合と比較して、求人広告の掲載期間が長くなったり、複数回にわたって会社説明会や選考会を実施する必要が出てきたりするため、トータルでの費用は増加する傾向にあります。また、採用活動が長期化することで、人事部門の業務負荷も高まります。
◾️採用担当者の負担増
通年採用では、応募者のエントリー時期が分散するため、その都度、個別に対応する必要があります。書類選考、面接日程の調整、合否連絡、内定者フォローなど、一括採用であればまとめて処理できた業務が年間を通じて発生するため、採用担当者の負担は大幅に増加します。特に、少人数の人事部門で運用する場合には、他の業務との両立が大きな課題となるでしょう。
◾️内定者フォローの複雑化
入社時期が異なる複数の内定者を同時にフォローすることは、一括採用の内定者フォローとは異なる難しさがあります。入社までの期間が内定者ごとに異なるため、コミュニケーションの取り方や情報提供のタイミングなどを個別に管理する必要があります。また、同期入社の意識が希薄になりがちなため、内定者同士の連帯感を醸成し、入社意欲を維持・向上させるための工夫も求められます。
導入時の注意点
◾️採用計画の明確化
通年採用を成功させるためには、まず「どのような人材を、いつまでに、何名採用するのか」という採用計画を明確にすることが不可欠です。場当たり的な採用活動に陥らないよう、事業計画と連動した長期的な視点での人員計画を策定し、それに基づいて採用ターゲットや求める人物像を具体的に定義する必要があります。
◾️社内体制の整備
採用担当者だけでなく、現場の面接官や受け入れ部署の協力体制を事前に構築しておくことが重要です。年間を通じて発生する面接に対応できるよう、複数の面接官を育成し、評価基準を標準化しておく必要があります。また、入社時期が異なる社員を受け入れ、スムーズにオンボーディング(定着支援)を行うための教育・研修プログラムや、メンター制度などのサポート体制を整備することも欠かせません。
◾️採用広報の工夫
年間を通じて継続的に母集団を形成するためには、採用広報の戦略も重要になります。自社のウェブサイトや採用ブログ、SNSなどを活用して、企業の魅力や働く環境に関する情報を継続的に発信し、潜在的な候補者との関係を構築していく必要があります。また、ターゲットとする人材層に応じて、ダイレクトリクルーティングやリファラル採用など、多様な採用チャネルを組み合わせることも有効です。
通年採用の導入方法
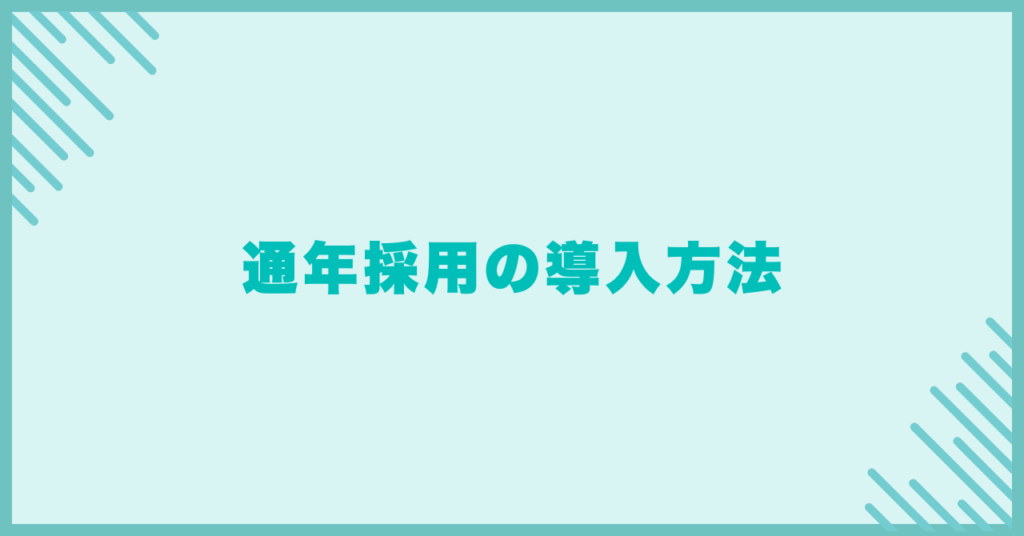
通年採用を効果的に導入し、成功させるためには、計画的かつ段階的なアプローチが求められます。ここでは、具体的な導入ステップと、成功のためのポイントを解説します。
導入ステップ
1. 採用計画の策定
まず、自社の経営戦略や事業計画に基づき、どのような人材が、いつ、どの部署で必要になるのかを洗い出します。その上で、採用する人物像(ペルソナ)を具体的に設定し、年間の採用人数や入社時期の目標を定めます。この計画が、以降のすべての活動の土台となります。
2. 募集チャネルの選定
策定した採用ターゲットに効果的にアプローチできる募集チャネルを選定します。新卒向け就職サイト、転職サイト、ダイレクトリクルーティングサービス、人材紹介、リファラル採用、自社採用サイト、SNSなど、多様なチャネルの中から、ターゲット層や予算に応じて最適な組み合わせを検討します。
3. 選考プロセスの設計
年間を通じて柔軟に対応できる選考プロセスを設計します。書類選考から最終面接までのフロー、各段階での評価基準、面接官の役割分担などを明確にします。オンライン面接を導入するなど、地理的・時間的な制約を受けにくい選考方法を取り入れることも有効です。
4. 内定後のフォロー体制の構築
入社時期が異なる内定者一人ひとりの状況に合わせたフォロー体制を構築します。定期的なコミュニケーションプランの策定、内定者向けイベントの開催、メンターによる個別相談など、入社までの不安を解消し、帰属意識を高めるための施策を計画的に実行します。
成功させるためのポイント
◾️採用ターゲットの明確化
「誰でもいつでも応募可能」という姿勢では、かえって応募が集まりにくくなることがあります。「当社はこのようなスキルや経験を持つ人材を求めています」というメッセージを明確に打ち出すことで、ターゲット人材からの応募を促進し、選考の効率も高まります。
◾️柔軟な選考方法の導入
候補者の多様なバックグラウンドに対応するため、選考方法にも柔軟性を持たせることが重要です。例えば、エンジニア職であればコーディングテスト、企画職であれば企画書の提出を求めるなど、職種に応じたスキル評価を取り入れることで、より的確な人材を見極めることができます。
◾️採用管理ツールの活用
年間を通じて多数の候補者の情報を管理し、選考プロセスを円滑に進めるためには、採用管理システム(ATS)の活用が非常に有効です。候補者情報の一元管理、選考進捗の可視化、面接日程の自動調整、コミュニケーション履歴の記録など、採用業務の効率を大幅に向上させることができます。
通年採用の導入企業事例
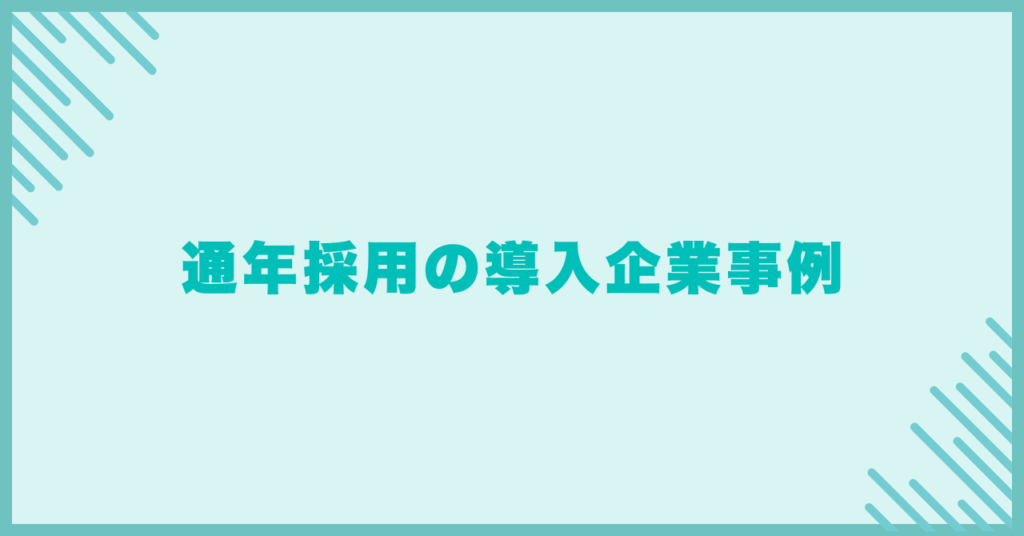
実際に通年採用を導入し、多様な人材獲得に成功している企業の事例をいくつかご紹介します。各社の取り組みは、自社で通年採用を導入する際の参考になるでしょう。
ソフトバンク
ソフトバンクは、「ユニバーサル採用」と称して、新卒・既卒を問わず、応募者が自身のタイミングで選考に参加できる制度を早くから導入しています。一般的な選考だけでなく、特定の分野で高い能力を持つ人材を対象とした「No.1採用」や、就労体験を通じて選考を行うインターンシップなど、多様な入り口を設けているのが特徴です。これにより、画一的な基準では測れないポテンシャルを持つ人材の発掘に成功しています。
ユニクロ(ファーストリテイリング)
ファーストリテイリンググループのユニクロでは、「一人ひとりが仕事について真剣に考え、主体的に行動し、納得した将来が送れるように」という考えのもと、年間を通じて新卒採用を行っています。一度不合格になった場合でも再チャレンジできる制度を設けるなど、候補者の成長や変化を長期的な視点で見極めようとする姿勢が特徴的です。これにより、短期間の選考では見抜けない候補者の潜在能力や熱意を評価する機会を創出しています。
ヤフー
ヤフーでは、「ポテンシャル採用」という名称で、30歳以下であれば新卒、既卒、就業経験の有無を問わず応募できる採用制度を導入しています。留学経験者や博士号取得者、あるいは一度社会に出てからキャリアチェンジを考える若手など、多様化するキャリアパスに対応し、幅広い層から優秀な人材を獲得することを目指しています。経歴ではなくポテンシャルを重視することで、新たな価値を創造できる人材の採用につなげています。
楽天
楽天グループでは、特にエンジニア職において、ポジション別に通年採用を積極的に行っています。毎月入社可能とするなど、採用から入社までを非常に柔軟に運用しているのが特徴です。これにより、グローバルな競争が激しいIT人材を、国内外からスピーディーに獲得することが可能となっています。専門性の高い職種においては、こうした柔軟な採用・受け入れ体制が、採用競争力を高める上で重要な要素となります。
まとめ
本記事では、通年採用の基本的な概念から、そのメリット・デメリット、具体的な導入方法、そして先進的な企業事例まで解説しました。
労働人口の減少、働き方の多様化、そしてグローバル化という不可逆的な変化の中で、企業が持続的に成長していくためには、もはや従来の新卒一括採用だけに依存することは困難です。年間を通じて多様な人材にアプローチし、企業の競争力を高める「通年採用」は、これからの時代のスタンダードな採用手法となっていくでしょう。
もちろん、通年採用の導入には、採用コストの増加や担当者の負担増など、乗り越えるべき課題も存在します。しかし、本記事で紹介した導入ステップや成功のポイントを参考に、自社の状況に合わせて計画的に導入を進めることで、そのデメリットを上回る大きなメリットを享受できるはずです。
重要なのは、通年採用を単なる採用手法の変更と捉えるのではなく、企業の成長戦略や人材戦略そのものを見直す機会とすることです。多様な人材が活躍できる組織文化を醸成し、柔軟な働き方を許容する制度を整えることと一体で進めることで、通年採用の効果は最大化されます。

「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe
Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界1300名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス
⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス
⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス
などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。
