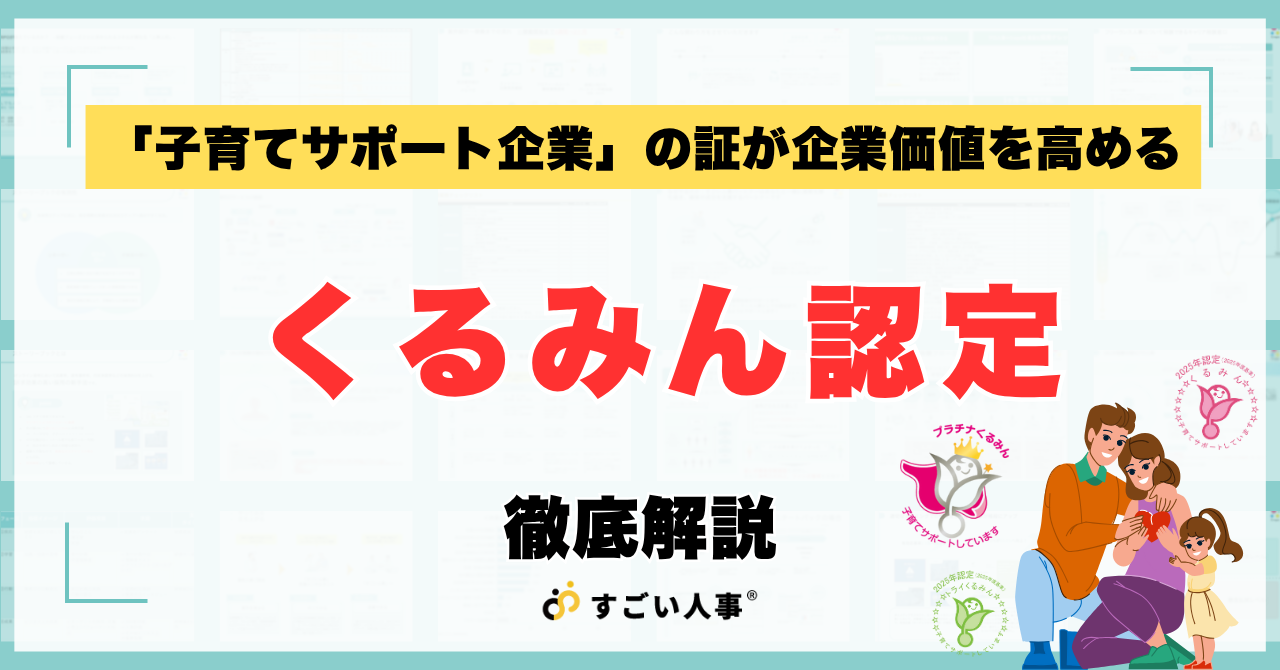
【2025年最新】くるみん認定とは?種類や基準、メリットを徹底解説
少子高齢化による労働力不足が深刻化する現代日本において、企業の持続的な成長のためには、多様な人材が活躍できる環境整備が不可欠です。特に、育児と仕事の両立支援は、優秀な人材の確保・定着に直結する重要な経営課題と言えるでしょう。
こうした中、国が子育てサポートに積極的に取り組む企業を評価する制度が「くるみん認定」です。本記事では、人事・経営者の皆様に向けて、くるみん認定の概要から2025年4月に改正された最新の認定基準、取得のメリット、申請方法まで、解説します。
目次
- くるみん認定とは?~次世代を担う子育て世代を支援する企業の証~
- 3種類の「くるみんマーク」と、不妊治療も支援する「プラス」認定
- 【2025年4月改正】くるみん認定の新基準を徹底解説
- 企業がくるみん認定を取得する5つの主要メリット
- くるみん認定の申請から取得までの7ステップ
- 混同しやすい「えるぼし認定」との違いとは?
- まとめ
くるみん認定とは?~次世代を担う子育て世代を支援する企業の証~
くるみん認定は、次世代育成支援対策推進法(以下、次世代法)に基づき、従業員の仕事と子育ての両立支援に積極的に取り組む企業を厚生労働大臣が「子育てサポート企業」として認定する制度です。認定を受けた企業は、「くるみんマーク」を商品や広告、求人票などに使用することができ、企業のイメージアップや人材獲得競争における優位性確保に繋がります。
くるみん認定制度の概要と、企業に求められる役割
くるみん認定制度は、単に育児休業制度などを導入しているだけでなく、実際に従業員が制度を利用しやすい職場環境の整備や、具体的な成果を上げている企業を評価するものです。企業は、従業員のニーズを把握した上で「一般事業主行動計画」を策定・公表し、その計画に定めた目標を達成することが認定の前提となります。
一般事業主行動計画とは 次世代育成支援対策推進法に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、(1)計画期間、(2)目標、(3)目標達成のための対策及びその実施時期を定めるものです。
出典: 厚生労働省「一般事業主行動計画の策定・届出等について」
常時雇用する労働者が101人以上の企業には、この行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられています(100人以下の企業は努力義務)。企業には、単なる制度の導入に留まらず、男性の育児休業取得促進や所定外労働の削減など、実効性のある取り組みを通じて、子育て世代が安心して働き続けられる環境を構築する役割が求められています。
根拠法である「次世代育成支援対策推進法」のポイント
くるみん認定の根拠となる次世代法は、急速な少子化の進行に対応し、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備するために2005年に施行されました。当初は10年間の時限立法でしたが、その後も少子化に歯止めがかからない状況から、2035年3月31日まで延長されています。
この法律は、国や地方公共団体だけでなく、企業に対しても、従業員の仕事と子育ての両立支援を求めるものであり、くるみん認定制度は、その取り組みを促進するための重要な柱となっています。
3種類の「くるみんマーク」と、不妊治療も支援する「プラス」認定
くるみん認定制度には、企業の取り組みレベルに応じて3段階の認定が設けられています。さらに、2022年4月からは、不妊治療と仕事の両立支援に取り組む企業を評価する「プラス」認定も加わりました。これにより、企業は自社の状況に合わせて段階的に、かつ多角的な子育て支援を目指すことが可能です。
| 認定の種類 | 特徴 |
| トライくるみん認定 | これから本格的に子育て支援に取り組む企業が、くるみん認定を目指すための第一歩となる認定。 |
| くるみん認定 | 子育てサポート企業として、一定の基準を満たした企業に与えられる基本的な認定。 |
| プラチナくるみん認定 | くるみん認定企業の中でも、より高い水準の取り組みを行い、継続的に成果を上げているトップレベルの企業に与えられる特例認定。 |
| プラス認定 | 上記3つの認定に加えて、不妊治療と仕事の両立支援に取り組む企業に付与される認定。(くるみんプラス、トライくるみんプラス、プラチナくるみんプラス) |
トライくるみん認定:認定への第一歩
「トライくるみん認定」は、くるみん認定の取得を目指しているものの、現時点ではその基準をすべて満たしていない企業を対象とした、いわば準備段階の認定です。男性の育児休業取得率などの基準が、くるみん認定よりも緩和されており、中小企業などがスモールスタートで子育て支援の取り組みを始めることを後押しします。
くるみん認定:子育てサポートの標準モデル
「くるみん認定」は、子育てサポートに関する行動計画を達成し、国が定める10項目の認定基準をすべて満たした企業に与えられます。認定を受けることで、名実ともに「子育てサポート企業」として社会的に認められ、前述したような様々なメリットを享受できます。認定回数に応じてマークに付される星の数が増えていき、継続的な取り組みをアピールすることが可能です。
プラチナくるみん認定:トップレベルの証
「プラチナくるみん認定」は、すでにくるみん認定を取得している企業が、さらに高いレベルの両立支援制度を導入し、その利用状況も極めて高い水準にある場合に認定されます。認定基準はくるみん認定よりも厳しく設定されており、例えば、男性の育児休業取得率は30%以上(2025年4月からの新基準)が求められます。プラチナくるみん認定は、子育てサポートにおける先進的な取り組みを行うトップランナー企業の証と言えるでしょう。
くるみんプラス、トライくるみんプラス、プラチナくるみんプラス:不妊治療と仕事の両立支援
近年、晩婚化などを背景に不妊治療を受ける夫婦が増加しており、仕事との両立が大きな課題となっています。この社会的な要請に応える形で創設されたのが「プラス」認定制度です。それぞれの認定基準に加えて、不妊治療と仕事の両立を支援するための環境整備(休暇制度、相談体制など)に関する目標を定め、達成した企業に付与されます。これにより、企業はより幅広い従業員のニーズに応え、多様な働き方を支援する姿勢を示すことができます。
【2025年4月改正】くるみん認定の新基準を徹底解説
2025年4月1日、次世代育成支援対策推進法の改正に伴い、くるみん認定およびプラチナくるみん認定の基準が大幅に引き上げられました。これは、男性の育児参加をさらに促進し、より実効性のある子育て支援を企業に促すことを目的としています。人事・経営者の皆様は、この新しい基準を正確に理解し、自社の取り組みを見直す必要があります。
なぜ基準は改正されたのか?背景と目的
今回の基準改正の背景には、男性の育児休業取得率の伸び悩みや、依然として女性に偏りがちな育児負担の現状があります。政府は「異次元の少子化対策」を掲げ、男女ともに育児と仕事を両立できる社会の実現を目指しており、その一環として、企業のより積極的な関与を促すために認定基準の厳格化に踏み切りました。
目的は、くるみん認定の価値を高め、認定企業が社会のロールモデルとして、より高い水準の子育て支援を牽引していくことです。特に、男性の育休取得を「当たり前」の文化として定着させることへの強い意志がうかがえます。
【一覧表】新旧基準の比較(男性の育休取得率など)
今回の改正で特に注目すべきは、男性の育児休業取得率に関する基準の大幅な引き上げです。以下に、くるみん認定とプラチナくるみん認定における主要な変更点をまとめました。
| 認定の種類 | 評価項目 | 旧基準(~2025年3月31日) | 新基準(2025年4月1日~) |
| くるみん認定 | 男性の育休取得率 | 10%以上 | 10%以上 または、育休等+企業独自の休暇制度の利用率が20%以上 |
| プラチナくるみん認定 | 男性の育休取得率 | 30%以上 | 30%以上 または、育休等+企業独自の休暇制度の利用率が50%以上 |
| くるみん認定 | 所定外労働時間 | – | 計画期間の終了年度において、フルタイム労働者の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月30時間未満であること等が追加 |
| プラチナくるみん認定 | 所定外労働時間 | – | 計画期間の終了年度において、フルタイム労働者の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満であること等が追加 |
くるみん認定の具体的な新基準
新しいくるみん認定基準では、男性の育休取得率に加えて、所定外労働の削減や多様な働き方の推進がより重視されています。主な基準は以下の通りです。
1.男性の育児休業等取得
男性労働者の育休取得率が10%以上、または育休等と企業独自の育児目的休暇制度の利用率を合わせて20%以上であること。2.女性の育児休業等取得
女性労働者の育休取得率が75%以上であること。3.所定外労働の削減
フルタイム労働者等の時間外・休日労働時間の平均が各月30時間未満であることなど。4.多様な労働条件の整備
育児休業の期間延長、年次有給休暇の取得促進、短時間正社員制度や在宅勤務などの措置について目標を定め、実施していること。5.法遵守
関連する法令を遵守していること。
プラチナくるみん認定のさらに厳しい基準
プラチナくるみん認定では、これらの基準がさらに厳格化されます。
1.男性の育児休業等取得
男性労働者の育休取得率が30%以上、または育休等と企業独自の育児目的休暇制度の利用率を合わせて50%以上であること。2.女性の継続就業
出産した女性労働者のうち、子の1歳の誕生日まで在職している人の割合が90%以上であることなど。3.キャリア形成支援
育児中の従業員のキャリア形成を支援するための計画を策定し、実施していること。
これらの新基準は、企業に対して、より本質的で継続的な子育て支援体制の構築を求めるものです。
企業がくるみん認定を取得する5つの主要メリット
くるみん認定は、社会貢献という側面だけでなく、企業経営に直接的なプラス効果をもたらす戦略的な取り組みです。ここでは、企業が認定を取得することで得られる5つの主要なメリットを解説します。
メリット1:企業イメージ向上と採用競争力の強化
くるみんマークは、厚生労働大臣が認めた「子育てサポート企業」の信頼の証です。これを自社のウェブサイト、採用ページ、製品やサービスに掲示することで、社内外に対して従業員の働きやすさを重視する先進的な企業であることを強力にアピールできます。厚生労働省の調査では、くるみん認定を取得した企業の49.2%が「学生に対するイメージアップ」を実感していると回答しており、特に若年層や女性求職者からの共感を呼び、優秀な人材の獲得において大きなアドバンテージとなります。
メリット2:従業員の定着率向上とエンゲージメント強化
認定取得のプロセスを通じて、育児休業制度の利用促進や所定外労働の削減といった具体的な取り組みが社内に浸透します。これにより、従業員は出産や育児といったライフステージの変化に不安を感じることなく、安心して働き続けることができます。実際に、認定企業からは「出産・育児を理由とした退職者の減少」(プラチナくるみん認定企業では24.0%)や「従業員の定着率向上」(同22.4%)といった効果が報告されており、人材の流出を防ぎ、組織全体のエンゲージメントを高める効果が期待できます。
メリット3:くるみん助成金の活用(中小企業向け)
常時雇用する労働者が300人以下の中小企業がくるみん認定またはプラチナくるみん認定を取得した場合、「くるみん助成金」の対象となります。この助成金は、仕事と育児の両立支援のためにかかった費用の一部を助成するもので、最大で50万円が支給されます。制度導入に伴うコスト負担を軽減し、より積極的な両立支援策の導入を後押しします。
メリット4:賃上げ促進税制の優遇措置
企業の賃上げを促進するための「賃上げ促進税制」において、くるみん認定企業は税制上の優遇措置を受けることができます。プラチナくるみん認定を取得したすべての企業、および、くるみん認定を取得した中小企業は、通常の控除に加えて法人税額等からの控除率が5%上乗せされます。これにより、従業員の待遇改善と企業の税負担軽減を同時に実現することが可能になります。
メリット5:公共調達における加点評価
国の各府省庁や地方自治体が行う公共調達において、くるみん認定企業は加点評価の対象となる場合があります。これにより、官公庁関連の入札において有利な立場を築くことができ、新たなビジネスチャンスの獲得に繋がる可能性があります。
くるみん認定の申請から取得までの7ステップ
くるみん認定の取得は、単なる申請手続きだけでなく、自社の労働環境を見つめ直し、継続的な改善サイクルを回していくプロセスそのものです。ここでは、認定取得に向けた具体的な7つのステップを解説します。
ステップ1:自社の現状と従業員ニーズの把握
まず、行動計画を実効性のあるものにするため、自社の現状を客観的に把握することが不可欠です。過去数年間の男女別の育児休業取得率、復職率、所定外労働時間の実績などをデータで分析します。同時に、従業員アンケートやヒアリングを実施し、「どのような支援制度があれば育児と仕事を両立しやすいか」「制度の利用をためらう理由はないか」といった現場の生の声を収集します。
ステップ2:一般事業主行動計画の策定
ステップ1で明らかになった課題に基づき、具体的な行動計画を策定します。計画には、(1)計画期間(2年~5年)、(2)数値目標、(3)目標達成のための対策、(4)実施時期を盛り込む必要があります。特に2025年4月からは、従業員101人以上の企業には、育児休業等の取得状況や労働時間の状況に係る数値目標の設定が義務付けられました。「男性の育休取得率を〇%以上に引き上げる」「全社の月平均残業時間を〇時間未満にする」といった、具体的で測定可能な目標を設定することが重要です。
ステップ3:行動計画の公表と社内周知
策定した行動計画は、外部へ公表するとともに、社内の従業員へ周知徹底する必要があります。外部への公表は、厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」への掲載や、自社のウェブサイトへの掲載が一般的です。社内へは、社内イントラネットへの掲載、説明会の実施、ポスターの掲示など、全従業員が計画内容を認知できるような方法で周知します。
ステップ4:都道府県労働局への行動計画策定の届出
行動計画を策定・変更したら、その日からおおむね3か月以内に、管轄の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ「一般事業主行動計画策定・変更届」を提出します。届出は、郵送、持参、または政府の電子申請システム「e-Gov」を通じて行うことができます。この際、行動計画書そのものを添付する必要はありません。
ステップ5:行動計画の実施と進捗管理(PDCA)
届出が完了したら、計画に沿って取り組みを実施します。計画倒れに終わらせないためには、定期的に進捗状況を確認し、目標達成に向けたPDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルを回していくことが不可欠です。担当部署が中心となり、各施策の実施状況や数値目標の達成度をモニタリングし、必要に応じて計画の見直しや追加の対策を検討します。
ステップ6:認定基準達成後の認定申請
計画期間が終了し、設定した目標を達成し、かつ国の定める認定基準をすべて満たしたことを確認したら、いよいよ認定申請です。「基準適合一般事業主認定申請書」に必要な書類を添付し、管轄の都道府県労働局へ提出します。申請が受理されると、労働局による書類審査が行われます。
ステップ7:認定通知と「くるみんマーク」の活用
審査の結果、基準を満たしていると判断されると、労働局から認定通知書が交付され、晴れて「くるみん認定企業」となります。その後は、「くるみんマーク」を自社のウェブサイトや名刺、求人広告などに使用し、子育てサポート企業であることを広く社会にアピールすることができます。
混同しやすい「えるぼし認定」との違いとは?
企業のダイバーシティ&インクルージョン推進において、くるみん認定と並んでよく耳にするのが「えるぼし認定」です。両者はともに従業員が働きやすい環境整備を評価する制度ですが、その根拠となる法律と目指す方向性に違いがあります。
根拠となる法律と目的の違いを明確化
| 認定制度 | 根拠法 | 主な目的 |
| くるみん認定 | 次世代育成支援対策推進法 | 仕事と子育ての両立支援(男女問わず) |
| えるぼし認定 | 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法) | 女性の活躍推進(採用、昇進、職域拡大など) |
端的に言えば、くるみん認定が「育児」を軸とした両立支援に焦点を当てているのに対し、えるぼし認定は「女性」を軸としたキャリア全般の活躍推進を評価する制度です。そのため、くるみん認定では男性の育休取得率が重要な指標となる一方、えるぼし認定では管理職に占める女性比率などが評価項目となります。
両方の認定を取得する相乗効果とブランディング戦略
両制度は異なる側面に焦点を当てていますが、目指すところは「誰もが活躍できる職場環境の実現」という点で共通しています。企業が「くるみん認定」と「えるぼし認定」の両方を取得することは、単に二つの認定を得たというだけでなく、「育児支援」と「女性活躍」という両面から、ダイバーシティ経営に本気で取り組む企業であることの強力な証明となります。
これにより、より幅広い層の求職者に対して魅力をアピールできるだけでなく、ESG投資(環境・社会・ガバナンスを重視する投資)の観点からも企業価値の向上に繋がり、企業の持続的な成長を支える強固なブランディング戦略となり得ます。
まとめ
本記事では、2025年4月に新基準が施行された「くるみん認定」について、その種類や基準、メリット、申請方法に至るまでを包括的に解説しました。
くるみん認定の取得は、もはや単なる福利厚生の充実や社会貢献活動の一環ではありません。それは、優秀な人材を惹きつけ、定着させ、従業員一人ひとりの生産性を最大化するための、極めて重要な「経営戦略」です。厳しい新基準をクリアすることは容易ではありませんが、そのプロセスを通じて構築される「男女ともに子育てをしながらキャリアを継続できる職場環境」は、変化の激しい時代を勝ち抜くための強固な基盤となるでしょう。
人事・経営者の皆様におかれましては、本記事を参考に、ぜひくるみん認定の取得を前向きにご検討いただき、企業の持続的な成長と、次代を担う子どもたちが健やかに育つ社会の実現に向けた一歩を踏み出していただければ幸いです。
「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe
Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界1300名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス
⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス
⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス
などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。
