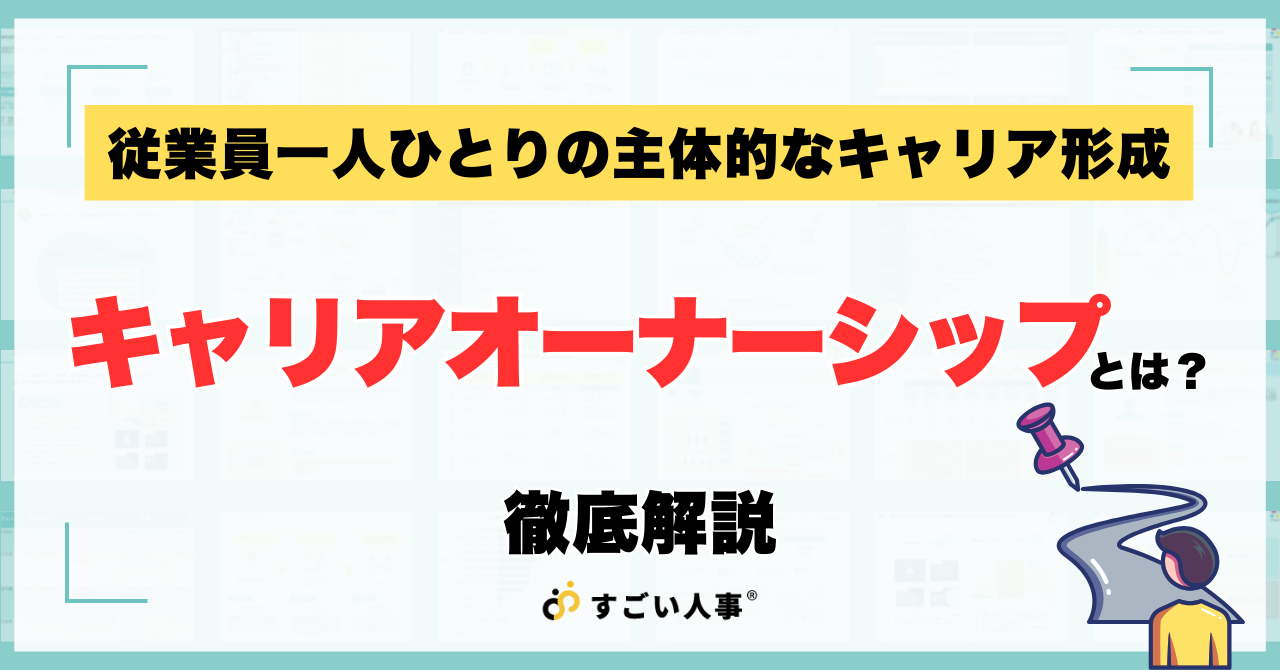
現代のビジネス環境は、終身雇用制度の変容、人生100年時代の到来、そして個人の価値観の多様化といった大きな変化の渦中にあります。このような時代において、企業が持続的に成長し、競争優位性を維持するためには、従業員一人ひとりの主体的なキャリア形成、すなわち「キャリアオーナーシップ」の確立が不可欠です。本記事では、人事担当者の皆様に向けて、キャリアオーナーシップの基本的な概念から、企業がその推進に取り組むことの具体的なメリット、そして実践的な方法や先進企業の事例に至るまで、網羅的に解説します。
目次
キャリアオーナーシップとは
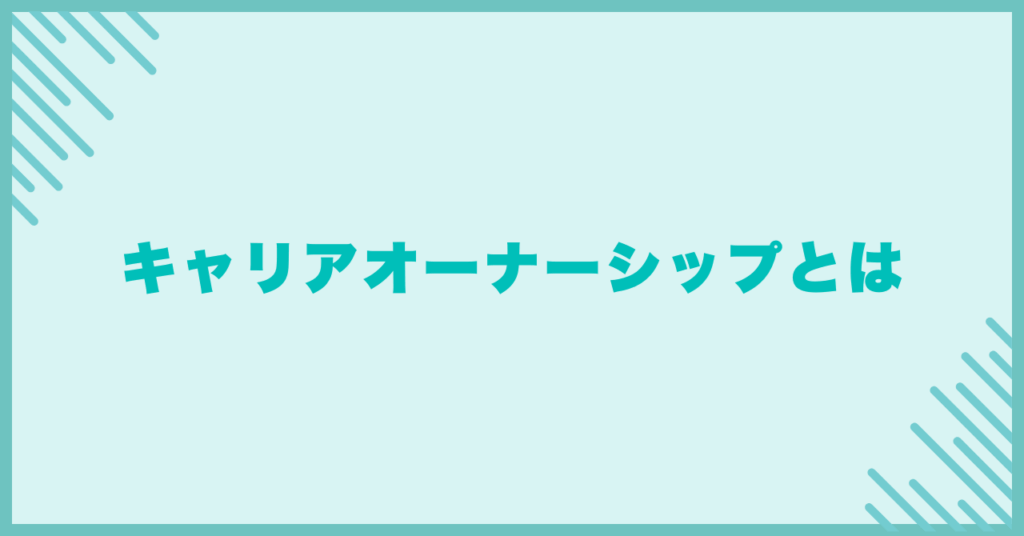
キャリアオーナーシップという言葉を耳にする機会は増えましたが、その本質を正確に理解しているでしょうか。このセクションでは、キャリアオーナーシップの定義と、現代においてなぜこれほどまでに注目を集めているのか、その背景を深掘りします。
キャリアオーナーシップの定義と基本的な考え方
キャリアオーナーシップとは、一般的に「個人が自身のキャリアに対して主体性(オーナーシップ)を持って取り組む意識と行動」を指します 。これは、企業から与えられるキャリアパスを待つのではなく、従業員自らが「どうありたいか」を問い、その実現に向けて能動的に行動していく姿勢を意味します。
経済産業省は、この概念をさらに具体的に、以下の2つの側面から説明しています。
『個人一人ひとりが「自らのキャリアはどうありたいか、如何に自己実現したいか」を意識し、納得のいくキャリアを築くための行動をとっていくこと』
『個人が自らの問題意識を持ち、学び、働くことを通じて、自らの「羅針盤」をもってキャリアを構築していくこと』
これらの定義から明らかなように、キャリアオーナーシップは単なる「意識」だけにとどまらず、具体的な「行動」を伴う概念です。従業員が自身のキャリアの舵を自らの手に取り、変化の激しい時代を航海していくための羅針盤とも言えるでしょう。
なぜ今、キャリアオーナーシップが注目されるのか
キャリアオーナーシップが現代の経営において重要なキーワードとなっている背景には、複数の社会的・経済的要因が複雑に絡み合っています。
終身雇用制度の変容
かつての日本企業を支えた終身雇用や年功序列といった制度は、グローバル化の進展や市場競争の激化により、その維持が困難になっています。企業はもはや従業員の生涯にわたる雇用を保証できなくなり、個人は自らの市場価値を高め、社外でも通用する専門性を身につける必要に迫られています。
人生100年時代の到来
平均寿命の延伸により、私たちの職業人生はこれまで以上に長期化しています。定年後も働き続けることが一般的となり、「学ぶ→働く→引退する」という単線的なキャリアモデルは過去のものとなりました。個人は、ライフステージの変化に合わせて、学び直し(リスキリング)や新たな挑戦を繰り返しながら、生涯にわたって活躍し続けることが求められます。
働き方の多様化と個人の価値観の変化
テレワークの普及や副業・兼業の解禁など、働き方はますます多様化しています。それに伴い、仕事に対する個人の価値観も変化し、金銭的な報酬だけでなく、自己成長や社会貢献、ワークライフバランスを重視する傾向が強まっています。企業は、多様な価値観を持つ従業員のエンゲージメントを高めるために、画一的なキャリアパスではなく、個人の主体性を尊重したキャリア支援を提供する必要があるのです。
SG投資の拡大と人的資本経営への注目
近年、企業の持続的な成長を評価する上で、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)への配慮を重視するESG投資が世界的に拡大しています。特に「S」の要素である人的資本への注目度は高く、企業は従業員の育成やエンゲージメント向上への取り組みを、投資家に対して積極的に開示することが求められています。キャリアオーナーシップの推進は、まさにこの人的資本経営の中核をなす施策と言えます。
これらの背景から、キャリアオーナーシップはもはや単なる個人の課題ではなく、企業の持続的成長を左右する重要な経営戦略の一つとして位置づけられているのです。
企業がキャリアオーナーシップに取り組むメリット
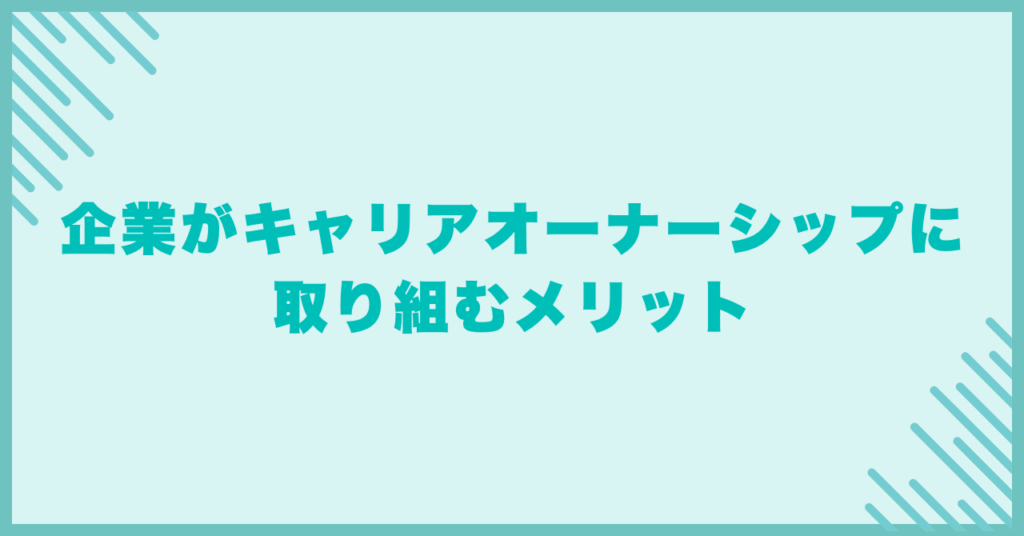
従業員のキャリアオーナーシップを尊重し、その主体的なキャリア形成を支援することは、単なる福利厚生の充実にとどまりません。それは、企業の競争力を直接的に高める戦略的な投資であり、組織に多くの具体的なメリットをもたらします。このセクションでは、企業がキャリアオーナーシップの推進に取り組むことで得られる主要なメリットを解説します。
生産性の向上と自律型人材の育成
キャリアオーナーシップが組織に根付くと、従業員は自らの業務に対して「自分ごと」として捉えるようになります。指示待ちの姿勢から脱却し、どうすればより高い成果を出せるか、どうすれば業務を改善できるかを主体的に考え、行動する「自律型人材」へと成長していくのです。このような人材が増えることで、組織全体の生産性は飛躍的に向上します 。
また、企業は従業員一人ひとりのスキルや専門性、キャリア志向をより深く理解できるようになります。これにより、個々の能力を最大限に発揮できる適材適所の人材配置が可能となり、組織のパフォーマンスを最大化させることができるでしょう。
従業員エンゲージメントとモチベーションの向上
キャリアオーナーシップを推進する過程では、1on1ミーティングやキャリア研修、キャリアカウンセリングといった施策を通じて、上司や人事部と従業員との対話の機会が必然的に増加します。このようなコミュニケーションは、従業員が自身のキャリアについて会社が真剣に考えてくれているという信頼感を育み、組織へのエンゲージメントを高める上で極めて重要です。
自らの将来のビジョンを描き、その実現に向けて会社が支援してくれる環境は、従業員の働くモチベーションを大きく向上させます。日々の業務においても、自身の成長とキャリアの目標達成につながっているという実感を持つことができ、より意欲的に仕事に取り組むようになるでしょう。
離職率の低下と優秀な人材の確保・定着
多くの従業員、特に優秀な人材ほど、自身のキャリア形成に対する意識が高い傾向にあります。キャリアの先行きが見えない、この会社で成長できる展望が描けないといった不満は、離職の大きな要因となります。キャリアオーナーシップを支援する取り組みは、従業員が社内で長期的なキャリアを築く展望を持つことを可能にし、結果として離職率の低下に大きく貢献します 。
さらに、従業員のキャリア自律を積極的に支援する企業文化は、社外に対する強力なアピールポイントとなります。キャリアアップを目指す意欲の高い優秀な人材にとって、そのような企業は非常に魅力的であり、採用競争において大きな優位性を築くことができます。人材の獲得競争が激化する現代において、これは計り知れないメリットと言えるでしょう。
キャリアオーナーシップを推進する具体的な方法
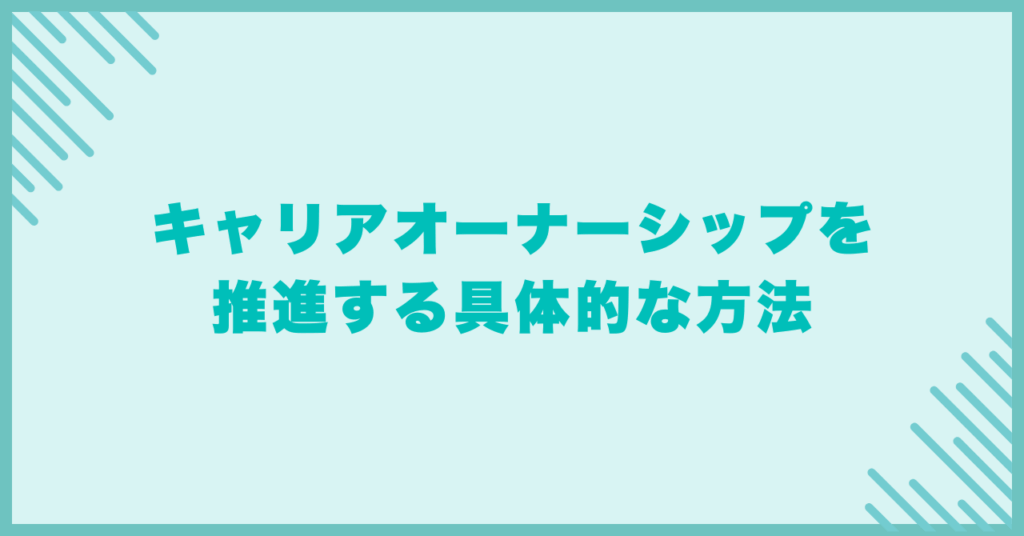
キャリアオーナーシップの重要性を理解しても、それを組織文化として根付かせるための具体的な方法が分からなければ、絵に描いた餅で終わってしまいます。このセクションでは、従業員のキャリアオーナーシップを効果的に推進するための具体的な施策を、3つの側面から解説します。
1. キャリア開発支援の仕組みを構築する
従業員が主体的にキャリアを考えるためには、まずそのための「機会」と「支援」を提供することが不可欠です。企業は、従業員が自身のキャリアについて内省し、将来のビジョンを描くための仕組みを構築する必要があります。
主な施策例:
キャリア研修
年次や役職に応じたキャリア研修を実施し、キャリアデザインの考え方や自己分析の手法、社内外のキャリアパスに関する情報を提供します。1on1ミーティング
上司と部下が定期的に1対1で対話する場を設け、業務の進捗だけでなく、中長期的なキャリアの希望や悩みについて話し合える関係性を構築します。これは、部下のキャリア志向を理解し、適切な支援を行う上で極めて有効です 。キャリアカウンセリング
国家資格を持つキャリアコンサルタントや、専門的なトレーニングを受けた社内コンサルタントによる相談窓口を設置します。客観的な第三者の視点から、従業員一人ひとりのキャリアの悩みに寄り添い、専門的な助言を提供します。
2. 挑戦と成長を促す人事制度を導入する
従業員が描いたキャリアビジョンを実現するためには、その意欲に応え、挑戦を後押しする人事制度が不可欠です。硬直的な人事制度は、従業員の主体的な行動を阻害する要因となりかねません。
主な施策例:
社内公募制度・FA(フリーエージェント)制度
部門やプロジェクトが必要とする人材を社内から公募したり、従業員が自らの意思で希望する部署へ異動を申請できる制度を導入したりすることで、従業員の挑戦意欲を喚起し、組織の活性化と人材の適材適所を促進します。ジョブ型雇用の導入
年齢や勤続年数ではなく、職務(ジョブ)の価値や難易度に基づいて評価や処遇を決定するジョブ型雇用は、従業員が専門性を高めるインセンティブとなり、キャリアオーナーシップの考え方と非常に親和性が高い制度です。成果を適切に評価する評価制度
キャリア目標の達成度や、主体的な学び・挑戦のプロセスを評価制度に組み込むことで、従業員のキャリアオーナーシップに基づいた行動を正当に評価し、さらなる成長を促します。
3. 多様な働き方を可能にする環境を整備する
キャリアオーナーシップは、社内でのキャリア形成に限定されるものではありません。社外での経験も含めて、従業員が自らのキャリアを豊かにしていくことを許容し、支援する環境が求められます。
主な施策例:
副業・兼業の解禁
副業や兼業を認めることで、従業員は社外で新たなスキルや経験、人的ネットワークを獲得する機会を得られます。そこで得た知見が本業に還元されることも期待でき、企業と従業員の双方にとってメリットがあります。学習・成長機会の提供
資格取得支援やオンライン学習プラットフォームの導入、社内ベンチャー制度など、従業員が主体的に学び、成長するための多様な機会を提供します。従業員の「学びたい」という意欲に応えることが、組織全体の学習文化を醸成し、持続的な成長につながります。
【企業事例】キャリアオーナーシップの先進的な取り組み
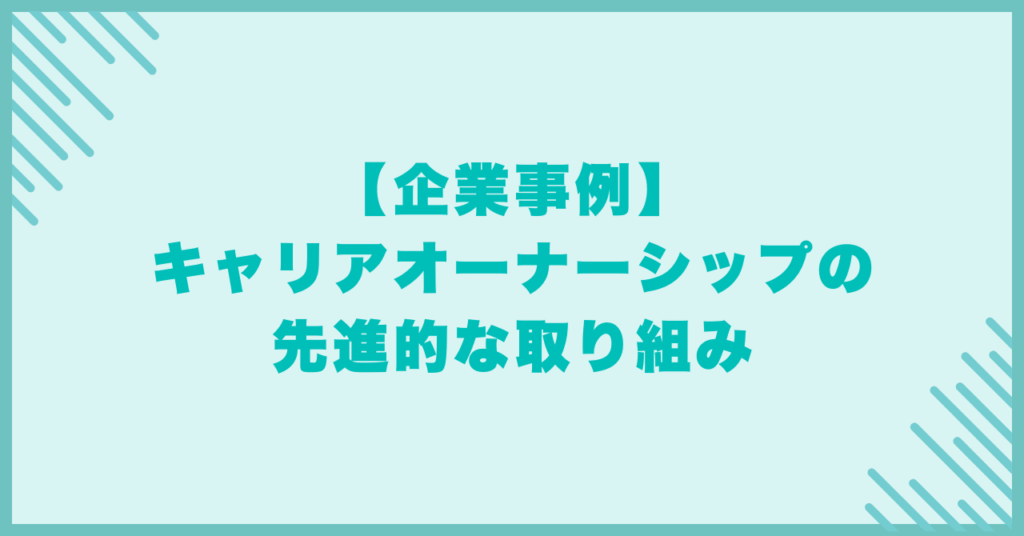
理論や方法論だけでなく、実際にキャリアオーナーシップを推進し、成果を上げている企業の事例から学ぶことは非常に有益です。ここでは、先進的な取り組みで知られる2社の事例を紹介します。
富士通株式会社:ジョブ型人材マネジメントと全社的な支援プログラム
富士通は、2022年4月から「ジョブ型人材マネジメント」を本格導入し、従業員一人ひとりの挑戦と成長を後押しする人事制度へと大きく舵を切りました。その核心となるのが、全社的なキャリア支援プログラム「FUJITSU Career Ownership Program(FCOP)」です 。
主な取り組み:
Purpose Carving
従業員一人ひとりが自身のパーパス(存在意義)を深く掘り下げ、キャリアの軸を明確にするためのワークショップ。Connect
評価制度を刷新し、上司と部下の対話を通じて成長を支援する仕組みを強化。社内ポスティング(社内公募)制度
グループ内の空きポジションを常時公開し、従業員が自らの意思で挑戦できる機会を大幅に拡大。2021年度には、国内グループ社員8万人のうち、延べ2万人がこの制度に手を挙げ、約7,800人が実際に異動を実現するなど、大きな成果を上げています。
富士通の事例は、制度の変革と同時に、従業員のマインドセット変革を促す包括的なアプローチが、キャリアオーナーシップ推進の鍵であることを示しています。
ソニーグループ:個の成長を促すカルチャーと先駆的な人事戦略
ソニーグループは、「クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす。」というPurpose(存在意義)のもと、「Special you, Diverse Sony」という人材理念を掲げています。これは、多様な「個」の成長の総和がグループ全体の成長につながるという考え方であり、キャリアオーナーシップの精神と深く共鳴するものです 。
主な取り組み:
3つの人事戦略の軸
「個を求む」「個を伸ばす」「個を活かす」という3つの軸に基づき、採用から育成、配置に至るまで、個の主体性を尊重する人事戦略を体系化しています。社内募集制度
1966年という早い段階から導入され、50年以上にわたって運用されているこの制度は、日本における社内公募の先駆けとも言える取り組みです。従業員が自らのキャリアを主体的に選択できる企業文化が、長年にわたって培われてきました。
ソニーグループの事例から学べるのは、制度だけでなく、企業の根幹にあるフィロソフィーやカルチャーが、従業員のキャリアオーナーシップを育む上でいかに重要であるかという点です。個の力を信じ、その成長を最大限に支援する姿勢が、イノベーションを生み出し続ける原動力となっています。
まとめ
本記事では、キャリアオーナーシップの基本的な概念から、企業がその推進に取り組むメリット、具体的な方法、そして先進企業の事例に至るまでを解説してきました。変化の激しい時代において、従業員一人ひとりが自らのキャリアに責任を持ち、主体的に行動するキャリアオーナーシップは、もはや一部の意識の高い従業員だけのものではありません。それは、企業の持続的な成長と競争力強化に不可欠な、全社で取り組むべき経営戦略です。
キャリアオーナーシップの推進を成功させるためには、制度を導入するだけでなく、それが従業員に活用され、組織文化として根付くことが重要です。そのためには、経営層からの強力なコミットメント、管理職の意識改革と部下への支援、そして何よりも、従業員一人ひとりが安心してキャリアについて考え、挑戦できる心理的安全性の高い環境づくりが求められます。
人事担当者の皆様には、本記事で紹介した情報を参考に、自社の現状と課題に合わせた形で、キャリアオーナーシップを推進する施策を企画・実行していただきたいと思います。それは、従業員の成長を支援し、エンゲージメントを高めるだけでなく、企業の未来を創造する力強い原動力となるはずです。

「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe
Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界1300名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス
⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス
⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス
などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。
