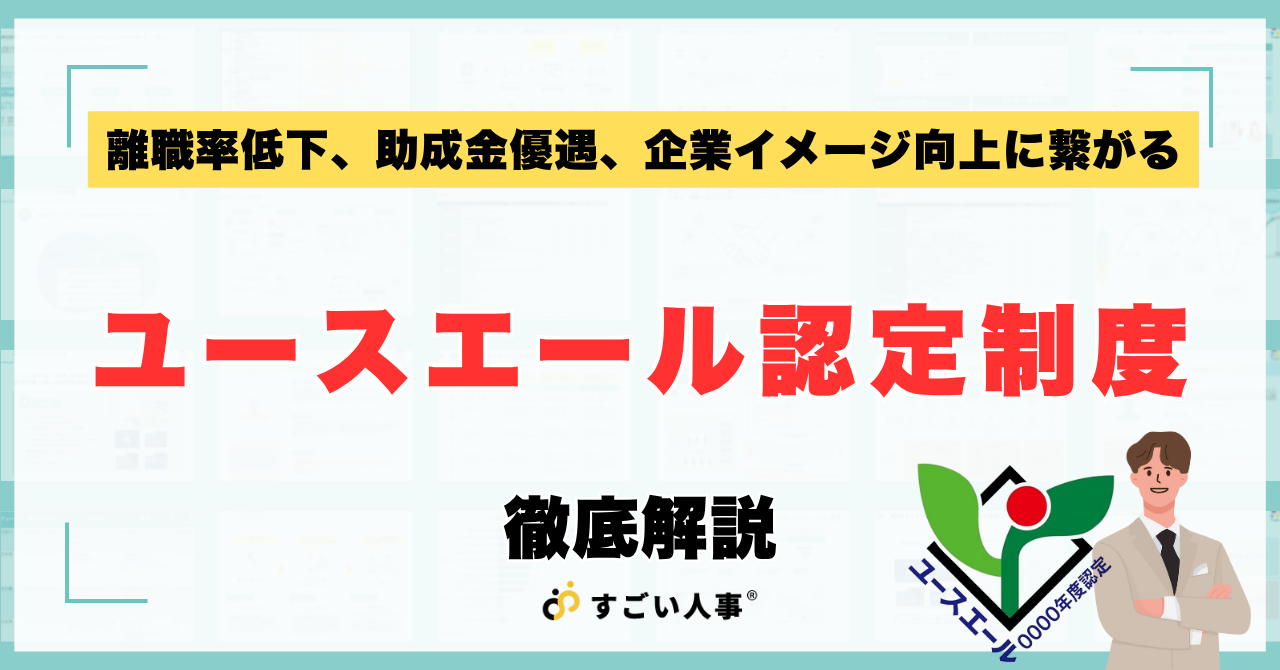
ユースエール認定制度とは?メリット・デメリット、認定基準を徹底解説
少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少が深刻化する日本において、若手人材の確保と定着は、企業の持続的な成長を左右する最重要課題の一つです。1995年に8,726万人だった生産年齢人口は、2024年10月時点で7,372万8,000人へと大きく減少しました。さらに、新規大卒就職者の3年以内離職率が34.9%と過去16年で最高を記録するなど、採用した若者の早期離職も企業にとって大きな悩みとなっています。
このような厳しい採用市場において、多くの経営者や人事担当者が注目しているのが、厚生労働省が所管する「ユースエール認定制度」です。この制度は、若者の採用・育成に積極的で、雇用管理が優良な中小企業を国が認定し、支援する仕組みです。単なる「お墨付き」に留まらず、採用力の強化、企業ブランディングの確立、そして経営基盤の安定化に直結する、数多くのメリットをもたらします。
本記事では、ユースエール認定制度の全体像を網羅的に解説します。認定基準の詳細から、企業が得られる具体的なメリット、そして申請における注意点やデメリットまで、経営者や人事担当者が本当に知りたい情報を、最新のデータを交えながら1万字で徹底的に掘り下げていきます。
目次
- ユースエール認定制度の基本
- 【企業側の本音】ユースエール認定を取得する5つの絶大なメリット
- 取得前に知るべきデメリットと注意点
- 【完全ガイド】ユースエール認定の全12要件を徹底解説
- 申請から認定までのロードマップ
- まとめ
ユースエール認定制度の基本
まずは、ユースエール認定制度がどのような制度なのか、その基本的な枠組みから見ていきましょう。
制度の目的:若者の雇用促進と中小企業の成長支援
ユースエール認定制度は、「若者雇用促進法(青少年の雇用の促進等に関する法律)」に基づき、若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を厚生労働大臣が認定する制度です。
若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を厚生労働大臣が認定する制度です。 認定を受けることで、様々な支援を受けることができます。
この制度の根底には、若者が安心して働き、その能力を十分に発揮できる環境を整備すること、そして、それを通じて中小企業の魅力を高め、その成長を後押しするという二つの大きな目的があります。
認定対象となる企業:常時雇用労働者300人以下の中小企業
ユースエール認定の対象となるのは、常時雇用する労働者が300人以下の「中小企業」です。大企業は対象外となっており、あくまで若者の雇用環境改善に取り組む中小企業を支援するための制度であることが特徴です。
ユースエール認定の現状:認定企業数と社会的な認知度
2015年にスタートした本制度は、年々その認知度を高めています。帝国データバンクの調査によると、2025年5月26日時点で、全国で1,481社がユースエール認定企業として認定されています。
これは、多くの企業が制度のメリットを認識し、厳しい認定基準をクリアするために労働環境の改善に努めていることの表れと言えるでしょう。今後、学生や求職者の間での認知度がさらに高まることで、認定の価値はますます向上していくと予想されます。
【企業側の本音】ユースエール認定を取得する5つの絶大なメリット
ユースエール認定は、単なる企業の社会的責任(CSR)活動の一環ではありません。採用、ブランディング、財務、組織開発といった企業経営の根幹に関わる、具体的かつ強力なメリットをもたらします。ここでは、企業が享受できる5つの絶大なメリットを、具体的な支援内容と共に詳しく解説します。
メリット1:採用競争力の劇的な向上
若手人材の獲得競争が激化する中で、ユースエール認定は他社との差別化を図る強力な武器となります。国が「若者にとって働きやすい優良企業」とお墨付きを与えたことで、求職者に対して絶大なアピール効果を発揮します。
具体的な支援策として、以下のようなものが挙げられます。
ハローワーク等での重点的なPR
「わかものハローワーク」や「新卒応援ハローワーク」といった若者専門の就職支援窓口で、認定企業の求人が優先的に紹介されます。これにより、自社に関心を持っていなかった層にもアプローチでき、応募者数の増加が期待できます。
認定企業限定の就職面接会への参加
各都道府県の労働局やハローワークが主催する、認定企業だけが参加できる就職面接会に参加できます。就職意欲の高い優秀な若手人材と直接出会える貴重な機会です。
「若者雇用促進総合サイト」での企業情報発信
厚生労働省が運営する「若者雇用促進総合サイト」に、認定企業として企業情報やPRシートが掲載されます。求職者はこのサイトを通じて、企業の詳細な情報を得ることができ、企業理解の促進と応募動機の形成につながります。
メリット2:企業イメージとブランド価値の向上
ユースエール認定は、企業の社会的信用力を大きく向上させます。認定の証である「ユースエール認定マーク」は、自社のウェブサイトやパンフレット、商品、広告などに使用することができ、「国が認めたホワイト企業」であることを内外に示すことができます。
厚生労働省が認定する公的な制度であるため、社会的信用力が高まります。ホームページや会社案内に「ユースエール認定企業」と記載することで、企業ブランディングにもつながります。
これにより、求職者だけでなく、取引先や金融機関、そして顧客からの信頼も獲得しやすくなり、企業全体のブランド価値向上に貢献します。
メリット3:経済的支援:助成金の加算や低利融資
認定企業は、国からの直接的な経済的支援も受けることができます。これは、労働環境改善への投資を後押しする重要なインセンティブです。
各種助成金の優遇措置
人材開発や処遇改善に関する様々な助成金において、支給額が加算されたり、申請要件が緩和されたりする優遇措置があります。例えば、「キャリアアップ助成金」や「人材開発支援助成金」などが対象となります。
日本政策金融公庫による低金利融資制度
働き方改革に取り組む企業を支援する「働き方改革推進支援資金(企業活力強化貸付)」において、通常よりも低い金利での融資が受けられます。ユースエール認定企業は、基準利率からマイナス0.65%という大幅な優遇が適用されます。
メリット4:公共調達(入札)での加点評価
国や地方自治体が行う公共事業の入札において、ユースエール認定企業は加点評価の対象となります。これにより、価格競争だけでなく、企業の社会的な取り組みも評価されるため、受注機会の拡大につながります。特に、公共事業を主要な収益源の一つとしている企業にとっては、極めて大きなメリットと言えるでしょう。
メリット5:社内環境の改善と従業員の定着率向上
ユースエール認定を取得する過程そのものが、企業にとって大きな価値を持ちます。認定基準をクリアするためには、自社の労働時間、休暇制度、人材育成体制などを根本から見直す必要があります。このプロセスを通じて、従業員にとってより働きやすい環境が整備され、結果として従業員のエンゲージメントや満足度が向上します。
外部からの認定を受けることで、社内の労働環境整備が進み、社員の満足度やモチベーションが向上する好循環が期待できます。
働きやすい環境は、従業員の定着率向上に直結します。採用コストの削減だけでなく、知識やスキルの社内蓄積が進み、中長期的な企業競争力の強化に繋がるのです。
取得前に知るべきデメリットと注意点
多くのメリットがある一方で、ユースエール認定の取得と維持には、相応の努力とコストが伴います。安易な気持ちで申請を進める前に、企業が直面しうるデメリットや注意点を正確に理解しておくことが不可欠です。
デメリット1:認定基準のハードルが高い
ユースエール認定の最大のハードルは、その厳格な認定基準です。特に、以下の項目は多くの企業にとって高い壁となる可能性があります。
離職率: 直近3事業年度の新卒者などの離職率が20%以下であること。
労働時間: 前事業年度の正社員の月平均所定外労働時間が20時間以下、かつ法定時間外労働60時間以上の正社員が一人もいないこと。
有給休暇取得率: 前事業年度の正社員の有給休暇取得率が平均70%以上、または年間取得日数が平均10日以上であること。
これらの基準を達成するためには、付け焼き刃の対策では不十分です。全社的な働き方改革や、労働環境の根本的な見直しが求められるケースも少なくありません。
ユースエール認定を受けるには、離職率、残業時間、有給取得率など厳格な基準をクリアする必要があります。業種によってはこの要件を満たすのが難しい場合もあり、社内体制の見直しや改革が必要になるケースがあります。
デメリット2:申請手続きと書類作成の煩雑さ
認定を申請する際には、多岐にわたる書類の提出が求められます。労働関係法令の遵守状況を証明する書類や、過去の採用・離職データ、労働時間や休暇取得に関する実績報告書など、その内容は非常に詳細です。
これらの書類を正確に準備するには、相応の手間と時間がかかります。特に、人事労務に関する専門知識が不足している中小企業にとっては、申請準備自体が大きな負担となる可能性があります。そのため、社会保険労務士などの専門家のサポートを受けることも有効な選択肢となります。
デメリット3:認定後の継続的な維持管理
ユースエール認定は、一度取得すれば永続的に有効なわけではありません。認定を維持するためには、毎年1回、事業の状況を報告し、認定基準を満たし続けているかどうかの確認を受ける必要があります。
万が一、基準を満たせなくなったり、報告を怠ったりした場合には、認定が取り消されることもあります。認定の維持には、継続的な労働環境改善への取り組みと、適切な管理体制が不可欠であることを肝に銘じておく必要があります。
【完全ガイド】ユースエール認定の全12要件を徹底解説
ユースエール認定を取得するためには、厚生労働省が定める12の要件をすべて満たす必要があります。これらの要件は、企業の基本的な姿勢から、労働環境、人材育成、法令遵守に至るまで、多岐にわたります。ここでは、各要件をカテゴリーに分け、一つひとつ詳しく見ていきましょう。
前提となる基本要件
まず、認定の対象となるための基本的な前提条件です。
学卒求人等の実施
ハローワークや民間の職業紹介事業者などを通じて、若者(おおむね35歳未満)を対象とした正社員の求人を提出または募集していることが必要です。
若者の採用・育成への積極性
若者の採用または人材育成に積極的に取り組む企業であることが求められます。これは、後述する人材育成方針の策定などによって示されます。
実績要件:離職率・労働時間・休暇
ここが最もハードルが高いとされる、具体的な数値目標を含む要件です。企業の「働きやすさ」が客観的なデータで評価されます。
| 要件項目 | 基準 |
| 新卒等離職率 | 直近3事業年度に正社員として就職した新卒者等の離職率が20%以下であること。 |
| 時間外労働 | 前事業年度の正社員の月平均所定外労働時間が20時間以下、かつ、月平均の法定時間外労働60時間以上の正社員が一人もいないこと。 |
| 有給休暇取得 | 前事業年度の正社員の年次有給休暇の付与日数に対する取得率が平均70%以上、または年間取得日数が平均10日以上であること。 |
これらの基準は、単に法令を遵守するだけでなく、従業員のワークライフバランスに配慮した、高いレベルの労働環境が求められていることを示しています。
体制要件:人材育成と育児休業
従業員のキャリア形成支援と、家庭との両立支援に関する体制も重要な評価項目です。
人材育成方針・教育訓練計画の策定
従業員の能力開発に関する方針と、それに基づいた具体的な教育訓練計画を策定し、実施している必要があります。
育児休業の取得実績
直近3事業年度において、男性労働者の育児休業等取得者が1人以上いること、または女性労働者の育児休業等取得率が75%以上であることが求められます。
コンプライアンスと情報公開に関する要件
企業の信頼性を示す、法令遵守と透明性に関する要件です。
雇用情報の公表
若者雇用促進法に基づき、以下の3つのカテゴリーに関する情報を公表している必要があります。
1.募集・採用に関する状況
直近3事業年度の採用者数・離職者数、男女別採用者数、平均継続勤務年数など。
2.職業能力の開発・向上に関する状況
研修内容、メンター制度の有無、自己啓発支援制度の有無とその内容など。
3.企業における雇用管理に関する状況
月平均の所定外労働時間、有給休暇の平均取得日数、育児休業取得実績、役員・管理職の女性割合など。
その他の法令遵守等
以下の項目に一つも該当しないことが求められます。
・過去に認定を取り消されている(取消日から3年以上経過していない)
・過去3年間に新規学卒者の採用内定取消しを行っている
・過去1年間に事業主都合の解雇または退職勧奨を行っている
・暴力団関係事業主である
・風俗営業等関係事業主である
・雇用関係助成金の不支給措置を受けている
・重大な労働関係法令違反を行っている
申請から認定までのロードマップ
ユースエール認定を取得するためには、計画的な準備と正確な手続きが不可欠です。ここでは、申請を決意してから認定を受けるまでの具体的なステップを4段階に分けて解説します。
Step1:自社の現状把握と要件確認
最初のステップは、自社が12の認定要件をどの程度満たしているかを客観的に把握することです。特に、離職率、労働時間、有給休暇取得率といった実績要件は、過去のデータを正確に集計する必要があります。
厚生労働省は、認定基準を満たしているかを手軽にチェックできる「ユースエール認定到達度診断」をオンラインで提供しています。まずはこの診断ツールを活用し、自社の現在地を確認することから始めましょう。診断結果を基に、どの項目が基準をクリアしており、どの項目に課題があるのかを明確にします。
Step2:必要書類の準備と作成
次に、申請に必要な書類を準備します。提出書類は多岐にわたるため、漏れがないように注意深く進める必要があります。主な提出書類は以下の通りです。
・基準適合事業主認定申請書(様式第1号)
・新規学卒者等採用実績及び定着状況報告書
・人材育成方針・教育訓練計画報告書
・労働時間等実績報告書
・有給休暇等取得実績報告書
・育児休業等取得実績報告書
・関係法令遵守状況報告書
・誓約書
・企業情報報告書
これらの様式に加え、就業規則、賃金台帳、タイムカード、労働者名簿など、報告内容を証明するための添付書類も必要となります。書類の準備には時間がかかるため、余裕を持ったスケジュールを組むことが重要です。
Step3:都道府県労働局への申請
すべての書類が整ったら、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局に申請します [1]。申請は、窓口への持参または郵送で行います。また、一部の手続きは、政府の電子申請システム「e-Gov」を利用してオンラインで行うことも可能です。
申請手続きは、管轄のハローワークを経由して行うこともできる場合がありますので、事前に最寄りのハローワークに相談してみるのも良いでしょう。
Step4:審査と認定
提出された書類に基づき、都道府県労働局で審査が行われます。書類に不備がなければ、審査を経て、後日、認定通知書が交付されます。晴れて「ユースエール認定企業」の誕生です。
前述の通り、認定は永続的なものではなく、毎年1回、状況報告を行う必要があります。認定を維持するためにも、継続的な労働環境の改善に努めましょう。
まとめ
本記事では、ユースエール認定制度について、その概要からメリット・デメリット、そして具体的な認定基準や申請プロセスに至るまで、多角的に解説してきました。
厳しい認定基準や煩雑な申請手続きなど、取得に向けたハードルは決して低くはありません。しかし、それらを乗り越えて認定を取得した先には、採用力の強化、企業ブランドの向上、経済的な支援、そして何よりも従業員が誇りを持って働ける組織風土の醸成といった、計り知れない価値が待っています。
ユースエール認定への挑戦は、単なる「お墨付き」を得るための活動ではなく、自社の労働環境と経営体制を根本から見つめ直し、未来に向けて持続可能な成長を遂げるための「投資」そのものです。若手人材と共に成長し、社会から選ばれ続ける企業となるために、その第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
認定取得に向けて、具体的な進め方や自社の課題について専門的なアドバイスが必要な場合は、社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。客観的な視点からの助言は、認定取得への道のりをより確かなものにしてくれるはずです。
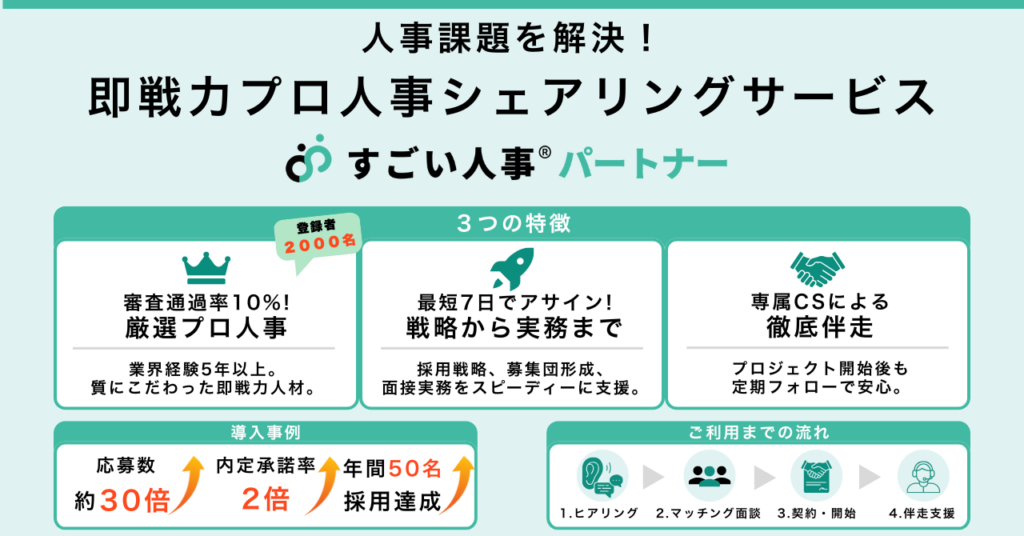
「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe
Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界2,000名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス
⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス
⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス
などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。
