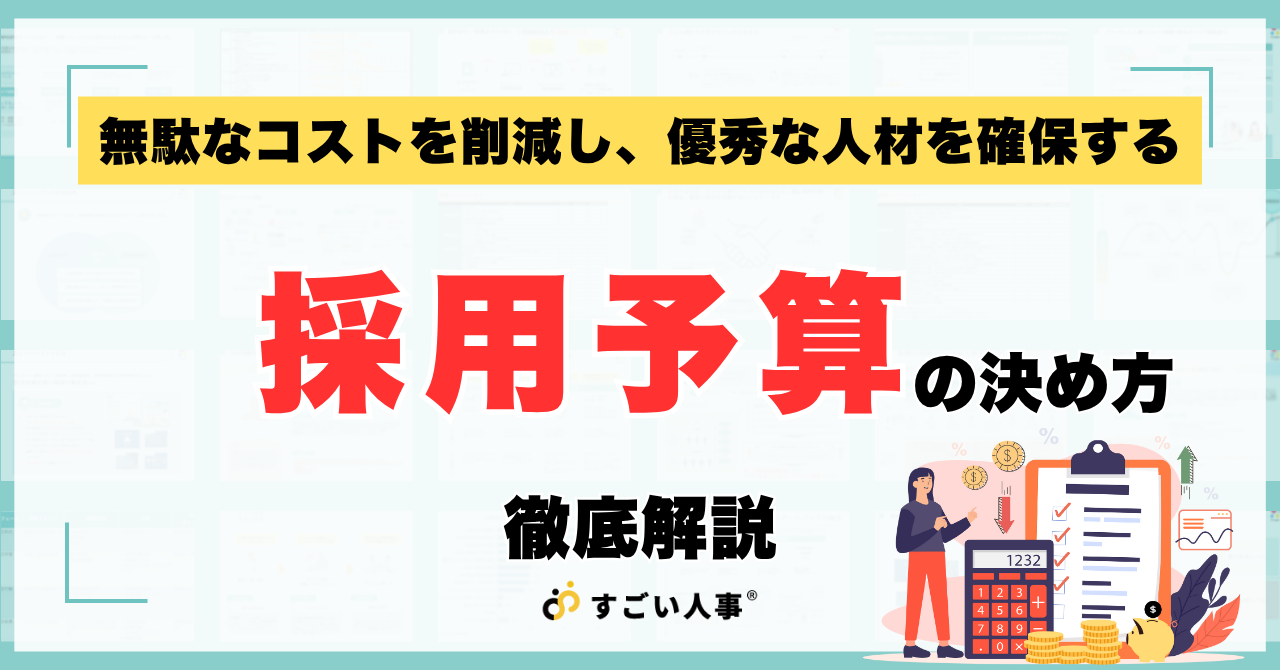
採用予算の決め方|効果的な採用戦略とコストを最適化する方法を徹底解説
現代のビジネス環境において、人材は企業の最も重要な資産であり、その獲得競争はますます激化しています。少子高齢化に伴う労働力人口の減少や、DX化の進展による専門人材の需要増など、企業を取り巻く採用市場は大きな変革期を迎えています。このような状況下で、採用活動はもはや単なる「欠員補充」の作業ではありません。企業の持続的な成長を支えるための「戦略的投資」として、その重要性はかつてないほど高まっています。
しかし、投資である以上、そこには明確な戦略と計画が不可欠です。特に、採用活動の根幹をなす「採用予算」の策定は、その成否を大きく左右します。場当たり的な予算設定は、貴重な経営資源の無駄遣いにつながるだけでなく、採用機会の損失や、採用の質の低下を招きかねません。一方で、戦略的に策定された採用予算は、コストを最適化し、費用対効果を最大化することで、企業に最適な人材をもたらし、事業成長の強力なエンジンとなります。
本記事では、人事担当者および経営者の皆様を対象に、効果的な採用戦略を実現するための「採用予算の決め方」を徹底的に解説します。採用予算の基本的な考え方から、具体的な立て方、コスト最適化の手法、そして効果測定まで、データに基づいた実践的なノウハウを提供します。この記事を通じて、貴社の採用活動を成功に導き、未来の成長を確固たるものにするための一助となれば幸いです。
目次
- 採用予算とは?基本の考え方と構成要素
- 【5ステップで解説】戦略的な採用予算の立て方
- 【2025年最新データ】採用コストの平均相場
- 採用コストを最適化する7つの具体的戦略
- 効果測定と改善|データドリブンな採用活動の実現
- まとめ
採用予算とは?基本の考え方と構成要素
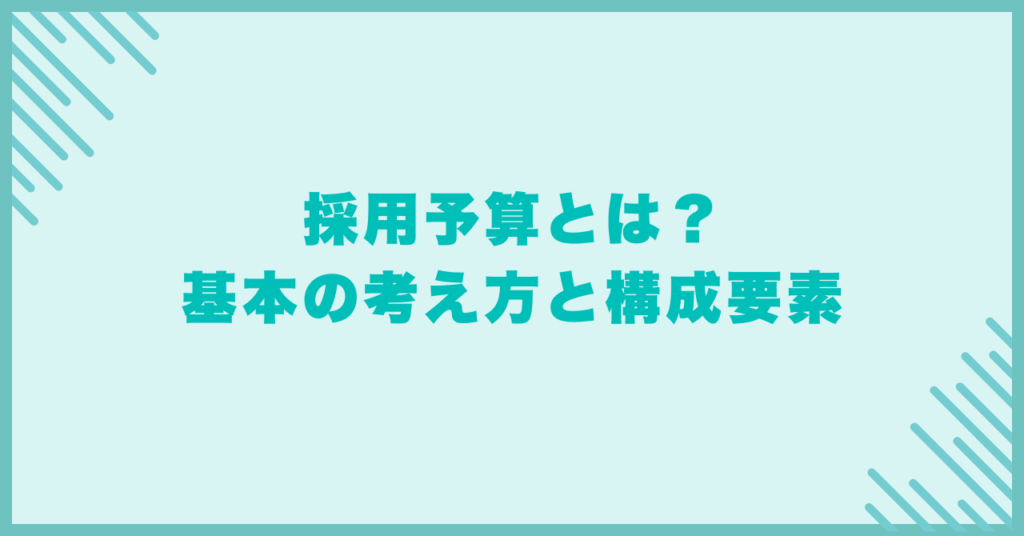
採用予算とは、企業が新たな人材を獲得するために計画する、年間の費用総額を指します。これには、求人広告の出稿から内定者のフォローアップに至るまで、採用活動の全プロセスで発生するあらゆるコストが含まれます。適切な採用予算の設定は、企業の財務状況を健全に保ちつつ、事業計画に必要な人材を確保するための羅針盤となる、極めて重要な経営指標です。
採用予算の定義と経営における重要性
採用予算は、単なる経費の枠組みではありません。企業の成長戦略を実現するための「投資計画」そのものです。予算が過剰であれば、企業の利益率を圧迫し、他の重要な事業投資の機会を奪うことになりかねません。逆に、予算が過小であれば、優秀な人材を獲得するための競争で後れを取り、事業の停滞や衰退を招くリスクがあります。したがって、自社の経営戦略と事業計画に深く根ざした、戦略的かつ適正な予算を策定することが、持続的な企業成長の鍵となります。
採用活動にかかる「内部コスト」の内訳
採用コストは、大きく「内部コスト」と「外部コスト」に分類されます。内部コストとは、採用活動を遂行するために社内で発生する費用のことで、主に人件費に関連するものが中心です。これらのコストは、直接的な支出として見えにくいため、予算策定の際には意識的に洗い出す必要があります。
| 内部コストの主な項目 | 説明 |
| 採用担当者の人件費 | 採用計画の策定、母集団形成、選考、内定者フォローなど、採用業務に関わる担当者の給与や賞与。 |
| 面接官の人件費 | 現場の管理職や社員が面接に費やす時間に対する人件費。 |
| リファラル採用の報酬 | 社員紹介制度を通じて人材を紹介してくれた社員へ支払うインセンティブ。 |
| 応募者への交通費 | 遠方からの応募者に対して、面接参加のために支給する交通費や宿泊費。 |
| 内定者フォローの費用 | 内定者懇親会や研修、コミュニケーションツールなど、内定辞退を防ぐための費用。 |
外部の採用サービスにかかる「外部コスト」の内訳
外部コストは、採用活動を外部のサービスや専門家の支援を得て進める際に発生する費用です。こちらは直接的な支払いとして明確に把握しやすく、予算管理の中心となります。どのサービスを選択し、どのように組み合わせるかが、採用の費用対効果を大きく左右します。
| 外部コストの主な項目 | 説明 |
| 求人広告費 | 求人サイトや求人情報誌、Web広告など、求人情報を掲載するための費用。 |
| 人材紹介サービス手数料 | 人材紹介会社(エージェント)を通じて人材を採用した場合に支払う成功報酬。 |
| 採用イベント出展費 | 合同企業説明会や転職フェアなど、採用イベントに参加するための費用。 |
| 採用関連ツールの利用料 | 採用管理システム(ATS)やオンライン面接ツール、適性検査ツールなどの月額・年額利用料。 |
| 採用アウトソーシング費用 | 採用業務の一部または全部を外部の専門企業に委託(RPO)する場合の費用。 |
| 採用サイト・コンテンツ制作費 | 採用サイトの構築やリニューアル、会社紹介パンフレットや動画などの制作を外部に依頼した場合の費用。 |
【5ステップで解説】戦略的な採用予算の立て方
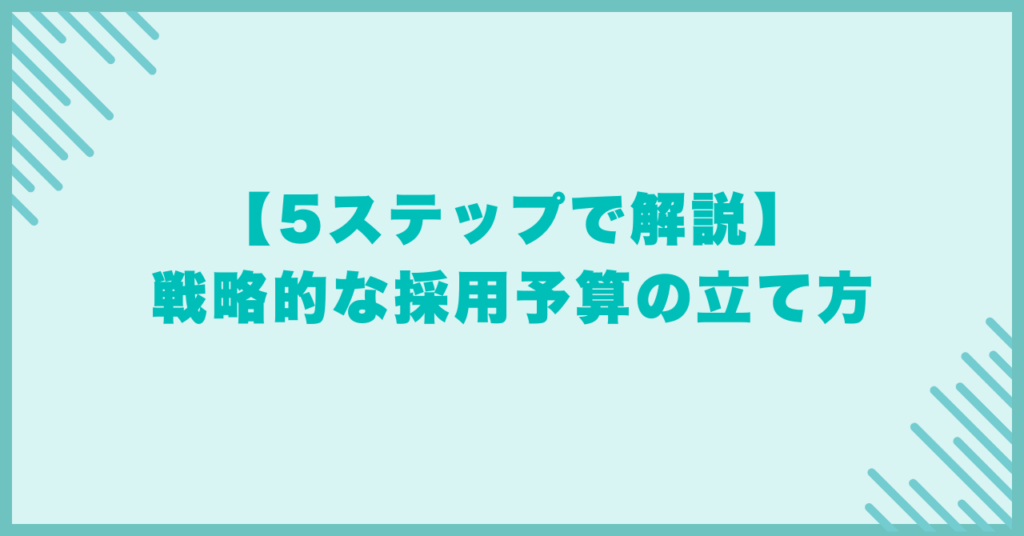
効果的な採用活動は、緻密な予算計画から始まります。ここでは、経営戦略と連動し、データに基づいた意思決定を可能にするための、戦略的な採用予算の立て方を5つのステップで具体的に解説します。
ステップ1:経営戦略と連動した採用目標を設定する
採用予算策定の第一歩は、経営目標や事業計画に基づいた明確な採用目標を設定することです。単に「何人採用するか」だけでなく、「どの部門に、どのようなスキルや経験を持つ人材を、いつまでに、どれくらいの役職レベルで採用する必要があるのか」を具体的に定義します。この目標が曖昧では、その後の予算計画全体の精度が低下してしまいます。市場の需要と供給のバランスも考慮に入れ、現実的かつ挑戦的な目標を設定することが重要です。
ステップ2:過去のデータから採用単価を算出する
次に、過去の採用実績データを分析し、「1人あたりの採用単価」を算出します。採用単価は、以下の計算式で求めることができます。
採用単価 = 採用コスト総額(内部コスト + 外部コスト) ÷ 採用人数
過去のデータを職種別、採用チャネル別などに細分化して分析することで、より精度の高い単価を把握できます。もし自社に十分なデータが蓄積されていない場合は、後述する業界の平均相場や、同業他社のベンチマークデータを参考にすると良いでしょう。この採用単価が、次年度の予算を見積もる上での基礎となります。
ステップ3:採用チャネル別の費用対効果を分析・選定する
採用活動には、求人広告、人材紹介、ダイレクトリクルーティング、リファラル採用など、多様なチャネルが存在します。それぞれのチャネルについて、過去の実績から「応募数」「書類通過率」「面接通過率」「内定承諾率」といった指標を分析し、費用対効果を評価します。どのチャネルが自社の求める人材に対して最も効率的かを見極め、次年度の予算を重点的に投下するチャネルを選定します。全てのチャネルを漫然と利用するのではなく、データに基づいた「選択と集中」がコスト最適化の鍵です。
ステップ4:ROI(投資対効果)を最大化する予算を配分する
採用は投資であり、その効果はROI(Return on Investment)で測るべきです。採用におけるROIは、採用した人材が将来的に企業にもたらす価値(生産性向上、事業貢献など)を、採用に要したコストで割ることで算出されます。短期的な採用単価の抑制だけに目を向けるのではなく、長期的な視点で企業の成長に貢献する人材をいかに効率的に獲得できるか、という観点から予算を配分することが不可欠です。例えば、採用単価は高くとも、入社後の定着率や活躍度が高いチャネルへの投資を厚くするといった判断が求められます。
ステップ5:予備費を設定し、市場の変動に備える
採用市場は常に変動しており、予期せぬ事態が発生する可能性があります。例えば、競合の採用激化による採用単価の高騰、急な退職者発生による追加採用の必要性などが考えられます。こうした不測の事態に柔軟に対応できるよう、全体の予算に対して一定割合(例:10〜15%程度)の予備費を確保しておくことを推奨します。これにより、計画の硬直化を防ぎ、年間を通じて安定した採用活動を継続することが可能になります。
【2025年最新データ】採用コストの平均相場
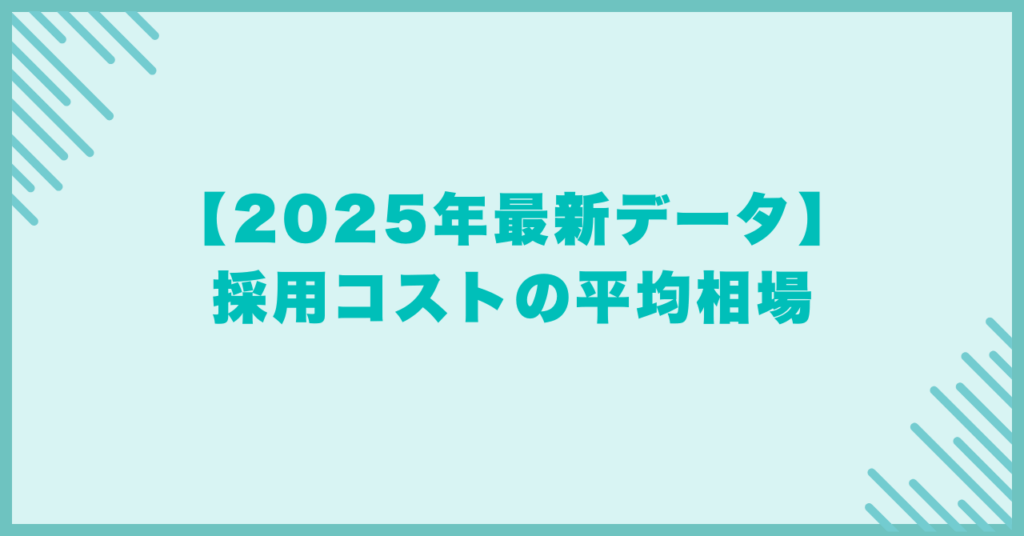
自社の採用予算が適正な水準にあるかを判断するためには、市場の平均相場を把握しておくことが不可欠です。ここでは、近年の調査データを基に、採用コストの平均相場を「雇用形態別」「企業規模別」「業種別」に解説します。ただし、これらの数値はあくまで目安であり、個別の採用要件や市場環境によって変動する点にご留意ください。
【雇用形態別】新卒・中途採用の平均採用単価
一般的に、即戦力を求める中途採用は、ポテンシャルを重視する新卒採用に比べて採用単価が高くなる傾向があります。それぞれの平均的な採用単価は以下の通りです。
| 雇用形態 | 1人あたりの平均採用単価 |
| 新卒採用 | 約93.6万円 |
| 中途採用 | 約103.3万円 |
特に、専門性の高いスキルを持つ人材や、管理職クラスの人材を採用する場合には、採用競争が激しいため、単価はさらに上昇する傾向にあります。
【企業規模別】年間採用費用の比較
企業の規模によっても、年間の採用費用総額は大きく異なります。当然ながら、企業規模が大きくなるほど採用人数も増えるため、費用総額は増加します。ただし、1人あたりの採用単価で見ると、スケールメリットを活かして中小企業よりも低く抑えられているケースも少なくありません。
| 従業員規模 | 中途採用の年間平均費用(2024年実績) |
| 3~50名 | 119.3万円 |
| 51~300名 | 247.3万円 |
| 301~1,000名 | 564.9万円 |
| 1,001名以上 | 1,461.8万円 |
【業種別】採用が激化する業界のコスト動向
人手不足が深刻な業界や、人材獲得競争が激しい業界では、採用コストが高騰する傾向が見られます。特に、IT・通信業界や運輸・物流業界では、その傾向が顕著です。
| 業種 | 中途採用の年間平均費用(2024年実績) |
| IT・通信・インターネット | 694.9万円 |
| メーカー | 853.8万円 |
| 運輸・交通・物流・倉庫 | 1,459.6万円 |
| 流通・小売・フードサービス | 303.8万円 |
これらのデータから、自社が属する業界の特性を理解し、競争環境に応じた予算戦略を立てることが重要であるとわかります。
採用コストを最適化する7つの具体的戦略
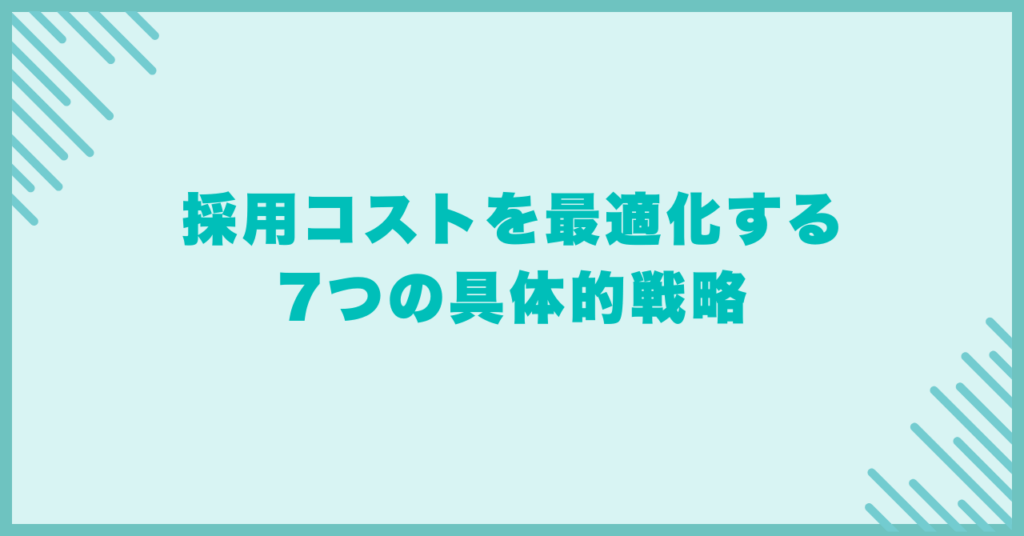
採用予算を効果的に活用し、費用対効果を最大化するためには、コストを戦略的に「最適化」する視点が不可欠です。単なる経費削減ではなく、採用の質を維持・向上させながら無駄をなくしていくための、7つの具体的な戦略を紹介します。
1. 採用ミスマッチの防止|アセスメントツールで定着率向上
採用コストにおける最大の無駄は、採用した人材が早期に離職してしまうことです。再採用にかかるコストだけでなく、教育研修にかけた費用や時間も水の泡となります。これを防ぐためには、スキルや経験だけでなく、候補者の価値観や行動特性が自社のカルチャーに適合するかどうかを、選考段階で的確に見極めることが重要です。客観的なデータに基づいて相性を可視化できる「アセスメントツール」の活用は、採用ミスマッチを科学的に防止し、入社後の定着率と活躍度を高める上で非常に有効な手段です。[3]
2. リファラル採用・アルムナイ採用の強化|質の高い人材を低コストで
リファラル採用(社員紹介)やアルムナイ採用(退職者の再雇用)は、質の高い人材を比較的低コストで獲得できる、費用対効果の優れた採用手法です。紹介者を通じて事前にリアルな企業情報が伝わるため、候補者の理解度が高く、カルチャーフィットしやすい傾向があります。また、求人広告費や人材紹介手数料といった高額な外部コストがかからない点も大きなメリットです。これらの制度を活性化させるためのインセンティブ設計や、退職者との継続的な関係構築に投資することは、長期的に見て大きなコスト削減につながります。[3]
3. 採用チャネルの最適化|データに基づいた選択と集中
前述の通り、採用チャネルはそれぞれに特徴があり、費用も様々です。全てのチャネルを漫然と利用するのではなく、自社の採用ターゲットに対して最も効果的なチャネルはどれか、過去のデータを分析して見極めることが重要です。「応募単価」「採用単価」「内定承諾率」などの指標で各チャネルを評価し、成果の出ているチャネルに予算を集中させる「選択と集中」を徹底しましょう。また、採用人数が多い場合は、採用数が増えてもコストが一定の「定額制サービス」を利用することも、予算管理を容易にし、単価を抑制する上で有効です。
4. 選考プロセスの効率化|オンライン面接と工数削減
選考プロセスが長期化・複雑化すると、面接官の人件費や会場費といった内部コストが増大するだけでなく、候補者の離脱リスクも高まります。不要な選考ステップはないか、意思決定のスピードは遅くないかを見直し、プロセスを可能な限り短縮・効率化しましょう。特に、一次面接をオンラインで実施することは、遠方の候補者にもアプローチしやすくなる上、面接官の移動時間や交通費を削減できるため、双方にとってメリットの大きい施策です。
5. 公的助成金の活用|返済不要の資金でコストを抑制
国や地方自治体は、企業の雇用促進を支援するために、様々な助成金制度を設けています。例えば、特定の条件を満たす人材(若者、女性、高齢者、障害者など)を採用した場合や、非正規雇用労働者を正規雇用に転換した場合などに、返済不要の助成金が支給されることがあります。これらの制度を積極的に活用することで、採用コストを大幅に抑制することが可能です。厚生労働省のウェブサイトなどで、自社が利用できる助成金がないか、定期的に確認することをお勧めします。
6. 採用マーケティングの推進|自社の魅力を発信し母集団を形成
求人広告や人材紹介といった「待ち」の採用手法だけに頼るのではなく、自社から積極的に情報を発信し、潜在的な候補者との関係を構築する「採用マーケティング」の視点が重要です。オウンドメディア(自社ブログや採用サイト)やSNSを通じて、事業の魅力、働く環境、社員の姿などを継続的に発信することで、広告費をかけずに自社に興味を持つ「母集団」を形成することができます。これは中長期的な取り組みになりますが、企業のブランディングにも繋がり、持続可能な採用力の構築に貢献します。
7. 外部人材の活用|固定費を変動費化し、リスクを軽減
全ての業務を正社員で賄うのではなく、一部の専門的な業務や、繁閑の差が激しい業務については、フリーランスや業務委託といった外部人材を柔軟に活用することも有効な選択肢です。これにより、人件費という固定費を、必要な時に必要な分だけ支払う「変動費」としてコントロールできるようになり、経営リスクを軽減できます。正社員採用に固執せず、業務内容に応じて最適な雇用形態を組み合わせることで、組織全体の生産性とコスト効率を高めることが可能です。
効果測定と改善|データドリブンな採用活動の実現
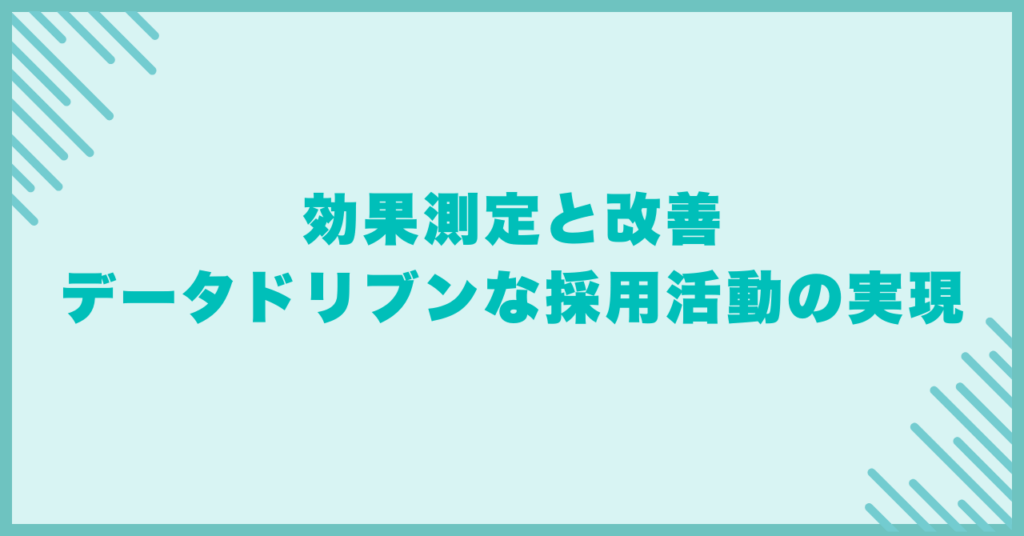
採用予算を策定し、戦略を実行するだけで終わりではありません。その効果を客観的に測定し、継続的に改善していくプロセスこそが、採用活動を成功に導く上で最も重要です。ここでは、データに基づいた意思決定(データドリブン)な採用活動を実現するための、効果測定と改善のサイクルについて解説します。
なぜKPI(重要業績評価指標)が不可欠なのか
KPI(Key Performance Indicator)とは、目標達成に向けたプロセスの進捗度合いを測るための、具体的な数値指標です。採用活動においてKPIを設定することで、これまで感覚的に捉えがちだった各プロセスの成果を「見える化」し、どこに課題があるのかを客観的に特定することができます。KPIを継続的にモニタリングすることで、問題の早期発見と迅速な改善アクションが可能となり、採用プロセス全体の最適化と費用対効果の最大化につながります。
採用プロセスにおける主要KPIと設定例
採用活動は、「母集団形成」「選考」「内定・入社」という一連のプロセスで構成されます。各段階で適切なKPIを設定し、その数値を追跡することが重要です。
| 採用段階 | 主要KPIの例 | KPIの定義と目的 |
| 母集団形成 | ・応募数 ・チャネル別応募単価 | ターゲットとなる母集団を十分に形成できているか、また、各チャネルのコスト効率はどうかを測定する。 |
| 選考 | ・書類通過率 ・一次面接通過率 ・最終面接通過率 | 選考基準の妥当性や、面接官による評価のばらつきがないかなどを分析し、選考プロセスの質を評価する。 |
| 内定・入社 | ・内定承諾率 ・採用単価 ・入社後定着率 | 最終的な採用成果とコスト効率を測定する。内定承諾率が低い場合は、内定者フォローや処遇面に課題がある可能性を示唆する。 |
PDCAサイクルを回し、継続的に採用力を強化する
KPIを設定したら、それらの数値を基にPDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)を回し、継続的な改善を図ります。
1.Plan(計画): 採用目標に基づき、KPIの目標値を設定する。
2.Do(実行): 計画に沿って採用活動を実行する。
3.Check(評価): 定期的にKPIの実績値を測定し、目標との差異やその原因を分析する。
4.Action(改善): 分析結果に基づき、採用手法の見直しや選考プロセスの改善など、次なるアクションプランを策定し、実行に移す。
このサイクルを粘り強く回し続けることで、採用ノウハウが組織に蓄積され、採用力そのものが着実に強化されていきます。
まとめ
本記事では、企業の持続的な成長に不可欠な「採用予算」について、その戦略的な策定方法からコストの最適化、効果測定に至るまで、網羅的に解説しました。
採用予算は、単なるコスト管理の枠を超え、経営戦略と深く結びついた「未来への投資」です。明確な採用目標の設定から始まり、データに基づいたチャネル選定、ROIを意識した予算配分、そしてKPIによる継続的な効果測定と改善のサイクルを回すこと。この一連のプロセスを戦略的に実行することが、採用の費用対効果を最大化し、企業の競争力を高める上で不可欠です。
採用市場の環境が厳しさを増す現代において、優秀な人材の獲得は企業の将来を左右します。本記事で紹介したアプローチを参考に、ぜひ貴社の採用活動を見直し、データに基づいた戦略的な採用予算を策定・実行することで、事業の成長を力強く加速させてください。
「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe
Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界1300名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス
⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス
⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス
などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。
