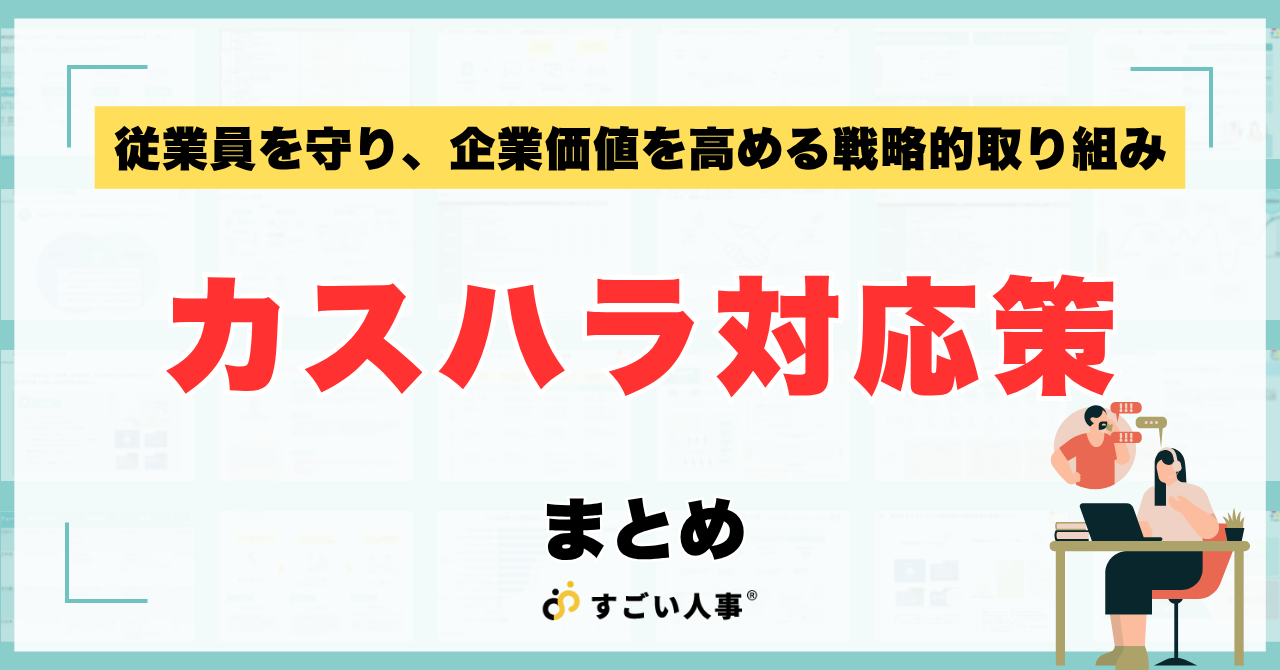
「カスハラ」が従業員に与える影響とは?企業事例や対応策まとめ
近年、顧客や取引先からの理不尽なクレームや暴言、威圧的な態度などの「カスタマーハラスメント(カスハラ)」が深刻な社会問題となっています。厚生労働省が2024年11月にカスハラの定義を明確化し、企業に対策義務づけを検討するなど、法的な対応も進んでいます。
パーソル総合研究所の調査によると、対人サービス職種の35.5%が過去にカスハラ被害を経験しており、3年以内の被害経験者は20%を超えています。これは職場内ハラスメントと同等の規模で発生していることを示しており、企業にとって無視できない課題となっています。
本記事では、カスハラが従業員に与える具体的な影響を詳しく解説し、先進企業の対応事例を紹介しながら、人事責任者や経営者が今すぐ取り組むべき対策についてまとめています。
目次
- カスタマーハラスメント(カスハラ)とは何か
- カスハラが従業員に与える深刻な影響
- カスハラが企業経営に与える深刻な影響
- 先進企業のカスハラ対策事例
- 企業が取るべきカスハラ対策の具体的アプローチ
- 法的な観点と今後の展望
- 経営者・人事責任者が今すぐ取るべき行動
- まとめ
カスタマーハラスメント(カスハラ)とは何か
カスハラの定義と判断基準
カスタマーハラスメント(カスハラ)とは、厚生労働省の定義によると「顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なもの」を指します。
正当なクレームとカスハラを区別する判断基準は、主に以下の2つの観点から評価されます。
要求内容の妥当性では、商品やサービスに実際に問題があるか、要求される対応が合理的かどうかが検討されます。商品に不良がないにもかかわらず交換や返金を求める行為、契約内容に含まれていないサービスを要求する行為などは、要求内容が妥当でないためカスハラに該当します。
手段・態様の相当性では、要求を実現するための方法が社会通念上適切かどうかが判断されます。たとえ正当な要求であっても、暴言や脅迫、長時間の拘束、土下座の強要などの手段を用いた場合は、カスハラとして扱われます。
カスハラの具体的な類型
カスハラは様々な形態で発生しますが、主な類型は以下のように分類されます。
精神的な攻撃には、脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言などが含まれます。パーソル総合研究所の調査では、「暴言や脅迫的な発言」が最も多く60.5%を占めており、「威嚇的・乱暴な態度」が57.7%で続いています。
身体的な攻撃は、暴行や傷害行為を指します。直接的な暴力だけでなく、威嚇的な身振りや物を投げつける行為なども含まれます。
継続的・執拗な言動では、同じクレーム内容の繰り返しや、何度も電話やメールを送り続ける行為が該当します。調査では17.2%の被害者がこのような行為を経験しています。
不当な要求には、土下座の強要、個人情報の開示要求、金銭的な要求などが含まれます。
業界・職種別の被害状況
カスハラの被害状況は業界や職種によって大きく異なります。3年以内のカスハラ経験率が最も高いのは「福祉系専門職員(介護士・ヘルパーなど)」で34.5%に達しています。これに続くのが「顧客サービス・サポート」の30.7%、「受付・秘書」の30.0%、「医療系専門職員(医師・看護師など)」の28.9%となっています。
また、性別・年代別の分析では、男女ともに若年層のカスハラ経験率が高く、20代では約4割が経験しており、経験の浅い従業員ほど被害に遭いやすい傾向があります。
カスハラが従業員に与える深刻な影響
心理的・精神的な影響
カスハラが従業員に与える最も深刻な影響は、心理的・精神的なダメージです。理不尽な暴言や威圧的な態度にさらされた従業員は、強い恐怖感や無力感を抱くようになります。ヤマト運輸の事例では、コールセンターのオペレーターが繰り返される暴言により恐怖で委縮し、約1か月間業務復帰が困難な状況に陥りました。
このような心理的ダメージは長期間にわたって影響を与え、特に真面目で責任感の強い従業員ほど、「私の対応の仕方が良くなかった」と自分を責める傾向があり、より深刻な精神的ダメージを受けやすくなります。
業務パフォーマンスへの影響
カスハラによる精神的ストレスは、従業員の業務パフォーマンスに直接的な悪影響を与えます。集中力や判断力の低下により、本来の業務効率が著しく悪化することが多く報告されています。
具体的には、カスハラ対応に時間を取られることで本来の業務が圧迫され、生産性が低下します。また、カスハラを受けた従業員は顧客対応に対する恐怖や苦痛を感じるようになり、積極的な顧客サービスを提供することが困難になります。
身体的健康への影響
カスハラによる継続的なストレスは、従業員の身体的健康にも深刻な影響を与えます。具体的な身体症状としては、頭痛、睡眠障害、食欲不振、胃腸の不調、耳鳴りなどが報告されています。重篤な場合には、うつ病や不安障害などの精神疾患を発症することもあります。
離職・転職への影響
カスハラは従業員の離職率上昇に直結する重要な要因となっています。東京商工リサーチの調査では、カスハラ被害により従業員の「休職・退職」が発生した企業が13.5%に達することが明らかになっています。
特に若手従業員の離職率が高い傾向があります。経験の浅い従業員はカスハラに対する対処スキルが不足しており、被害を受けやすい上に、回復にも時間がかかります。
他の従業員への波及効果
カスハラの影響は、直接被害を受けた従業員だけでなく、周囲の従業員にも波及します。カスハラの現場を目撃した従業員の約9割が不快な気分になったという調査結果があり、職場全体の雰囲気悪化につながることが明らかになっています。
カスハラが企業経営に与える深刻な影響
人材確保・定着への影響
カスハラは企業の人材確保と定着に深刻な影響を与えます。離職による直接的なコストは膨大で、採用コスト、研修コスト、引き継ぎコストなどを含めると、1人の従業員が離職することで数百万円の損失が発生することも珍しくありません。
また、カスハラ被害を放置している企業という悪評が広まれば、求職者からの応募が減少し、優秀な人材の確保が困難になります。
生産性・業務効率への影響
カスハラは企業の生産性と業務効率に多方面から悪影響を与えます。カスハラ対応に要する時間と労力は、本来の業務時間を圧迫し、全体的な業務効率が低下します。
また、カスハラを受けた従業員の業務パフォーマンス低下により、チーム全体の生産性が影響を受けます。集中力や判断力が低下した従業員は、ミスを起こしやすくなり、品質管理にも悪影響を与える可能性があります。
法的リスクと安全配慮義務
企業には従業員に対する安全配慮義務があり、カスハラ被害を放置することは法的リスクを伴います。労働契約法第5条では、使用者は労働者の生命・身体等の安全を確保するよう配慮する義務があると定められており、カスハラ対策もこの義務の範囲に含まれると考えられています。
先進企業のカスハラ対策事例
事例1:ヤマト運輸株式会社 – 実務的なマニュアルと全社的な情報共有
取り組みの背景
ヤマト運輸株式会社(従業員数約18万人)では、コールセンターで同じ顧客から「態度が悪い」「お前は向いていない。やめろ」といった暴言を繰り返し受ける事案が発生しました。対応したオペレーターが恐怖で委縮し、約1か月間業務復帰が困難な状況に陥ったことを受けて、経営層から「社員の健全な業務を守らなければならない」という指示があり、本格的なカスハラ対策が始動しました。
実態調査と対応マニュアルの作成
コールセンターのオペレーター向けアンケート調査の結果、約8割がカスハラと思われる被害に遭っていたという実態が明らかになりました。
2020年10月に作成された「カスタマーハラスメント対応マニュアル」は、弁護士への相談や過去のクレーム情報の分析を基に作成された実務的な内容となっています。マニュアルの特徴は、「カスハラ発言リスト」と「文言集」を含む実践的な構成です。
「カスハラ発言」には「死ね」「殺すぞ」などの一度でもカスハラと判断する用語が含まれ、即座に管理者に電話を交代するフローになっています。「カスハラの可能性のある発言」には「あほ」「お前じゃ話にならない」などが含まれ、一度問いかけてクールダウンを図り、収まらない場合に管理者に交代する段階的な対応を定めています。
二段構えの対応戦略
個人を傷つけるような発言をする顧客に対する二段構えのアプローチが特徴的です。まず一次対応者が「脅されているようで怖いです」など、主観的な気持ちを伝えて相手の冷静さを促します。それでも改善されない場合は、管理者が「あなたの行為は○○といった点でカスハラです」と客観的に伝えます。
全社的な情報共有システム
カスハラ行為を伴う顧客の対応を実施した際は、必ずレポートを作成し、社内データベースに登録するシステムを構築しています。これにより、どのコールセンターでも一貫した対応ができるようになり、従業員が同じ顧客から再度カスハラを受けるリスクを軽減しています。
事例2:フリー株式会社 – プロジェクト型アプローチと社外発信
プロジェクト立ち上げの経緯
フリー株式会社(従業員数1,083名、IT・サービス業)では、2022年夏にサポートデスクで「お前殺すぞ、こら」「なめてんじゃねーぞ」といった脅迫的発言を40分以上続けて受ける事案が発生しました。この事案を重く受け止めた担当者が法務部と相談したことを契機に、カスタマーハラスメント対策プロジェクトが立ち上がりました。
体系的な調査と検討プロセス
プロジェクトは、サポートデスクのメンバーに法務部や直属の上司をアドバイザーとして加えた5名体制で進められました。社内でのアンケート調査とデータ収集を行い、厚生労働省のマニュアルを読み込みながら、法務部への法律的な知識の照会を行いつつ検討を進めました。
社外への積極的な方針発信
2023年2月9日に自社HPで「カスタマーハラスメントに対するfreeeの考え方」を公開しました。公開内容は「対象となる行為」「社内対応」「社外対応」の3つの柱で構成され、カスハラに該当すると判断した場合、サービスやサポートの提供をお断りする場合があることを明記し、企業としての毅然とした姿勢を示しています。
包括的な社内対応体制
社内対応では、専門チームの立ち上げ、被害者のケア(フラッシュバックによる二次被害防止のため、直接ヒアリングではなく管理職経由で状況確認)、外部専門機関への相談体制を整備しています。
また、8項目で構成される社内向けガイドラインを作成し、過去に実際に受けた暴言や判例等を参考にした事例集を掲載しています。
企業が取るべきカスハラ対策の具体的アプローチ
基本方針の策定と組織体制の構築
カスハラ対策の成功には、経営層の強いコミットメントが不可欠です。企業は、カスハラを許さないという基本方針を明確に定め、全社に周知する必要があります。
専門的な知識とスキルを持つチームや担当部署の設置も重要です。法務部門、人事部門、現場部門の連携を図り、組織横断的な対応を可能にする調整機能が必要です。
従業員が安心してカスハラ被害を相談できる窓口の設置と、明確な連絡フローの確立も対策の基盤となります。
実践的な対応マニュアルの作成
効果的なカスハラ対策には、現場で使える具体的な判断基準が必要です。厚生労働省のガイドラインに基づきながらも、自社の業界特性や過去の事例を反映した判断基準を作成します。
状況に応じた段階的なアプローチを定義し、初期対応、エスカレーション基準、管理者対応、記録・報告、事後フォローなどの各段階を明確にします。
現場での対応を支援するため、具体的な文言集の整備も有効です。謝罪の表現、状況確認の方法、境界設定の伝え方、サービス終了の告知方法などを含めます。
従業員教育と研修プログラム
カスハラ対策の基本的な知識とスキルを全従業員に身につけてもらうため、定期的な研修プログラムの実施が必要です。特に新入社員や顧客接点の多い部署への配属者には、より詳細な研修を実施します。
理論的な知識だけでなく、実際の対応スキルを身につけるため、ロールプレイング研修の実施も効果的です。様々なカスハラ事例を想定したシナリオを用意し、従業員が実際に対応を体験できる機会を提供します。
被害者支援とメンタルヘルスケア
カスハラ被害が発生した際は、まず被害者の安全確保と心理的支援を最優先に行います。被害者を責めない、話を真摯に聞く、適切な医療機関やカウンセリングサービスの紹介を行うなどの基本原則を守ります。
カスハラ被害により休職した従業員の職場復帰には、段階的なアプローチが必要です。医師やカウンセラーとの連携により、被害者の回復状況を適切に評価し、無理のない復帰計画を策定します。
法的な観点と今後の展望
現行法制度におけるカスハラの位置づけ
現在、カスハラは労働施策総合推進法の枠組みの中で「望ましい取組」として位置づけられています。しかし、企業には労働契約法第5条に基づく安全配慮義務があり、カスハラによって従業員の心身の健康が害される場合、この安全配慮義務違反として企業の責任が問われる可能性があります。
法制度の動向と企業への影響
厚生労働省は2024年11月、カスハラの定義を明確化し、企業に対策を義務づけることを検討していると発表しました。これは、現在の「望ましい取組」から「法的義務」への格上げを意味する重要な動きです。
義務化が実現すれば、企業はカスハラ対策を講じることが法的に求められ、対策が不十分な場合は行政指導や企業名公表などの措置を受ける可能性があります。
経営者・人事責任者が今すぐ取るべき行動
カスハラ対策の緊急性と重要性
カスハラは従業員の心身の健康を脅かし、企業の生産性や競争力に深刻な影響を与える重要な経営課題です。対人サービス職種の35.5%がカスハラ被害を経験しており、もはや一部の企業だけの問題ではありません。
特に、カスハラ被害により従業員の休職・退職が発生している企業が13.5%に達していることは、人材不足が深刻化する現在の労働市場において、企業の持続的成長に致命的な影響を与えかねません。
段階的な実装ロードマップ
第1段階(緊急対応:1-3か月)
経営層のコミットメント表明、基本方針の策定、相談窓口の設置、緊急時対応フローの確立を行います。第2段階(基盤整備:3-6か月)
実態調査の実施、対応マニュアルの作成、専門チームの設置、基礎研修の実施を行います。第3段階(本格運用:6-12か月)
全従業員への研修展開、情報管理システムの構築、被害者支援体制の整備、外部機関との連携体制確立を行います。第4段階(継続改善:12か月以降)
蓄積されたデータの分析、対策の継続的改善、業界団体との連携、新技術の活用検討を行います。
投資対効果の考え方
カスハラ対策には一定のコストがかかりますが、これを単なる費用ではなく、リスク管理と競争力向上のための投資として捉えることが重要です。対策を講じないことによる損失と、対策にかかるコストを比較すると、多くの場合、対策への投資の方が経済的に合理的です。
まとめ
カスハラ対策の本質は、従業員一人ひとりを大切にし、安心して働ける職場環境を提供するという企業文化の構築です。「お客様は神様」という従来の考え方から、「お客様も従業員も大切にする」というバランスの取れた考え方への転換が求められています。
経営者・人事責任者の皆様には、カスハラ対策を通じて、従業員が誇りを持って働ける職場環境を構築していただきたいと思います。今すぐできることから始めて、段階的に対策を充実させていくことで、カスハラのない健全な職場環境を実現しましょう。

「すごい人事」情報局運営元:株式会社Crepe
Crepeでは、「人事が変われば、組織が変わる」というコンセプトのもと、⚫︎各種業界1300名の人事が在籍。工数・知見を補う「即戦力」レンタルプロ人事マッチングサービス
⚫︎1日2時間〜使えるマネージャークラスのレンタル採用チーム。オンライン採用代行RPOサービス
⚫︎人事にまつわる課題を解決へ導く、伴走型人事コンサルティングサービス
などのサービスを通して、人事課題を解決する支援を行っています。
